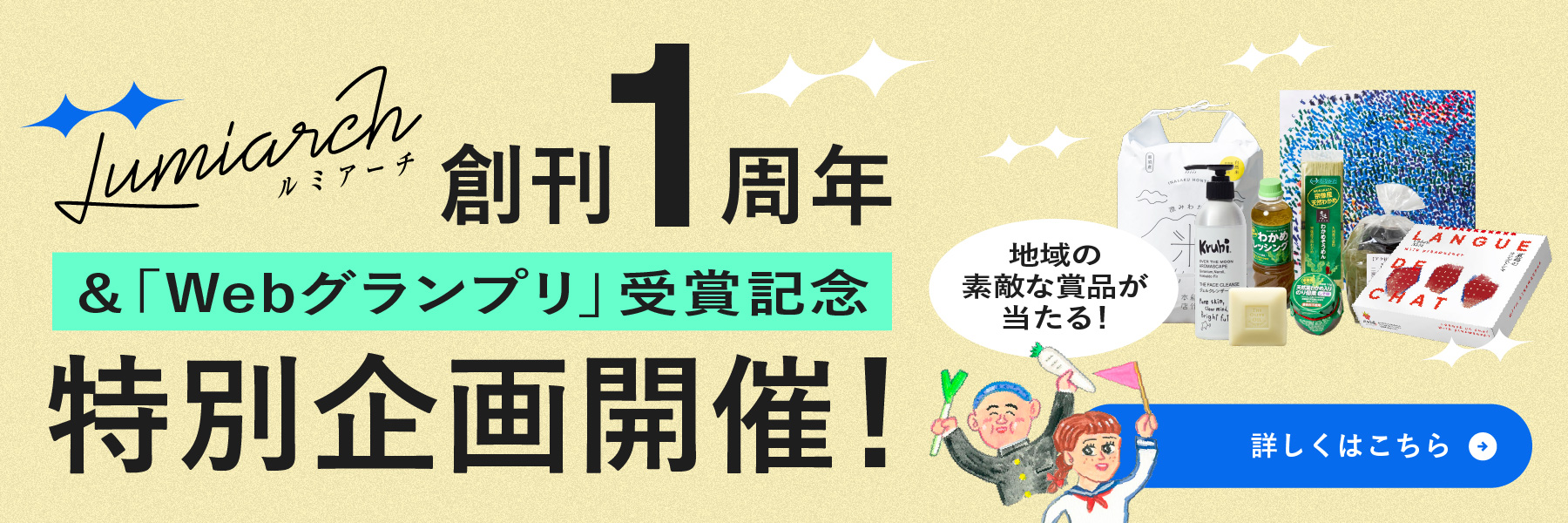ドリンク1杯の価格で、トーストやゆで卵などの朝食がセットで提供される、喫茶店の「モーニング」。
モーニングといえば名古屋——というイメージを持つ人も多いかもしれませんが、実はモーニング発祥とされる有力な地のひとつが「愛知県一宮市」なんです。
なぜ一宮市でモーニング文化が根づき、現在に至るまで愛され続けているのでしょうか? そして、いまこの文化は、地域のなかでどのような役割を果たしているのでしょうか?
その疑問を紐解くため、愛知県一宮市でモーニングを提供する「COCORO CAFÉ(ココロカフェ)」の中村有吾さん・正枝さん夫妻、一宮市でモーニング文化を盛り上げる活動を続ける「一宮モーニング協議会」の栃倉勲さんにお話をうかがいました。
喫茶店は「もうひとつのリビング」。誰もが立ち寄れる地域の店をめざして
モーニング発祥の地、愛知県一宮市。
そこでは、独自のモーニング文化が地域の暮らしを支えてきたのか。その手がかりを求めて訪れたのは、2008年の開店から地元で愛され続けている喫茶店「COCORO CAFÉ」。
店名には、「心を込めておもてなしをしたい」という想いが込められており、誰もがほっとひと息つける場所になるように歩んできたそうです。
お店を営むのは、中村有吾さん(以下、有吾)・正枝さん(以下、正枝)ご夫妻。子どもの頃から親しんできた喫茶店文化の記憶や、この地でモーニングを提供することへの想いについて、語ってくださいました。

愛知県一宮市にあるCOCORO CAFÉ。のどかな住宅街に店舗がある

日替わりモーニング。コーヒー1杯の価格で日替わりのホットサンドを楽しめる
—COCORO CAFÉは、いつも開店からにぎわっているとお聞きしましたが、モーニングの時間帯はどんな雰囲気ですか?
正枝
平日のモーニングは半分くらいが常連のお客さまですね。朝6時の開店に合わせて来てくださる方もいて、「おはようございます」と地域の方と顔を合わせるのが習慣になっています。
有吾
一宮の喫茶店には、モーニングを楽しむことが日常の一部になっている常連さんが多く訪れます。店内では、そんな常連客通しが顔なじみになって自然と言葉を交わすような、「ちょうどいい距離感のつながり」があるんですよね。
正枝
常連さん同士であいさつはするけれど、お互いに名前までは知らないということも多いんです。喫茶店の名前にちなんで、「COCORO友だち」みたいな感じですね。

COCORO CAFÉのオーナーの中村有吾さんと正枝さん
—モーニングを楽しみに訪れる地元の方にとって、喫茶店はどういった存在なのでしょうか。
有吾
学校や仕事が休みの日の朝は、喫茶店で朝ごはんを食べるというのが、多くの一宮市民の習慣になっていると思います。
僕も一宮育ちですが、子どもの頃から、わが家では土日になると家族みんなで喫茶店に出かけるのが当たり前でした。それは大人になったいまも変わりません。コーヒーを飲んで、誰かと顔を合わせてちょっと喋るという、家のリビングが地域のなかにいくつもあるような感覚です。

有吾
一宮の人はいくつかの喫茶店に顔出すことも多く、曜日ごとに違う喫茶店に通っている方もいます。「火曜はこっち、水曜はあっち」とコーヒーチケットを何冊も持ち歩いている姿も見かけます。

正枝
常連さんが亡くなってしまった際には、「お供えとしてお葬式にモーニングを持っていきたい」とご家族から頼まれることもありました。
それだけ、喫茶店でのモーニングが、一宮の家族の記憶に深く結びついているんだなと感じました。
—常連のお客さまが多いなかで、毎日の朝ごはんとなる「モーニング」は大切な存在だと思います。どんなメニューを提供しているのでしょうか?
正枝
お客さまの健康を考えて、偏った食事にならないようにこちらで考えたメニューを日替わりで提供しています。
なるべく野菜も取り入れて、家庭で食べる朝ごはんのような、身体にやさしい朝ごはんをめざしていて、今日はハムとツナのサンド。昨日はじゃがいもや玉ねぎが入った野菜サンドを提供しました。
また、COCORO CAFÉでは、パンの中にシチューやハヤシライスを詰めた「スペシャルモーニング」も用意しているので、毎日通っても気分を変えて楽しんでいただけるのではないかと思います。

COCORO CAFÉのスペシャルモーニングは、パンを器にしたシチューなど独自のメニュー。喫茶店それぞれの個性やこだわりが楽しめるのも「一宮モーニング」の魅力。

スペシャルモーニングのシチューを盛り付けている様子
地域の暮らしに染み込んだひと手間が、モーニング文化を育ててきた
一宮に暮らす人々の生活に馴染んでいるモーニング。COCORO CAFÉを営む中村夫婦のお話からは、モーニングが単なる「朝食」ではなく、喫茶店が地域の日常に溶け込む存在になっているということが分かりました。
このように一宮に深く根づいたモーニング文化は、どのようにして生まれ、育まれてきたのでしょうか。
ここで、モーニング文化を盛り上げる活動を続ける「一宮モーニング協議会」の会長を務める栃倉勲さん(以下、栃倉)に、モーニングという言葉の裏にある地域の歴史や、暮らしとともにある文化について聞きました。

一宮モーニング協議会 栃倉勲さん
—一宮市は喫茶店が多い街として知られていますが、なぜこれほどまでにモーニング文化が根づいたのでしょうか?
栃倉
もともと一宮市は、全国有数の「毛織物のまち」として栄えていました。とくに朝鮮戦争の特需を背景にした「ガチャマン景気」と呼ばれた時代には、市内の工場の織機が一回「がっちゃん」と動くたびに1万円稼げるほどだったともいわれています。
工場内の機械音が大きかったこともあり、社長さんたちは来客対応や打ち合わせのために、朝昼晩と1日何度も喫茶店を利用したんです。

1950年頃の一宮市の様子
—その頃は、喫茶店が仕事場でもあったと。
栃倉
そうなんです。すると、喫茶店側は、「せっかく何度もいらしてくれるんだから、何か添えてあげたい」というねぎらいの気持ちが生まれるもの。はじめはピーナッツを、次にゆで卵を……とサービスが増えていって、一宮モーニングの原型が育まれていったのだと思います。
当時、卵はまだ高価な食材でしたが、一宮市の西側には養鶏場が多く、地元では比較的手に入りやすかったんです。そういった土地柄の背景もあり、喫茶店のオーナーたちが、日頃の感謝を込めてコーヒーを注文した方に卵を添えるなどサービスがしやすかったのではないでしょうか。

ゆで卵とピーナッツがついた当初のモーニング ※写真はイメージです
—地域の産業と喫茶店文化が結びついていたのですね。
栃倉
そうなんです。さらに、この地域には昔から「お茶で客をもてなす文化」も根付いています。たとえば、愛知を代表する戦国武将・織田信長も、宣教師など海外からの賓客を茶会でもてなしたと伝えられています。
そういったおもてなしの感覚が、やがて喫茶店でのモーニング文化にもつながっていったのではないかと思います。時代が変わっても、「誰かのためにひと手間かける」という気持ちは、この土地にずっと受け継がれているのではないでしょうか。
—そんな一宮市に根づいたモーニング文化ですが、最近ではずいぶんバリエーションが増えていると聞きました。
栃倉
最近は、ラーメン屋さんがお粥のモーニングを始めたり、焼肉屋さんが朝だけ特別に定食を出したりと、喫茶店以外の飲食店にもモーニング文化が広がっています。

2025年版一宮モーニングマップに掲載されているラーメン店と焼肉店のモーニングメニュー。一宮モーニングマップは一宮モーニング協議会が無料配布しており、PDFデータのダウンロードも可能
—ラーメン屋さんや焼肉屋さんにもモーニングがあるんですね……!
栃倉
「モーニング=喫茶店」というイメージがあるかもしれませんが、業種に関係なく、朝の時間に何かを提供するスタイルであれば「一宮モーニング」として歓迎しています。
実際に私たちモーニング協議会も『一宮モーニング三カ条』を掲げて、喫茶店に限らない広がりを大切にしています。
【一宮モーニング三カ条】
1.一宮市内の飲食店にて提供されること
2.起源に倣って、卵料理を付けること
3.できるだけ一宮産の食材を使うこと
栃倉
ただ、これはあくまで原則で、大切なのは一宮市のモーニング文化を盛り上げたいという想いです。
モーニング文化をこれからも発展させていくには、やはり新しい発想や挑戦も大切です。多くのお店に、「モーニングで地域の人たちをもてなしたい」という気持ちがあれば、地域に自然と根づいていくはず。それが一宮らしさにもつながっていくと思っています。

有吾
「おもてなしの気持ち」を第一に、喫茶店ならではのあたたかい雰囲気も大切にしながら、他業種など、ほかのスタイルとも共存していけたらと思っています!
モーニング文化が地域社会で果たす役割と今後
—モーニングは地域の人たちの暮らしにおいて、実際にどのような役割を果たしていると感じますか?
正枝
モーニングにいらっしゃるお客さまにはお年寄りの方も多く、「ここに来るのが日課なんです」「これがリハビリみたいなもの」とおっしゃる方もいます。毎日歩いて喫茶店に来ていただくことで健康の維持にもつながりますし、誰かと顔を合わせて言葉を交わすだけで、元気になれますよね。
有吾
逆に、毎日来ていた方が突然来なくなってしまうと「どうしたのかな?」と心配になりますし、ほかのお客さまが「あの人、最近見ないね」なんて心配して声をかけてくれることもある。喫茶店を通じて生まれる、そういった地域のつながりは、いまの時代には貴重なものだと思います。

—日頃から、顔を合わせる場があることで、地域のなかに緩やかな見守りの機能も生まれているんですね。
有吾
そうですね。また、こういった緩やかなつながりには、防犯的な側面もあると感じます。一宮警察署と連携し、防犯について考える講習会をCOCORO CAFÉで開いたこともあり、喫茶店を通じて地域全体でお互いを見守る雰囲気が少しずつ広がっていると感じます。
また、警察署が作成したコースターに、地域の小学生たちが「詐欺に気をつけて」といったメッセージを手書きしたものを店で配り、特殊詐欺被害を防ぐ活動にも協力しました。

コースターに子どもたちが手書きで詐欺対策のメッセージを記載している

正枝
「110番の家」のような感覚で、お店に来てくれる子どもたちもいるんですよ。
地域に根づいた日常を言葉に変えて、文化として未来につないでいく
—今後も一宮のモーニング文化を守り、次の世代へつないでいくために、どのような取り組みをされているのでしょうか?
栃倉
一宮モーニング協議会では、「一宮モーニングマップ」を作成し、観光案内所や市内の店舗に設置しています。
また、これまでモーニングのNo.1を決める『モー1グランプリ』を開催したほか、昨年からは地域のお店が集まりモーニングメニューを提供するイベント『モーニングマルシェ』も実施しています。
それから、少し意外な組み合わせかもしれませんが、オリジナルの盆踊り “一宮モーニング音頭”もつくっていて、一宮市内の夏まつり会場で披露されています。こうした取り組みも、地域の人たちに親しみを持ってもらい、文化として根づかせるためにはとても大切なことだと思っています。

2025年の一宮七夕まつりで披露した、一宮モーニング音頭の様子
栃倉
また、喫茶店のオーナーは通常、横のつながりが少ないのですが、モーニング協議会が主催して、地域のお店の人同士が集まって、懇親会のような形で悩みやアイデアを気軽に共有できる場もつくっています。

有吾
喫茶店は一人でやっている方も多いので、横のつながりがあるだけでも安心感がありますね!
—モーニング文化を守る人として、有吾さんと正枝さんは、今後どのようにCOCORO CAFÉを営んでいきたいですか?
有吾
やはり、お店を長く続けることが一番かなと思います。COCORO CAFÉだけでなく、一宮で5年、10年と続けていける喫茶店が少しでも増えてくれたらうれしいです。「モーニングをやってみよう」と思ってくれる人がいたら、背中を押してあげられるような存在になりたいなと感じますね。
また、地域の人を支えたり、人と人をつないだりするこのモーニング文化を、喫茶店のオーナーとして未来に引き継いでいきたいと思います。
正枝
私は、お店を長く続けるうえで、お客さまの健康が大切だと感じています。コロナ禍にお客さまの足が遠のいたとき、空いた時間を使って店内でできるイベント「椅子ヨガ」の企画をはじめたのですが、みなさんが楽しんでくださって。月に1回、30分くらい体を動かして、そのあと一緒にお茶をするというのが、私の元気にもつながっています。
地域のなかで、店側もお客さまも無理なく楽しくできることを積み重ねることで、喫茶店やモーニング文化も息長く続いていくのではないでしょうか。

—モーニングは地域の人の暮らしを支える存在になっているんですね。やはり身近な習慣のなかに、地域の魅力が隠れていることがあるのかもしれませんね。
栃倉
そうですね。一宮市のモーニング文化も、最初から「文化」として意識されていたわけではなく、当たり前すぎて見過ごしてしまうようなものでした。でも私たち協議会が「一宮モーニング」という名前をつけたことで、喫茶店のオーナーたちは「これは地域の魅力なんだ」とあらためて気づかされたのです。
どの地域にも、その土地ならではの習慣や日常があると思います。当たり前のなかにある価値を見つけ出し、言葉にして共有していく。これが地域活性化をしていくためのステップとして大切なポイントなのではでしょうか。

この記事の内容は2025年9月11日掲載時のものです。
Credits
- 取材・執筆
- 竹内ありす
- 写真
- 安井信介
- 編集
- 野村英之(プレスラボ)、牧之瀬裕加(CINRA,Inc)