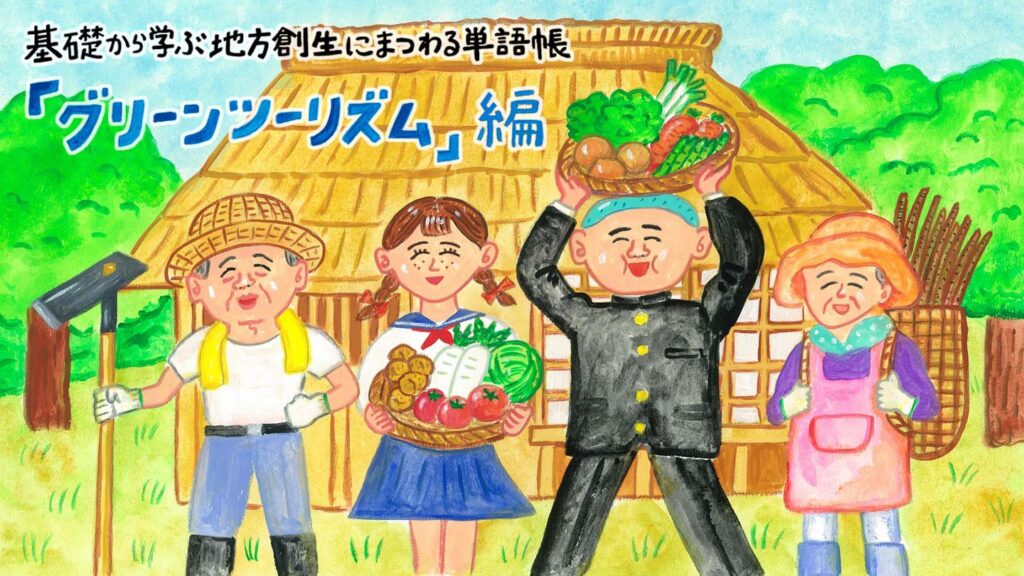みなさんは「スマートシティ」という言葉を聞いたことがありますか? まちづくりや地方創生の文脈でよく見る言葉ですが、直訳すると「賢い街」……? 実際スマートシティとは、どういう意味でしょうか。
「大好きな地元に貢献したい」という想いが強いカンタ&めぐりは、地方創生について猛勉強中。そんな二人が地域の未来をより良くするために、ヒントとなるキーワードを集めて単語帳を作成する連載「基礎から学ぶ、地方創生にまつわる単語帳」。
今回二人が学ぶ単語は、スマートシティです。
スマートシティの定義から事例、課題についてまで、地方創生や地域政策に詳しい牧瀬先生に話を聞きました。
「スマートシティ」とは?簡単に解説
スマートシティの定義と起源

めぐり
牧瀬先生、最近よく「スマートシティ」という言葉を聞くんですが、いったいどんな街なんですか?
牧瀬
国や自治体によってさまざまな定義がありますが、それらをまとめて簡単に要約すると、スマートシティとは「テクノロジーを用いた先端技術によってさまざまな課題を解決したり、経済を活性化させたりすることで、人々の生活がより快適になる街」です。
ここでいう「さまざまな課題」とは、環境・エネルギー問題や人口増加・減少に伴う社会インフラの整備、交通・モビリティの改善、行政サービスの最適化など、グローバルな範囲からローカル特有のものまで多岐にわたります。
実は、スマートシティという言葉が国際的に使われはじめたのは1980年代からで、けっこう前からある言葉なんですね。当時としてはかなり先進的な構想だったものが、昨今の技術の進歩によって実現の可能性が高まったことで、いまあらためて注目されています。
海外と日本のスマートシティの違い

めぐり
世界的にもスマートシティの取り組みは広がっているんですか?
牧瀬
そうですね。ただ、海外と比べて日本のスマートシティの取り組みは少し独特です。世界的には「人口増加に対応するための手段」として推進されている事例が多いのですが、とりわけ少子高齢化が進んでいる日本においては「人口減少に対応するための手段」としてスマートシティの構想に着目されることが多いんです。
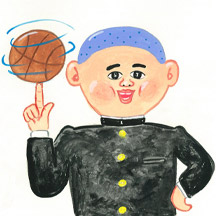
カンタ
へえー、日本とそのほかの国で考え方が違うんだ!
牧瀬
ここでのポイントは、スマートシティは「目的」ではなく「手段」だということです。各国の行政の目的は「あらゆる住民の福祉、幸福感の最大化」であり、そのための手段としてスマートシティをめざしていく……という順番で考える必要があるんです。
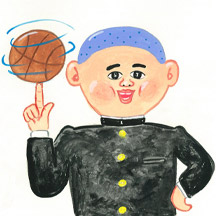
カンタ
幸福感の最大化ってどんな状態なの?

めぐり
最近よく聞く、「ウェルビーイング(Well-being)」ってやつじゃない? 住民が体も心もよい状態で、自分らしく豊かな生活を送れている状態って聞いたよ。先生、どうですか?
牧瀬
そのとおりです。各国の行政が目的とする幸福感の最大化とは、一人ひとりがより良く生きられることを指しています。補足すると、さまざまな要素が相互に作用して全体としてバランスが取れた状態といえます。
スマートシティの日本の事例。茨城県、愛媛県の取り組みを紹介

めぐり
調べてみると、日本でもいろんなスマートシティの取り組みが行われていました。

めぐり
牧瀬先生が注目している事例はありますか?
茨城県境町|自動運転バスの運用や端末の配布
牧瀬
日本のスマートシティの取り組みで、私が注目している事例を紹介しますね。
まずは、茨城県境町の事例について。当町ではスマートシティの推進に力を入れていて、交通や医療でのICT導入なども進んでいますが、とりわけ注目されているのが、2020年に国内の自治体ではじめて実用化した自動運転バスの運用です(*1)。
車の運転が難しい高齢者らの移動難を解消し、地域住民のウェルビーイング(Well-being)を向上する手段として期待されています。

自動運転バスのイメージイラスト
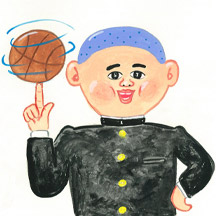
カンタ
自動運転って、人が運転してないってことですか!?
牧瀬
現時点では安全確認のためにオペレーターが同乗していますが、バスの運転自体は自動で行われています。将来的には遠隔でのオペレーションのみで運行する状態をめざしています。

めぐり
人が運転しなくて済むなら、採算が取れない地方のエリアでもバスを走らせられるようになる、ってことでしょうか?
牧瀬
そのとおりです。もう少し先の話にはなりそうですが、自動運転技術が進歩すれば、バスの走るルートの自由度もあがっていくでしょう。それこそタクシーを呼ぶ感覚で、バスが自宅まで迎えに来てくれるようになる未来が実現するかもしれません。
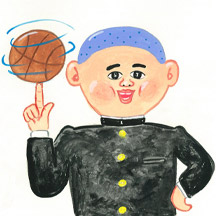
カンタ
おお、すげー! 足の不自由なおじいちゃんおばあちゃんは、すごく助かりそうだな!
牧瀬
そうですね。自動運転バスによって、高齢の方も気軽に出かけられれば運動にもなり、筋力の低下を防ぐことができます。また、茨城県境町では自動運転車のほかにも、特定保健指導(生活習慣病の発症リスクが高く改善が必要な方)の対象者にウェアラブル端末を配布し、そこで取得したデータをもとに遠隔での健康指導を行っています。
ほかにもスマートシティの施策として、スマホでのチャット機能を活用した24時間対応の健康サービスも併せて展開するなど、高齢者の健康寿命を伸ばす取り組みを充実させています。

めぐり
スマートシティは「最新のもの」「都会のもの」というイメージが強かったんですが、先生の言うとおり、住民の幸福のために地域の課題を解決し、住民が安心して暮らせるようにしていくための取り組みなんですね。
愛媛県西条市|ICTを活用した教育
牧瀬
愛媛県西条市では、自治体が「スマートシティ西条」という将来ビジョンを掲げ、「地域の誰もがつながり、安全・安心に、豊かで快適な生活を送ることのできるまちづくり」をめざすために、市民の健康づくり、子育て支援、高齢者福祉などの分野でICTを活用した事業を積極的に展開しています。
そのなかでも、西条市が特に早期から注力していた取り組みが、教育分野のICT活用です。私は市政に関わらせていただいたのですが、2012年度よりモデル校で電子黒板とデジタル教科書、校務支援システムの導入を開始し、2015年度内に市内すべての学校に整備されました。
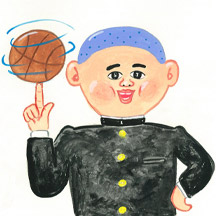
カンタ
全部の学校に! お金かけたんだなあ。
牧瀬
田舎の小さな学校では生徒も教職員も少なく、多学年を一緒に教えているところもあるんですね。そうすると、どうしても授業の質は落ちてしまいます。西条市ではこの課題の対策として、複数の学校の教室をオンラインでつないで合同授業を行う「バーチャルクラスルーム」を導入し、小規模校の教育状況を大きく改善しました。実際に授業を受けた小学生からは、中学で一緒になる児童と入学前に同じ授業をうけることで一体感がもててよかったという声もあります。

バーチャルクラスルームの様子(画像提供:西条市教育委員会)

めぐり
一口にスマートシティといっても、いろんな事例があるんですね。
牧瀬
そうなんです。ほかの自治体ではエネルギーの効率化や、行政システムの刷新に注力しているところもあります。スマートシティで大事なのは「住民の幸福度の最大化」であり、向き合うべき課題や取り組む優先度は自治体によって変わってきます。
二人の住んでいる街でも、きっと何かしらのスマートシティに関連する取り組みが行われていると思いますよ。ぜひ、興味を持って調べてみてくださいね。
スマートシティが進むとどんな未来になる?
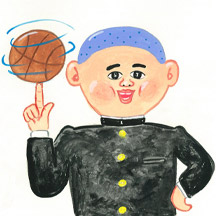
カンタ
スマートシティ化がどんどん進んでいくと、未来の街はどんな景色になるだろう……空飛ぶ車がビュンビュン飛び交うような感じになったりするんですか?
牧瀬
そこまでいくには、まだまだ時間がかかりそうですね(笑)。けれども、教育や交通、医療やエネルギー分野など、さまざまな公共インフラのDX(デジタルトランスフォーメーション)が進んで、私たちの生活はより便利に、より豊かになっているはずです。
成果の出たスマートシティの取り組みは徐々にほかの自治体でも取り入れられ、ゆくゆくは全国的なスタンダードになっていくでしょう。自動運転バスなどは、近い将来あらゆる街で運用されるようになると思いますよ。
スマートシティ実現に向けた課題

めぐり
スマートシティ化を進めていくにあたって、どんな課題がありますか?
牧瀬
資金の調達やプライバシー保護など、スマートシティの実現に向けて課題はたくさんありますが、直近で最も懸念するべきなのは、デジタルデバイド(インターネットなど情報通信技術を使える人と使えない人のあいだに生まれる格差)の問題だと感じています。
デジタルネイティブ(生まれたときからインターネットが身近な世代)にとってはメリットしかない施策でも、テクノロジーを使いこなせない、あるいはその恩恵を受けづらい人たちにとっては逆に不便になってしまうこともあります。
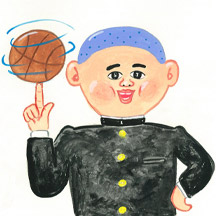
カンタ
たしかにそうだよな。バスの乗車予約や役所でする手続きがすべてオンライン申請になっちゃったら、うちのばあちゃん苦労しそうだな。
牧瀬
そうですね。スマートシティ化を進めていくにあたって、特に高齢者層に向けての配慮がないと、そこに大きな格差が生まれてしまいます。
スマートシティの課題を解決するための取り組み
牧瀬
スマートシティ実現に向けた課題の一つ「デジタル格差の解消」へのアプローチとして、一部の自治体ではデバイスを配布したり、使い方の講習を開催したりして、デジタル格差の解消に向けたアプローチを実施しています。
ただ、今後ますます高齢化が進んでいくことを考えると、自治体単位の取り組みだけではなく、産官学がしっかりと連携しながら「誰も取り残さないスマートシティ」の整備を進めていくことが強く求められるでしょう。ここまで紹介してきた事例でも、やはり背景に国からの援助、企業の技術協力があってこそうまく機能しているものが多いです。
最初にお伝えしたとおり、スマートシティの目的は「あらゆる住民の福祉、幸福感の最大化」であり、一部の人にメリットが偏らない施策であることが不可欠です。「最先端の技術を取り入れる」という手段が目的化しないよう意識しなければいけません。

めぐり
そっか……。それぞれの地域の特徴をふまえ、住民が求めていることに合わせた対応が大切なんですね。
牧瀬
まさにそうです。「この施策はある地域で有効だったけど、別の地域でやったら損をする人たちがたくさん出てきてしまった」なんてことも、課題として考えられます。本当に街に必要なスマートシティのかたちを模索するには、行政と企業、地域住民が積極的に意見交換をする必要があります。
最近では市民参加型のプロジェクトを立ち上げて、住民の声を行政の意思決定に取り入れようとする自治体の動きも増えています。住民としても理想のスマートシティを一緒に考えていくために、自治体の意見箱に投書してみるなど、小さなところから声を届けるアプローチができるといいですね。

めぐり
私たちの未来のためにも、街の取り組みに意識を向けていくことが大事なんですね。先生、ありがとうございます。勉強になりました!
スマートシティを簡単にまとめると……
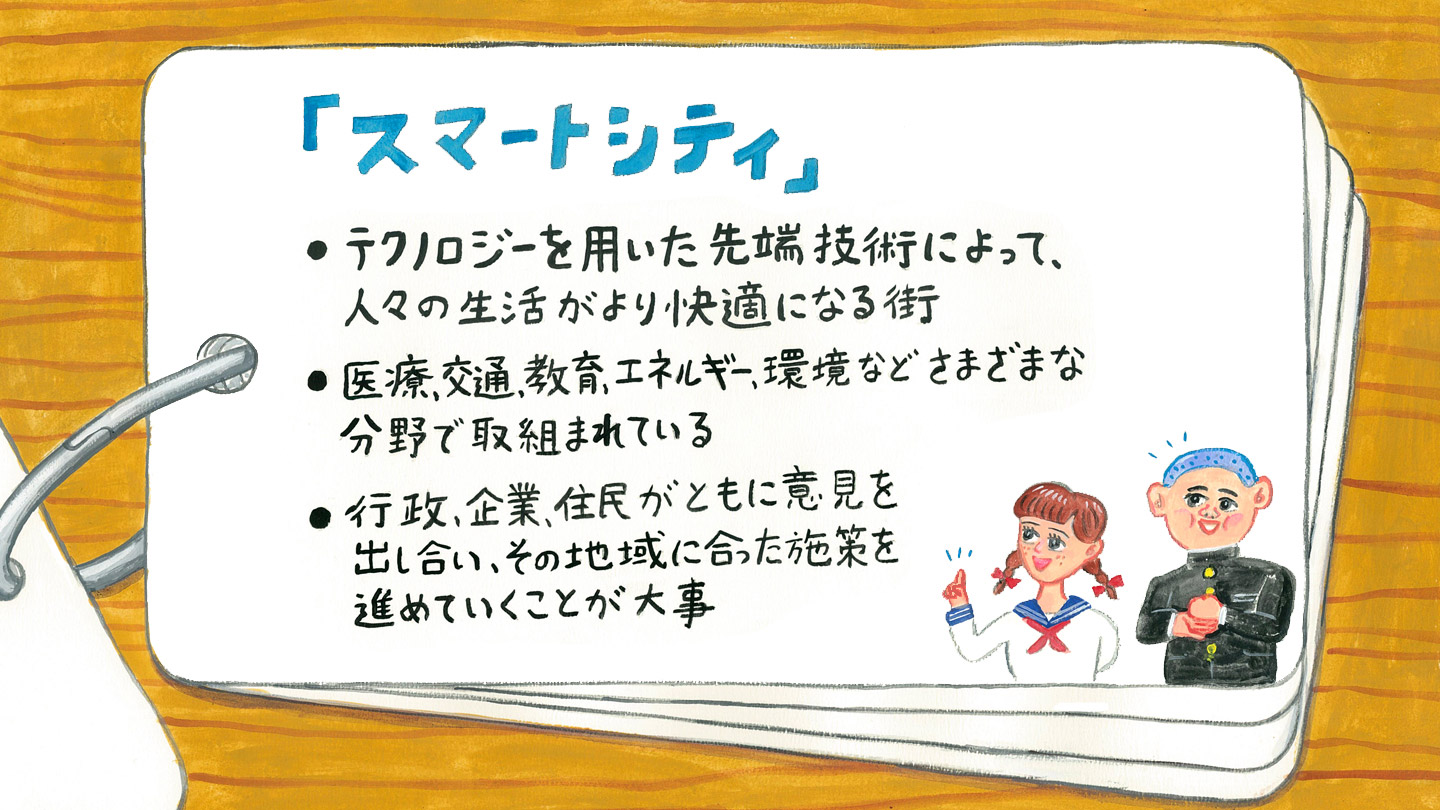
- スマートシティとは、テクノロジーを用いた先端技術によって、人々の生活がより快適になる街のこと
- 医療、交通、教育、エネルギー、環境などさまざまな分野で取組まれている
- 行政、企業、住民がともに意見を出し合い、その地域に合った施策を進めていくことが大事
*1 茨城県境町「境町で自動運転バスを定常運行しています【自治体初!】」
記事内のイラストはイメージです。
この記事の内容は2025年1月31日掲載時のものです。
(2025年4月21日 一部更新)
Credits
- 監修
- 牧瀬稔
- 執筆
- 西山武志
- イラスト
- ヘロシナキャメラ
- 編集
- 森谷美穂(CINRA, Inc.)