Theme考える
お城も神社も舞台に。元日本代表・細田雄一が語るトライアスロンの可能性
- 公開日

地域の自然や街を舞台に、海や湖を泳ぎ、自転車で風を切り、大地を駆け抜けるトライアスロン。世界中に競技者やファンがいるスポーツですが、「マラソンなどと比較してもハードルが極めて高そう」といったイメージもあるかもしれません。
でも、実際は距離別などで複数のカテゴリーがあり、初心者からベテランまで、自分のペースで楽しめる懐の深いスポーツということをご存知ですか? 最近は健康づくりやレジャーとして気軽に楽しむ人も増えているそう。
さらに、全国各地で開催される大会では、その地域の文化や歴史を盛り込み、観客や選手が地元の人々と触れ合えるよう工夫されているのも魅力です。単なる競技イベントにとどまらず、地域と人を結びつける一つのきっかけになっています。
そんなトライアスロンの魅力や楽しみ方を、元日本代表トライアスリート*1・細田雄一さん、公益社団法人トライアスロンジャパンの坂田洋治マーケティング事業局長にうかがいました。
*1 トライアスロン競技に参加する選手のこと
限界に挑むだけじゃない、自然を味わい、仲間と交流する喜び
―トライアスロンというと「ハードなスポーツ」という印象を持つ人も多いですが、実際はどんな競技なのでしょうか?
細田
おっしゃるとおり、本気で競技に打ち込めばとてもハードなスポーツです。しかし、アスリートとして取り組んでいる選手もいますが、多くの人は健康維持のため、あるいは趣味として、自分のペースで楽しんでいます。
海上のコースではさわやかな潮風を受けながら泳ぎ、山間コースでは木々のあいだを走り抜け、自然と一体になれます。フィニッシュした瞬間に味わう達成感や充実感、爽快感は言葉では言い表せないほど。だからこそ、ある人にとっては「競技」であり、ある人にとっては「ライフスタイルの一環」でもある。トライアスロンは、多様で奥深い世界なんですよ。

トライアスロンの魅力について語る細田雄一さん(右)と坂田洋治さん(左)
坂田
こうした多様な楽しみ方ができるのは、トライアスロンにいくつかの距離や種目があるからです。体力や経験に応じて、自分に合ったスタイルを選べます。
主な種目を挙げると、過酷さで知られる「アイアンマンレース」、国際大会の種目にも採用されている「スタンダードディスタンス」、そして距離をさらに短縮した「スプリントディスタンス」などがあります。
―いまは、体力や楽しみ方に合わせて、より参加しやすくなっているんですね。
坂田
そうですね。1974年の誕生から約50年が経ち、トライアスロンという競技そのものの性質も変わってきました。かつては「自分への挑戦」という意味合いが強かったのですが、最近は「仲間と一緒に時間を共有したい」「同じ目標に向かって頑張りたい」といった、人とのつながりを目的に参加する人も増えてきています。
細田
いまでは、トライアスロンがコミュニケーション手段の一つになっていますよね。
朝のプールでの練習でも、出勤前に仲間とおしゃべりしながら泳いでいる会社員の方をよく見かけます。練習後はシャワーを浴び、モードを切り替えてそのまま出勤するのです。ハードに見えるかもしれませんが、むしろそれが仕事によい影響を与えることも少なくないそうです。
時間や経験を分かち合える「場」として、トライアスロンはとてもよい役割を果たしていると感じます。

初レースの「ダントツ最下位」から国際大会へ。細田雄一の意外な出発点
―細田さんは現役時代に日本代表として活躍。現在はコーチ業を通じて後進の育成、競技の普及に尽力されています。そもそも、どんなきっかけでトライアスロンをはじめたのでしょうか?
細田
私は徳島県出身なのですが、小学5年生のときに隣の愛媛県で開催されたトライアスロンの大会に出場したのがはじまりです。
いや、「出場させられた」と言ったほうが近いかな。
姉が出てみたいと言い出し、家族で応援に行ったつもりが、なぜか私もエントリーさせられていて。自転車も持っていなかったので、足が届かない父の自転車を借りて出場しました。完走はしたものの、結果はダントツのビリ。そのときは「二度とやるか」と思いました(笑)。

―散々な思い出だったのに、どうしてそこからのめり込んでいったのでしょう?
細田
それも姉の影響ですね。中学2年生のとき、一緒にオーストラリアへ留学し、姉が現地の強豪トライアスロンクラブに入ることになって。それを見て「自分もやってみようかな」と思ったんです。
当時のオーストラリアはトライアスロン最強国で、そのクラブには世界ランキング上位の選手たちが所属していました。最初はまったく通用しませんでしたが、15歳のときに州の選手権で優勝したんです。
そこから、オーストラリアのジュニアの全国選手権にも出場し、知り合った仲間と共同生活をはじめるなど、生活の中心が徐々にトライアスロンになっていきました。
―競技者として本格的に活動をスタートしてからは、世界各地の大会に出場してきたと思います。各地でどんな景色や人との出会いがありましたか?
細田
訪れた国や地域はたくさんあります。トライアスロンの大会を誘致する地域は、それだけ誇れる自然や文化を持ち、自分たちの土地に自信を持っていることが多いんです。なので、どこに行っても感動的な体験がありました。
なかでも特に印象深いのは、スウェーデンのストックホルムです。中立国として第一次・第二次世界大戦などの被害をほとんど受けなかった歴史があり、中世の街並みがいまも残っています。
大会では、宮殿の敷地を自転車で走り抜けたり、何世紀も続く魚屋さんやパン屋さんの前を通過したりと、街の歴史を感じさせるコースが設定されていました。景色の美しさはもちろん、中世から受け継がれてきた計画的な都市構造を肌で実感できました。
震災から12年。「復興」から「日常」へ、『七ヶ浜大会』の新たなテーマ
―坂田さんは大会を運営する立場として、各地域でトライアスロン大会を開催するにあたり、特に意識していること、大切にしていることは何でしょうか?
坂田
先ほど細田さんがおっしゃったことにも近いですが、その地域の特性を踏まえ、地元の人たちが誇りを持てる大会づくりを心がけています。魅力的な風景、グルメ、歴史や文化など、さまざまな要素がありますが、トライアスロンという競技を通じて、どうやってその地域のストーリーを表現するかが最も重要だと考えています。
たとえば、大阪城で開催する大会では、お城の濠(ほり)をスイムのコースとして利用させてもらっています。実は世界的に見ても、城に濠があるのは珍しい特徴なのです。そうした文化を世界に発信しながら、地元の方々にも「自分たちが暮らす場所のよさ」をあらためて感じてほしいという思いがありました。


2025年5月に大阪で開催された『アジアトライアスロンカップ』。大阪城の濠を泳ぎ、大阪城公園を自転車で駆け抜けるトライアスリートたち(©Shugo TAKEMI/Triathlon Japan Media)
―地元の人にとっては当たり前でも、外から見れば唯一無二の風景や文化はたくさんありそうですね。
坂田
本当にそう思います。広島県の宮島で大会を開催したときは、厳島神社の魅力を伝えるため、スタート前にウェットスーツ姿の選手たちが宮司さんから安全祈願のお祓いを受け、そのまま大鳥居の横からスイムをスタートする演出にしました。選手たちには、海中に立つ神社ならではの、ここでしかできない特別な体験をしてもらうことができました。
―坂田さんが運営として携わったなかで、特に印象深い大会を挙げるならどれですか?
坂田
宮城県の七ヶ浜で毎年行われている『みやぎ国際トライアスロン仙台ベイ七ヶ浜大会』です。30回以上も続く歴史ある大会ですが、2011年の東日本大震災以降は「復興イベント」としての意味合いも強まっていました。震災では大会開催地域も甚大な被害を受けるなかで、「トライアスロンに何ができるのか」を考えながら大会を運営してきました。
震災後は「復興」というテーマを強く打ち出しながら、大会の開催やパラリンピアンを地元小学校へ派遣しての交流を重ねることで、地元住民のみなさまに元気をお届けしたいと願っていました。そのなかで、地元のみなさまと対話し、ともに行動することで、2025年からは「日常」や「生活の向上」という意識へとシフトしつつあることを感じています。



2025年7月開催『第31回みやぎ国際トライアスロン仙台ベイ七ヶ浜大会』。トライアスリートたちが松島湾を泳ぎ、海岸線や市街地を駆け抜けた(©Shugo TAKEMI/Triathlon Japan Media)
坂田
長い時間をかけて取り戻した日常の価値を、これからどう高めていくか。そんな想いもあり、2022年からは本大会とは別に「健康ゆるゆるトライアスロン」というプログラムを実施してきました。自分のペースでスイム・バイク・ランの3種目をのんびり楽しみ、運動を楽しむことや健康寿命を延ばすことを目的として取り組んでいただいています。

自分のペースで楽しめる「健康ゆるゆるトライアスロン」(©Triathlon Japan Media)
―大会のテーマや目的も、その時々で変わっていくと。
坂田
そうですね。ただ、私たちだけの想いで動くのではなく、地域の方々と密にコミュニケーションを取り、同じ目線で進んでいくことが大切です。私たちはよく「伴走」という言葉を使います。
七ヶ浜でも、長年地域のみなさんと伴走しながら運営を続けてきたからこそ、考え方や意識の変化に少しずつ気づくことができました。そうした変化を受けて、「それなら、大会も復興から日常へと一歩進んでいいのではないか」と思えるようになったのです。

スポーツで街を動かす。トライアスロンが挑む地域課題
―トライアスロンの大会を行うには地元の人々と密にコミュニケーションを取り、その地域を深く理解する必要がある。思った以上に、地域に根ざしたスポーツなんですね。
坂田
そのとおりです。細田さんは長年千葉県の館山で、トライアスロンを通じて地域の人々に伴走し、地元の課題にも向き合っていますよね。

細田
地域貢献というとおこがましいですが、現役晩年の2018年から家族で館山に移住し、トライアスロンを通じた活動を続けています。館山は合宿でよく訪れていましたし、国際大会の出場を決めた大会が開催された場所でもあり、特別な思い入れがありました。それでも、こんなに長く住むとは思っていませんでしたけどね(笑)。
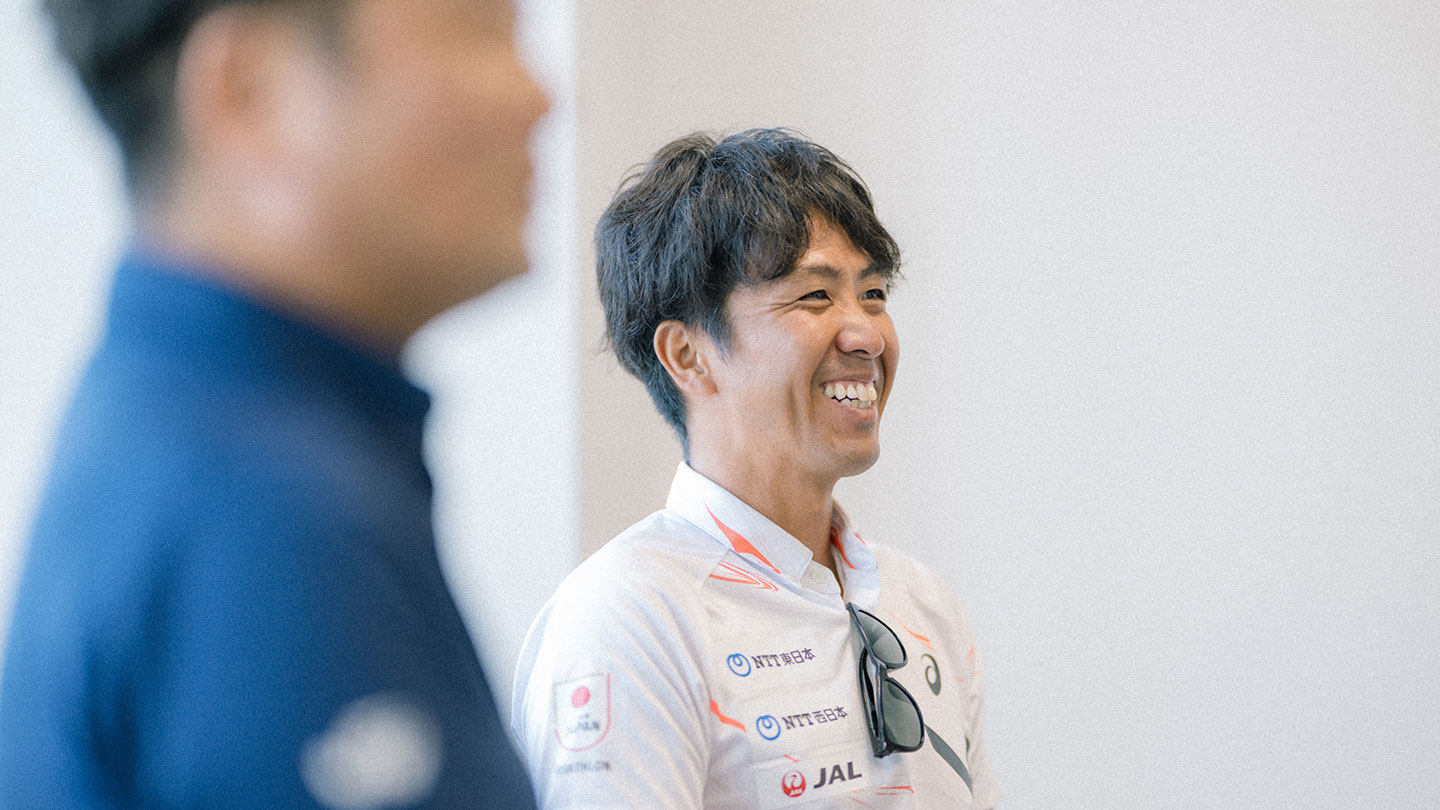
―館山に住み続ける決め手になったのは何でしょうか?
細田
一番は、やはり「人」です。現役を引退するときに館山を離れることも考えましたが、そこで頭に浮かんだのが、地元の人たちの顔でした。練習をサポートしてくれた人、応援してくれた人、一緒に楽しく汗を流した人。そんな方々に少しでも恩返しをしたいと思ったんです。
それで、選手時代には実現できなかったことに挑戦しはじめました。地元でクラブを立ち上げてコーチを務めたり、館山のスポーツ審議会に入り、イベントの企画やスポーツ関連施設の有効活用を議論したり。こうしたスポーツやトライアスロンを通じて街を盛り上げる活動で、地元のみなさんの毎日をもっと健康的で楽しいものにできたらと思っています。
最近は、トライアスロンでも使えるスポーツタイプのレンタサイクルを取り入れた観光パッケージも構想中です。自転車で館山の名所や海鮮のおいしいお店を巡りつつ、トライアスロンのセッションを行うとか。たとえば、水深18メートルの海中に祀られている「海底神社」などの観光資源とトライアスロンを組み合わせたパッケージをつくり、一般的なツアーでは味わえない景色を楽しみながら、館山ならではの魅力を体感してもらえる企画なども考えたいですね。
坂田
館山も地域としていくつかの課題を抱えていると聞きます。だからこそ、トライアスロンのように自然のフィールドや観光資源を活かせるスポーツには大きな可能性があると思うんです。
地域と連携したトライアスロンの活動を全国に広げ、各地で想いを持ったトライアスリートが、細田さんのように地域で活躍できれば、日本全体を地方から盛り上げていけるはず。考えただけで、すごく面白いことになるんじゃないかとワクワクしますね。
街と観客を巻き込む、新しいトライアスロンの楽しみ方
―トライアスロンが未来に向けて発展していくためには、どんな課題が挙げられるでしょうか?
坂田
やはり、「トライアスロンのファンをいかに増やしていくか」ということに尽きます。競技する人だけでなく、トライアスロンそのもののファンを増やすことですね。現在、トライアスロンジャパンの会員の9割以上は競技者ですが、「トライアスロンはやらないけど観るのは好き」という人が増えれば、このスポーツの可能性が広がります。
そのためには、野球やサッカーのように、観戦するだけで楽しめるような工夫や演出が必要になってくると思います。

―2025年5月に横浜で開催された『ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ』『ワールドトライアスロンパラシリーズ』では、観戦体験を向上させるアプリが導入されましたね。
坂田
はい、「World Triathlon Championship Series YOKOHAMA NAVI powered by NTT EAST」です。私たちもアプリの開発に少し関わりましたが、新しいファンの獲得に非常に有効だと感じています。

アプリ「World Triathlon Championship Series YOKOHAMA NAVI powered by NTT EAST」の使用イメージ(資料画像)
坂田
アプリを使えば、アイデア次第でさまざまな施策が可能です。たとえば大会当日は、会場周辺の名物グルメガイドや、選手が開催地の名所や歴史を案内するコンテンツを発信するとか。また、選手の練習密着動画などを配信すれば、大会が開催されない時期でもトライアスロンに親しみを持ってもらえます。

『ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ』『ワールドトライアスロンパラシリーズ』では大会運営に携わるキッズプログラムを実施し、小学生を中心とした子どもたちが参加。プログラム「こどもスポーツ記者」では、自分たちの体験や学びを新聞記事にまとめた
細田
あとはトライアスロンの「見せ方」も工夫の余地がありますよね。ランもバイクも、選手が目の前を通り過ぎるのは一瞬で、また戻ってくるまでけっこう時間が空きます。スイムにいたっては、観戦自体が難しい。観客からすると「待ち時間が長い」という課題があるんです。
だからこそ、その待ち時間をどう楽しめるかが大事だと思います。たとえばコース沿いに特別感がある「〇〇シート」という応援スペースを設ければ、名所や景色を眺めながら飲食ができ、お目当ての選手が近づいたら全力で応援する、といった楽しみ方もできるようになります。さらに、アプリで選手の位置情報を表示したり、中継映像を配信したりすれば、より臨場感のある観戦ができます。
坂田
最近では、オンラインでバーチャル空間に集まり、一緒に練習や交流を楽しんだり、大会に参加できたりする「トライアスロンeスポーツ」の取り組みも広がっています。トップアスリートと走れる企画などもあって、新しい楽しみ方が生まれてきています。
ライバルは、ほかのスポーツではなく、エンターテイメント全般。そのなかで、今後も街の人や技術を持つ企業と連携しながら、競技者だけでなく、観る人にも魅力を感じてもらえるトライアスロンにしていきたいですね。

この記事の内容は2025年9月30日掲載時のものです。
Credits
- 取材・執筆
- 榎並紀行
- 写真
- 佐藤翔
- 編集
- 川谷恭平(CINRA,Inc.)
- 提供画像
- 公益社団法人トライアスロンジャパン


