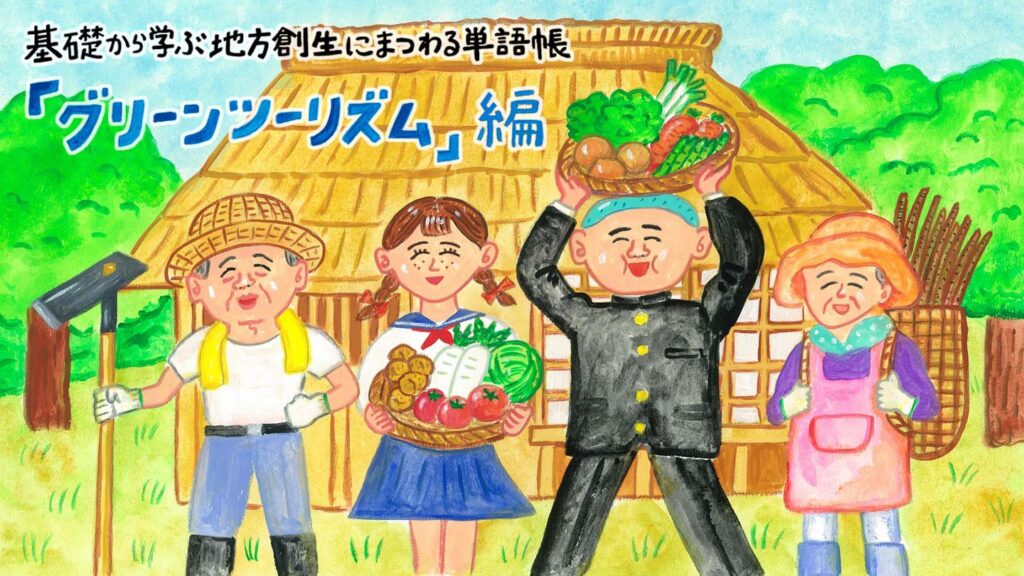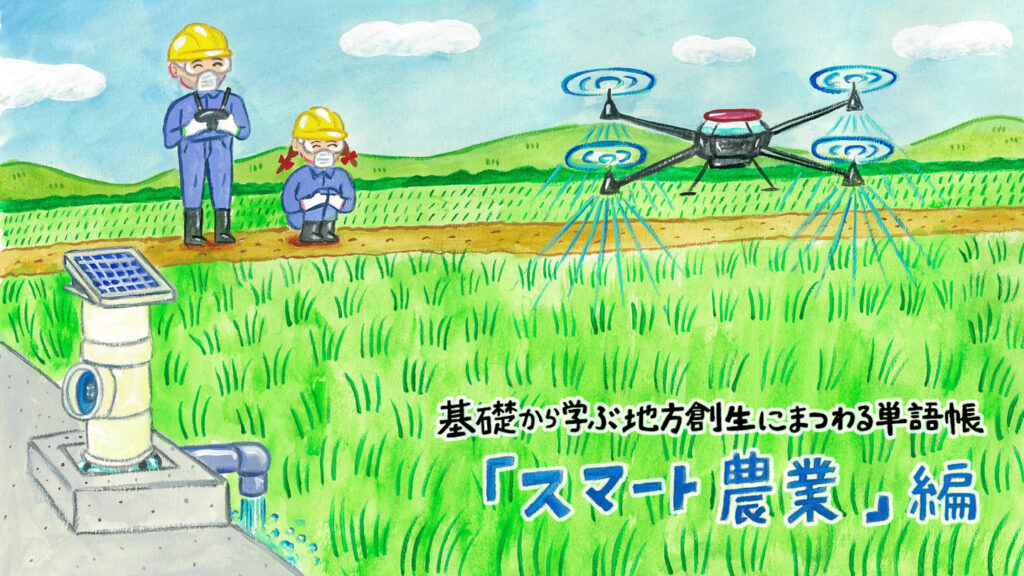ニュースやテレビ番組などさまざまな場面で、誰しも一度は耳にしたことがある「地方創生」というワード。地域を元気にするような取り組みだとはぼんやり理解しつつ、「地方創生って具体的にどんなことをするの?」と聞かれると、説明に困ってしまう人は多いと思います。
「大好きな地元に貢献したい」という想いが強いめぐり&カンタは、地方創生について猛勉強中。そんな二人が地域の未来を良くするために、ヒントとなるキーワードを集めて単語帳を作成する連載「基礎から学ぶ、地方創生にまつわる単語帳」。
今回二人が学ぶ単語は「地方創生」です。
地方創生の取り組みや成功例について、地方創生や地域にまつわる関連書籍も多数出版されている牧瀬先生に話を聞きました。
そもそも「地方創生」とは?
「地方創生」の定義
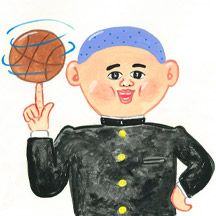
カンタ
先生、僕たち地元をもっと盛り上げたいんですが、「地方創生」ってそもそも何なんですか?
牧瀬
「地方創生」という言葉はかなり多義的で、国や自治体ごとで少しずつ異なる定義を掲げています。たとえば内閣官房は、地方創生に関する取り組みについて、「各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生」するために取り組んでいると記しています(*1)。

めぐり
「自律的で持続的な社会」をつくる、ですか……?
牧瀬
はい。日本の地方では少子高齢化や若者の都市部への流出など人口減少も進行し、経済活力が著しく低下しているエリアも多くなっています。「自律的で持続的な社会」とはそれらの課題を克服し、地域経済の活性化に向けた取り組みを行い活力ある日本社会を維持していくことです。
そもそも「地方創生」という言葉は、2014年に内閣が「地方創生担当大臣」というポジションを置いて以降、広く使われるようになりました。国として特に力を入れて取り組もうとしているのが、人口減少の課題です。少子高齢化により、日本の人口は2060年に8,674万人まで下がると推計されています(*2)。そのため国が掲げる地方創生の長期ビジョンにも「希望出生率1.8の達成」「2060年に1億人前後の人口を確保」といった人口減少の課題に対する具体的な目標が明記されています(*3)。
地方創生が注目されている背景

めぐり
それまでにも「地方を活性化しよう!」といった取り組みはいろいろあったと思うんですけど、わざわざ「地方創生」という言葉が新しく注目されはじめたのには、どういう背景があったんでしょうか?
牧瀬
これは私見ですが、「地方創生」の言葉が注目された背景として、2014年に日本創成会議という民間の団体によって「消滅可能性自治体」のレポートが発表されたことは大きく影響していると思います。
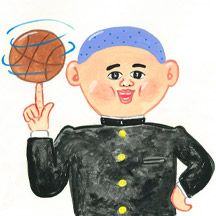
カンタ
消滅可能性自治体? 街がなくなっちゃうってことですか?
牧瀬
消滅可能性とは、人口減少が著しく、このまま減り続けると存続が危ういよ、というニュアンスですね。消滅可能性自治体の計測はいまも続いており、それも踏まえていうと「計測基準時点から30年間で、20代〜30代の女性人口が5割以上減少する自治体」と定義できます(*4)。
2014年の日本創成会議のレポートでは、全国約1800ある自治体のうち、896が消滅可能性自治体に当てはまると発表されました。なかでも北海道は78%、青森は87%、秋田は96%の自治体が消滅可能性都市に該当しているとされ(*5)、当時の社会に大きな衝撃を与えたんです。
消滅可能性自治体の計測をきっかけに人口減少への対策の機運が高まって、国を挙げた「地方創生」の動きへとつながっていったのではないか、と考えています。
地方創生はなぜ重要なの?

めぐり
先生の考えとしては、「地方創生」って、人口減少の課題を解決しようとしている、ということですか?
牧瀬
地方創生が必要になったおおもとの問題は「人口減少」なのですが、これがさまざまな地域の課題につながっていきます。
人口減少が進むと、その地域の経済はどんどん後退します。単純にお金を使う人が減ると、そのぶんお店の数も少なくなり、働ける場所も消えていく。地元に雇用機会がなければ、若い世代は仕事を求めて都市に流れていくので、さらに人口は減って……と、負のスパイラルに陥っていくんですね。


めぐり
あ、そっか。そのスパイラルを逆に考えて、お店や働く場所を増やしながら魅力的な街にしていけば、人が出ていかなくなるから、そういうアプローチも「地方創生」につながってくるんですね。
牧瀬
そのとおりです。地方創生の文脈において、自治体が取り組むべきことは「地域の魅力を最大化して、豊かな経済圏を育むこと」です。それが結果的に「人口の流出を抑えること、流入を促すこと」に寄与して、地域の「人口減少」克服につながっていくのです。
いまの地方創生が抱えている課題
牧瀬
ただ地方創生について、自治体では「スマートシティ」のようなさまざまな施策を考えていますが、現状から「地方創生」の行く先を考えるとあまり楽観はできないな、というのが本音です。
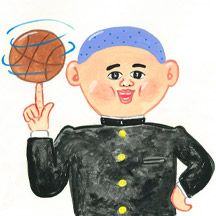
カンタ
えー! 各地が魅力的な街になったら完璧だと思ったのに! 先生が気にしている点は何ですか?
牧瀬
私が地方創生における課題として感じているのは、いまの地方創生の向かう先が「地域間での人口の奪い合い」のようになってしまっていることです。「出生率を上げて人口を増やす」といったアプローチのほうが取り組みとしては本質的ではあるのですが、出産・子育て支援に注力しても「ある程度子どもが育ってから、労働・教育環境が豊かな地域に引っ越してしまう」といったケースも多いようです。
そういった背景を踏まえると「いかに他所からの人口流入を増やすか」という自治体の施策が多くなるのは理解できます。しかし、現状ではこの競争に勝った自治体の人口は増え続け、負けた自治体は減り続け……というように、各地域の共存が難しくなってしまっているんです。
本来の「地方創生」がめざすのは生存競争や淘汰ではなく、共創や共存です。日本全体が盛り上がるように協力し、個々の地域のよさを最大化しながら共存していけるようなまちづくりの施策を、行政と企業、そして住民が協力しながら生み出していけるといいですね。
地方創生の代表的な取り組み。長野県、千葉県の成功例を紹介

めぐり
それぞれの地域の良さが日本に住むみんなに伝わって、自分に合った場所に住めるようになるといいなぁ。そのためにまだまだ課題はありますが、地方創生の取り組みはいま、さまざまな自治体や企業でされていると聞きました。
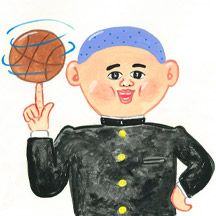
カンタ
どんな取り組みがあるのか、教えてもらえますか?
長野県|充実した移住・定住サポート
牧瀬
地方創生の取り組みとして、いまは移住促進のPRに力を入れている自治体も増えています。
定住までのサポートを手厚く行っている事例としては、長野県の取り組みが代表的です。県庁内に移住相談を担当する「信州暮らし推進センター」の設置、移住ポータルサイト「楽園信州」の運営、移住希望者の住宅探しや職探しを支援するイベント開催などの活動を手広く展開しつつ、移住者向けの補助金も充実させています。こうした施策が功を奏し、長野県への2023年度の移住者数は6年連続の増加、過去最高の3,363人を記録(*6)しています。

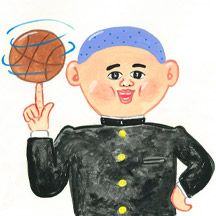
カンタ
6年連続で増えているのはすごいなあ!
千葉県|地域の特色を活かしたブランディング
牧瀬
また、地方創生では地域の特色を印象付ける「イメージ戦略」も重要です。この成功事例として挙げられるのは、2021年の調査で人口増加数全国1位となった千葉県流山市でしょう。同市は全国に先駆けて役所内にマーケティング課を設置し、「流山市ブランディングプラン」を策定(*7)しました。
このプランの特徴は、「都心から一番近い森のまち」「母になるなら、流山市」などめざすべきブランドを言語化し、そのブランドイメージの構築に向けた戦略を緻密に練りあげたところにあります。子育て支援の拡充や街の緑化の推進など具体的な施策にも取り組みつつ、地域としての特色を全面的に押し出した広報活動を内外に向けて展開したことが、千葉県流山市の人口増加に大きく寄与したといわれています。

めぐり
なるほど。「地方創生」といっても、移住支援やブランディングなど、いろんな切り口があるんですね。
牧瀬
もう少し違った切り口でいうと、外国の留学生・就労者の受け入れ促進によって人口を増やしたり、地域や地域の人と継続的に関わってくれる関係人口の増加につながる取り組みをしたりすることで、地域経済を活性化させた事例もあります。地域の地理や文化、特色を理解したうえで、効果的な施策を打つことが「地方創生」のカギとなります。
地方創生が進むとどんな未来がある?
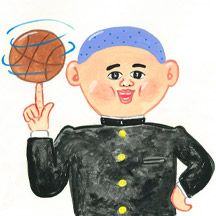
カンタ
「地方創生」で地元が盛り上がったら、近所で毎年やってるお祭りももっと賑やかになるだろうな! 地元でしか食べられない料理も残していきたいなぁ。先生は「地方創生」について、どんな理想がありますか?
牧瀬
それぞれの自治体がそこにしかない魅力をフックに独自性のある施策を打ち出して、どんどん地域経済を盛りあげていくことで、日本全体が元気になっていくのが理想ですね。
自治体は、土地の特色をしっかりと理解し、それを活かした将来のビジョンを、住民へ魅力的に示していくことが必要です。長期的な定住者に向けて「ここに住み続けたい」「ここに住んでよかった」と思ってもらえるような訴求力が求められている気がします。未来への希望は、いまを生きる活力となって、よい経済の循環を生み出す起点となるはずです。

めぐり
私たち一人ひとりの住民は、「地方創生」にどんな姿勢で関わっていけるといいでしょうか?
牧瀬
まずは、こういった記事をきっかけに「うちの自治体ではどんな取り組みをしているんだろう?」と関心を持ってくれたら嬉しいです。
自治体に興味を持つと、「こんな情報発信をしているんだ」「こんな施策が動いていたんだ」など目に入るものが少しずつ変わってくると思います。「うちの自治会って何をしているんだろう?」と気になってくるかもしれません。
そういう小さな変化を足がかりにして、「自分たちの街をよくするために、何ができるだろう?」と考え、手の届く範囲でできることから実践をしていけると素敵ですね。
地方創生を簡単にまとめると……
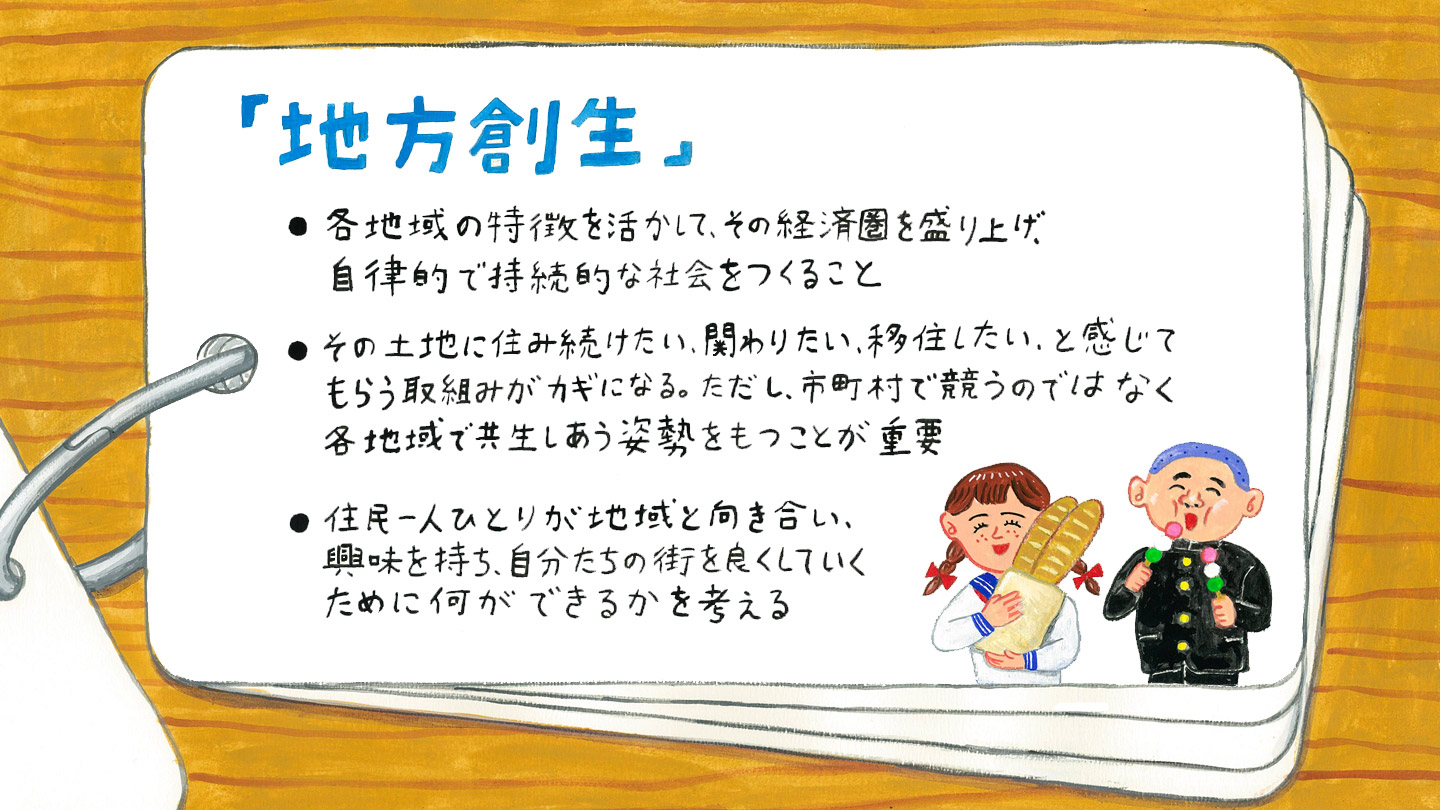
- 地方創生とは、各地域の特徴を活かしてその経済圏を盛り上げ、自律的で持続的な社会をつくること
- その土地に住み続けたい、関わりたい、移住したい、と感じてもらう取り組みがカギになる。ただし、市町村で競うのではなく各地域で共生しあう姿勢をもつことが重要
- 住民一人ひとりが地域と向き合い、興味を持ち、自分たちの街を良くしていくために何ができるかを考える
*1内閣官房「地方創生に関する取り組み」より
*2 内閣府「第1章 第1節 1 (2)将来推計人口でみる50年後の日本」より
*3 地方創生推進事務局「まち・ひと・しごと創生『長期ビジョン』が目指す将来の方向」より
*4 人口戦略会議「令和6年・地方自治体「持続可能性」分析レポート 」、日本農業新聞「「消滅可能性自治体」を問う 発表者の増田氏×批判の小田切氏、双方の見解は」より
*5 日本創生会議発表「全国市区町村別[『20~39歳女性』の将来推計人口」より
*6 NHK 信州NEWS WEB「長野県に移住 昨年度3363人 これまでで最多に」より
*7 RESERVA.lg「千葉県流山市|人口増加数が全国1位の市が取り組む『住み続ける価値』のあるまちづくりを紹介!」より
※イラストは全てイメージです。実際とは異なる場合があります。
この記事の内容は2025年2月20日掲載時のものです。
(2025年3月31日一部更新)
Credits
- 監修
- 牧瀬稔
- 執筆
- 西山武志
- イラスト
- ヘロシナキャメラ
- 編集
- 森谷美穂(CINRA, Inc.)