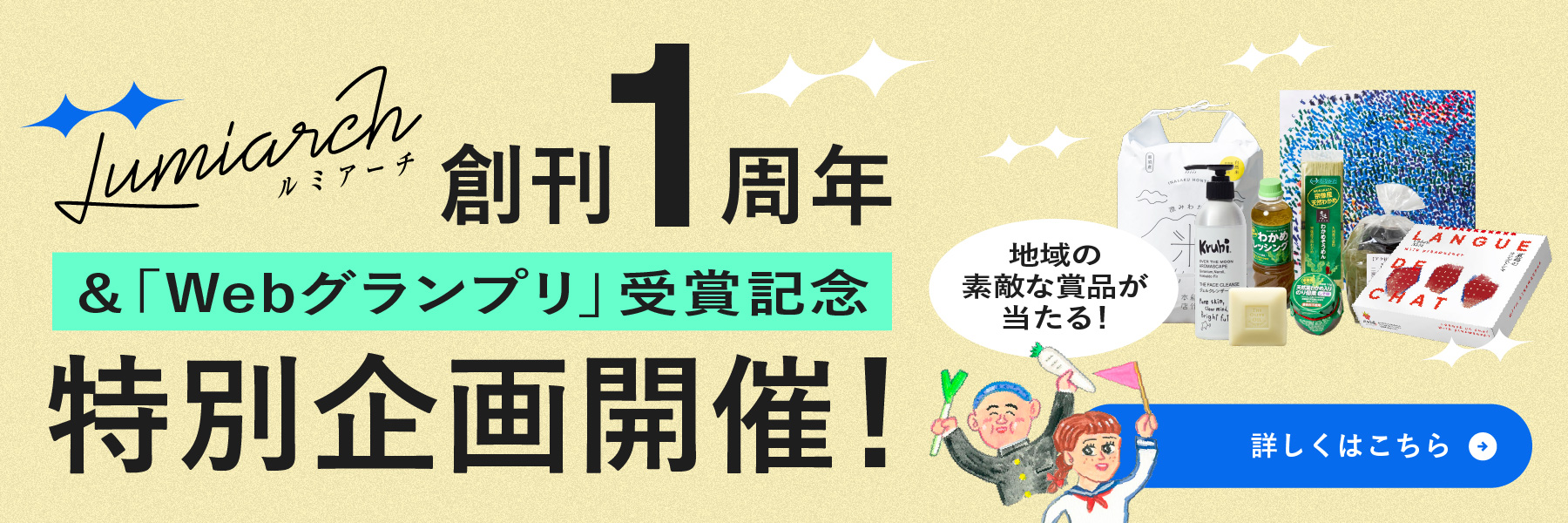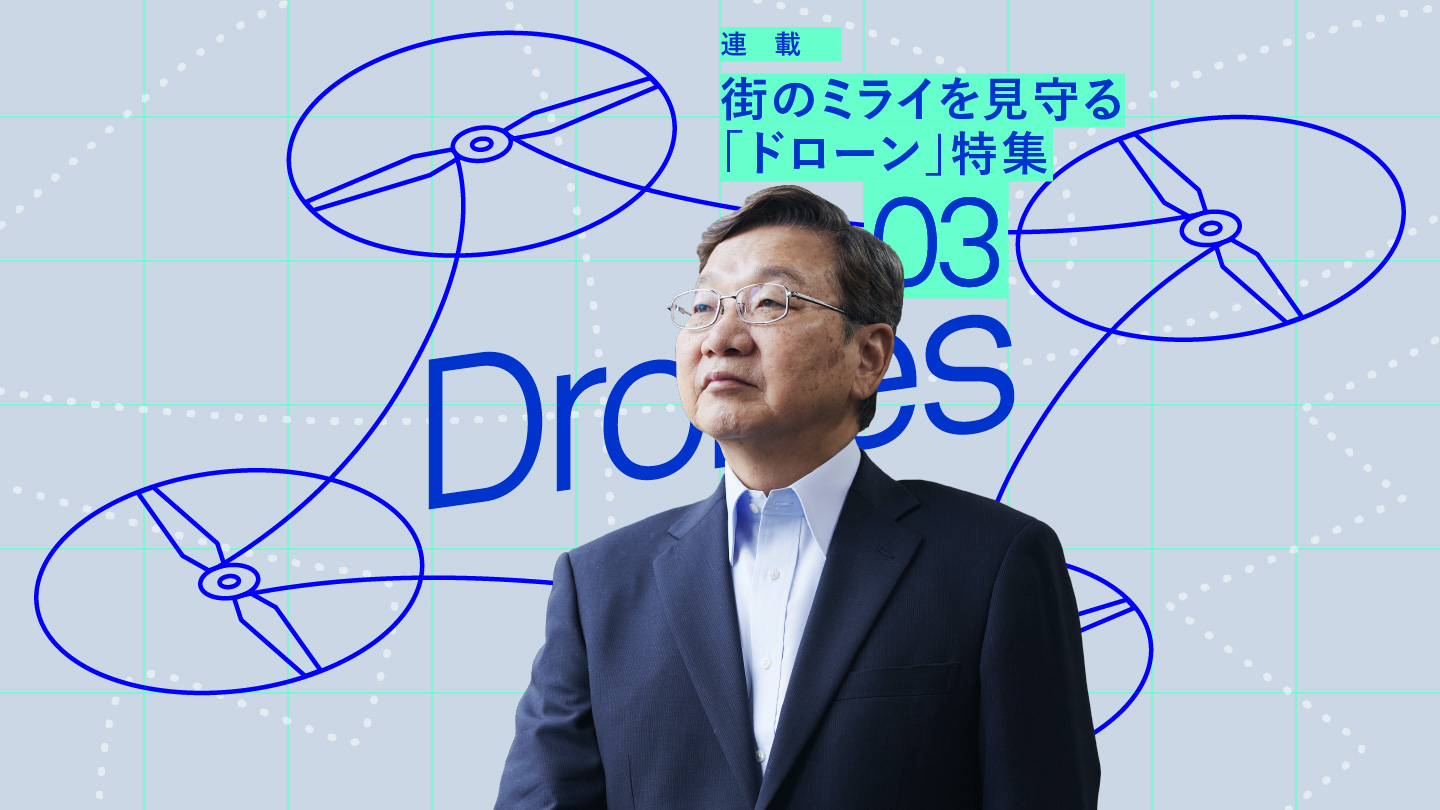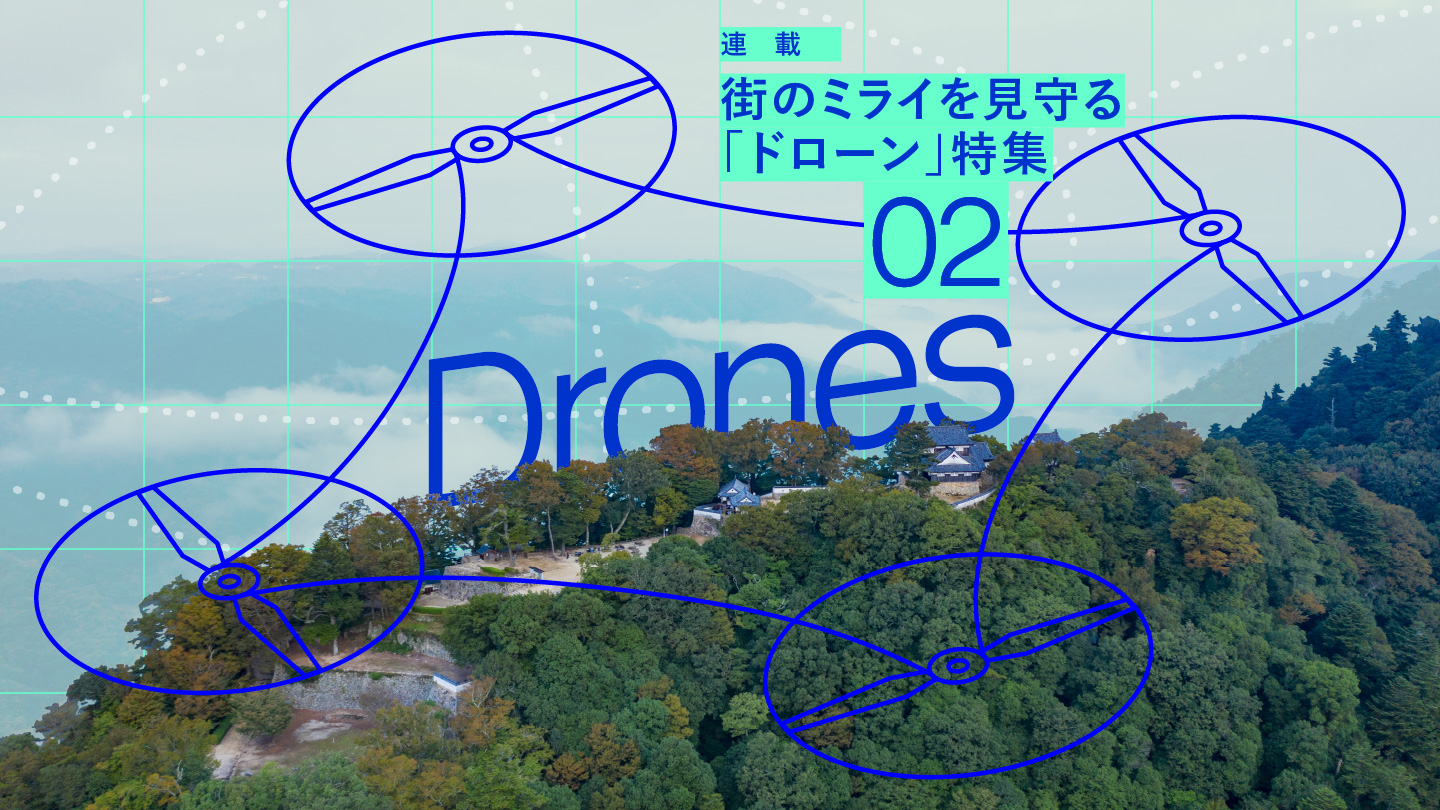物流や災害救助、農業、観光など、さまざまな分野で活躍の場を広げ、市場規模が急速に拡大しているドローン。ニュースで取り挙げられたり、実際に飛んでいる様子を見かけたりする機会も増え、ドローンが気になっている方や事業での導入を検討されている企業も多いのではないでしょうか?
とはいえ、ドローンはそもそもどんな定義で、どんな活用事例があるのかなど、基礎の知識があまりないという方もいるはず。
そこで「街のミライを見守る『ドローン』特集」の第1回では、ドローンの定義から代表的な種類、活用事例までわかりやすく解説します。
そもそもドローンとは?基礎知識をおさらい
ドローンの定義
ドローンは日本の航空法上で「無人航空機」に分類されますが、これには、翼が複数ついたマルチコプターのほか、ラジコン機や農薬散布用ヘリコプターなどが該当します。
2015年12月に導入された航空法第11章によると、ドローン含む無人航空機は「構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されています(*1)。
ただし、マルチコプターやラジコン機などであっても、重量(機体本体とバッテリーの重量の合計)が100g未満のものは「模型航空機」に分類され、無人航空機とは異なり、航空法の一部規制が適用されない扱いになります(*2)。

ドローンとラジコン機との違い
実は、現行の航空法において、ドローンとラジコン機の明確な違いは示されていません。
しかし、ラジコン機は無線で遠隔操作するため、操縦中は常に操縦者がコントロールし続ける必要があります。一方、ドローンには、自動飛行機能が搭載されていることが一般的で、比較的簡単に操縦できる点が特徴です。
代表的な4種類のドローン
ドローンにはさまざまな種類があり、用途に合わせて利用されています。本記事では代表的な4種類のドローンそれぞれの特徴や長所・短所を紹介します(*3,*4,*5)。
- シングルローター型(回転翼)
- マルチコプター型(回転翼)
- 固定翼型
- VTOL型
1. シングルローター型(回転翼)ドローン

シングルローター型(画像提供:野波健蔵さん)
シングルローター型ドローンとは、通称「無人ヘリコプター」と呼ばれる、翼が回転する機体です。主な使用用途は、農薬散布や物流(物資の輸送・投下)、測量や放送コンテンツの画像取得、放射線や大気物質のデータ計測などです。
飛行速度は時速30〜80kmで、60~90分程度巡航可能。自動離着陸やGPSによる自律飛行もできます。また、積載重量は100kg程度までとされています。
<シングルローター型ドローンの長所>
・安定していて燃費がよい
・スピードを出しやすい
<シングルローター型ドローンの短所>
・操縦技術が求められる
・離着陸に比較的大きな場所が必要
2. マルチコプター型(回転翼)ドローン

マルチコプター型イメージ
マルチコプター型ドローンとは、複数の回転翼(プロペラ)を備えた機体です。画像解析やセンサーによる屋内での自律飛行も可能なのが特徴。空撮や趣味用、インフラの点検などに利用されています。
飛行速度は時速30〜60kmで、15~45分程度巡航が可能です。積載重量は10kg程度までです。
<マルチコプター型ドローンの長所>
・比較的低価格で入手しやすい
・離着陸の場所はわずかでよい
・操作性が高い
<マルチコプター型ドローンの短所>
・速度が遅め
・重いものを運びにくい
3. 固定翼型ドローン

固定翼型イメージ
固定翼型ドローンは、翼が固定されている機体で、主に広範囲の作物の監視や長距離運用に使用されています。
速度は時速30〜150kmで、3~6時間程度巡航可能。積載重量は5kg程度までです。
<固定翼型ドローンの長所>
・高速長距離飛行が可能
・風・気流を利用して発動機を使わずに空を飛ぶ「滑空」ができる
・燃費もよい
<固定翼型ドローンの短所>
・ローター未搭載のため離陸時に滑走路が必要
・より高い操縦技術が求められる
4. VTOL型ドローン

VTOL型イメージ
VTOL型ドローンは、固定翼・回転翼を併せ持つ機体で、時速70〜200kmと高速飛行できるのが特徴です。3~6時間程度の巡航が可能で、積載重量は10kg程度まで。
現在、主に民生用(一般消費者向け)と軍事用の使用用途がありますが、今後は物流や広域の測量・点検・監視などでも活用が広がる予定です。
<VTOL型ドローンの長所>
・高速長距離飛行が可能
・滑走路不要で狭い場所でも垂直に離着陸可能
・滑空も可能
・少ないエネルギーで長時間の飛行ができる
・最高速度が速い
・安定性が高い
<VTOL型ドローンの短所>
・固定翼に比べてコストが高い
・制御技術は難しい
ドローンの活用事例|趣味・産業・災害など
ご紹介した代表的な4種類のドローンをはじめ、さまざまなドローンが下記のような用途で幅広く活用されています。それぞれの活用事例と抱える課題について詳しく解説します。
ドローンの活用事例1|趣味用
カメラを搭載したドローンは、写真だけでなく動画の撮影にも活用されています。たとえば映像制作や空撮など、さまざまなシーンで臨場感あふれる映像が撮影可能です。また、ラジコンのように飛ばして遊ぶためのドローンも多く存在します。趣味用のドローンは価格帯もさまざまで、手軽に購入できる安価なモデルも多いため、幅広い層に親しまれています。
趣味用のドローンにおける主な課題として、操縦者が飛行規制やルールを確認し遵守できるか、という点があります。飛行規制やルールには国が定めるものに加え、自治体ごとに異なるルールも存在し、複雑さを増しています。そのため、禁止区域での飛行や無許可の撮影が問題となるケースが増えているのです。

ダイナミックなアングルも、ドローンだからできる撮影
ドローンの活用事例2|スポーツ・競技用
ドローンの活用事例2つ目は、スポーツ・競技用です。現在、世界中で「ドローンレース」が行われています。ドローンを遠隔操作して決められたコースを飛行し、速さや技術を競い合うエアレースのことです。日本でも「JAPAN DRONE LEAGUE」をはじめ、大規模なドローンレースが行われており、近年、さまざまな場所にドローンの練習場もつくられるようになりました。
スポーツ・競技用ドローンには、高速かつ高精度な操作が求められるため、激しい競技に耐えられる強度や安定した通信機能、長時間稼働できるバッテリーの実装が不可欠です。さらに、ドローンレースはまだ比較的新しいスポーツであり、競技としての認知度の向上もめざされています。
ドローンの活用事例3|産業用
ドローンはさまざまな産業での活用が進められており、農業、観光、インフラ整備など多岐にわたります。
なかでも、農業分野のドローンは急速にニーズが拡大しています。たとえば、農薬散布ドローンは、薬剤タンクを搭載して効率的に散布するだけでなく、種まきや人工授粉にも利用されています。さらに今後、農作物の運搬や土壌のデータ取得などをドローンが担うことによって、大幅なコスト削減や人手不足の解消が期待されています。

農業でドローンを活用しているイメージ
また、建物やインフラの整備・点検・調査・メンテナンスにもドローンが活用されています。たとえば、カメラで破損部分を確認したり、センサーで異常な熱を検出したりなど、狭い場所や高所などの危険な場所でも安全かつ効率的な点検が可能になります。
ドローンの活用事例4|災害用
ドローンは、地震や洪水などの災害発生時に、現場の状況を把握するためにも活用されています。
たとえば、地震発生時の住家被害認定調査では、ドローンで撮影した高解像度画像をもとに、自治体や事業者が遠隔で被害を判定します。これにより、現場に行かずとも迅速な状況判断ができたり、人が歩けないような危険場所の状況把握も可能です。加えて、逃げ遅れた被災者の発見にも大いに役立ちます。
ドローンは、災害時の情報収集や被害判定、救助活動において、リスク回避や人的リソースの不足を補う役割を果たしているのです。
ドローンの活用における課題
ドローンの社会実装は少しずつ進みつつありますが、ドローンが日常で当たり前のように活用される世界の実現には、依然として多くの課題が残されています。
たとえば、ドローンは墜落や落下といったリスクが懸念されており、そのため風や急な天候の変化に対応できる耐候性の強化や、バッテリー・モーターの性能向上による飛行の安定性の確保などが必要となります。そのため、技術力の強化が求められています。
上に加えて、特に産業用ドローンにおいては導入や運用にかかるコストが高いこと、操縦可能な人材が不足していることも大きな課題です。また、飛行規制やルールの整備も必要です。こうした技術的な課題や運用上の問題を解決することで、ドローンの普及と効率的な活用が進むと考えられています。
ドローンを導入・活用するうえでの注意点は?
2022年6月より無人航空機の安全確保や事故の原因究明のため、機体の登録が義務化されました。「屋外を飛行させる100g以上のすべてのドローン・ラジコン機」が対象で、複数台所有している場合も一台ずつの登録が必要です。ここでは、ドローンを導入・活用するうえで代表的な注意点を解説します。
無人航空機の各種規制を確認し遵守する
ドローン飛行には、日中(日出から日没まで)に飛行させることや、第三者または第三者の物件との間に距離(30m)を保って飛行させること、飲酒時の飛行はしないことなど、守らなければならない飛行ルールが国や各自治体によってさまざま定められています(*6)。
規制に違反すると罰則を受ける恐れや重大な事故につながる危険性もあるため、必ず確認し、遵守するようにしましょう。無人航空機の飛行ルールについては、「国土交通省のWebサイト」に詳しく記されています。
飛行許可の取得や周囲への配慮を行う
ドローンの操縦に資格は必須ではありません。しかし、「空港等の周辺」「人口集中地区の上空」「150m以上の上空」など、特定の条件下で飛行する「特定飛行」に該当する場合には国土交通大臣の許可が必要です。
その際、ドローンの操縦に関する知識や技術を証明する「無人航空機操縦者技能証明書」の取得が求められるので、状況に応じて「一等無人航空機操縦士」または「二等無人航空機操縦士」といった資格が必要となります(*7)。
飛行許可・承認申請は、飛行開始予定日の少なくとも10日以上前(土日祝日等を除く)までに行わなければならないため、余裕をもって申請しましょう(*8)。
操縦者は飛行を開始してから終了するまで、そのすべての責任を問われます。第三者や関係者が危険を感じるような操縦をしない、第三者が容易に近づくことのないような飛行経路を選択するなど、常に第三者や関係者の安全を意識することが重要です(*9)。
万が一の事故に備えておく
「第三者にケガをさせてしまった」「物件を壊してしまった」「飛行中に突然発火した」など、ドローンの飛行中に万が一事故が起きた場合は、ただちに飛行を中止しましょう。併せて、負傷者の救護や消防・警察への連絡、国土交通省への報告が必要です。飛行前に「事故等の報告及び負傷者救護義務」を必ず確認しておきましょう。
また、無人航空機の保険には、自動車のような強制加入の保険はなく、すべて任意加入となっています。しかし、万が一事故が起こった場合に備え、保険に入っておくと安心です。無人航空機の保険には、さまざまな種類や組み合わせがあるため、自分の機体の使用状況に合った保険を選んで加入するといいでしょう(*9)。

ドローンを操縦しているイメージ
ドローンの活用と今後の期待
ドローンは、さまざまな種類があり、空撮や農業、災害救助など幅広い用途で利用されています。近年では国によるドローンの制度整備も進み、今後さらに多くの場面での活用が期待されています。
ドローンを導入・活用する際は、規則の遵守や安全確保を行うことが不可欠です。飛行させる場合は、記事で紹介したようなポイントを参考にしながら慎重に行いましょう。
地方創生をはじめ、娯楽や産業、災害救助など、私たちの生活のさまざまな場面でドローンが果たす役割がますます広がっていくでしょう。今後のドローンの活躍に、ぜひ注目してみてください。
*1:国土交通省「飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体」
*2:国土交通省航空局「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」
*3:財務省関東財務局経済調査課「ドローン機体ビジネスの動向について」
*4:農林水産省生産局技術普及課「農業用ドローンの普及拡大に向けて」
*5:総務省事務局「ドローンの現状について」
*6:国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」
*7:国土交通省「無人航空機操縦者技能証明」
*8:国土交通省「ドローンの飛行ルール」
*9:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則」
この記事の内容は2024年12月19日掲載時のものです。
(2025年4月21日 一部更新)
Credits
- 監修
- 野波健蔵
- 執筆
- 渋谷唯子
- 編集
- exwrite、CINRA, Inc.