Theme知る
人口約7,500人の街に誕生した「ネオ集落」。デジタル×地域×家づくりの可能性
- 公開日

秋田県中央部に位置し、里山が広がる五城目町(ごじょうめまち)。人口約7,500人の土地に、新しいかたちの集落「森山ビレッジ」が誕生しました。2023年12月に竣工したこのビレッジは、半径30km圏内の森林資源を使って建てられています。さらに特筆すべきは、デジタルデータをもとにしたものづくりの手法で、全国から集まった一般の希望者が家づくりに参加して完成したことです。
この取り組みをスタートしたのは、森山ビレッジの住人でもある、丑田俊輔さん。里山の暮らしにデジタル技術を活用させながら、新しいコミュニティのかたちを模索しています。
なぜ森山ビレッジをつくることにしたのか、持続可能な暮らしへの取り組みと、その先にどんな未来を描いているのかなど、お話をうかがいました。
自分たちで遊びや暮らしをつくる。森山ビレッジの着想に至るまで
―まず、森山ビレッジはどんなところなのでしょうか?
丑田
地域資源やデジタル技術を用いて住まいを建て、その周辺エリアとつながりながら新たな住まい方を実験する「ネオ(新しい)集落」をつくろうと考えて立ち上げた場所です。

森山ビレッジ外観。一つ屋根の下に5棟の家を建設。伝統的な入母屋屋根を採用し屋根の雪を落としやすくするなど、雪国に合わせた建築が取り入れられている。庭は共有スペース。取材時はテントサウナが設営されていた。
丑田
森山ビレッジは、豊かな森と川に囲まれた秋田県五城目町にある「森山」のふもとにあります。森山は標高325mほどで、地元の方もよく登る、街のシンボルのような山。五城目町の中心地へも車で5分ほどです。
街の中心地では、520年以上続く朝市が定期的に開かれ、地元の人が育てた野菜や手づくりの漬物などが購入できます。ほかにもカフェやパン屋さん、300年以上続く酒蔵の新しい拠点など、この10年で25軒ほどの新しい施設ができました。

丑田俊輔さん
丑田
そんな五城目町にある森山ビレッジは、それぞれが独立しながらも、長い屋根でつながっています。家の間取りはあえて必要最小限にし、商店街に、みんなでつくったあそび場をはじめ、近所のさまざまな拠点も住まいの延長線上のように活用することで、近所の方と自然に顔を合わせたり、頼り合ったりできるようにしました。
僕もこのビレッジの住人なのですが、集落で過ごす日常を楽しみつつ、ときには商店街のシェアオフィスで仕事をしたり、街の温泉へ頻繁にいったりするなかで、五城目で住む人たちとのかかわりがどんどん増えていっています。
この街では、歴史ある朝市を活性化するプロジェクトや、ビレッジの建つ「森山」を盛り上げる活動など、自分たちで「遊び」や「暮らし」をつくっていこうという機運が高まっていて、こうした動きとのつながりも面白い部分です。
「田舎」と「都会」どちらかに寄らず生活をしたい
―ところで、どうして森山ビレッジをつくろうと思ったのでしょうか?
丑田
僕はこの10年、秋田に住みながら毎週東京を行き来する生活をしているのですが、自分の暮らしがもっと楽しく、ラクになったらいいなという気持ちからはじまっています(笑)。
あとは、そういうライフスタイルをする人のハードルをぐんと下げられたらいいなと思って。これまでは、家を買ったら住宅ローンを組んで、住民票がある街に長くいることが一般的だったと思います。でも、最近は二拠点生活が徐々に普及しはじめました。
教育の現場では、東京や他県の小学校に通う子どもが1週間単位で五城目小学校に通う「教育留学」も進んでいます。

(画像提供:五城目町役場)

秋田県外の小学生・中学生を対象に、学校での授業のほか、地域での体験活動を行うプログラム(画像提供:五城目町役場)
丑田
ただ、いざ地方で暮らそうとすると、空き家はあってもなかなか借りられなかったり、断熱がしっかりしていない物件だと寒さが厳しかったりといった住まいの課題を感じていたんです。だからといって、都市の方が地方に家を買って移住する、という判断はとても勇気がいります。
そこで、毎日住む人だけでなく、2拠点居住する人や教育留学する人、たまに遊びにくる人も含め、住民票にとらわれず多様な住まい方が育まれていくような環境ができたらと考え、森山ビレッジを構想しました。
―森山ビレッジは何人くらいの仲間とともに始動したんでしょうか?
丑田
僕を含めて5世帯です。東京と秋田を行き来するなかで、次第に遊び仲間になり、意気投合しました。何かはじめようと言い出す人たちばかりなので、通称「言い出しっぺ村民」と呼んでいます。
―森山ビレッジの立ち上げには「言い出しっぺ村民」以外にも、いろんな方がかかわったのでしょうか?
丑田
本当にたくさんの人が協力してくれました。森山ビレッジをつくるにあたって、2023年にクラウドファンディングを実施したんです。そこで県内外問わず支援をしてくれた方や地元の人たち、子どもたちが友だちを連れてきたりもして。いままで知らなかった方々とのご縁もできましたね。つながりが新たなつながりを呼び、かかわる人が増えていきました。

(画像提供:丑田俊輔さん)

森山ビレッジ建築中の様子(画像提供:丑田俊輔さん)
デジタル技術を用いて「みんなでつくる」体験を
―森山ビレッジは、「地域資源×デジタル×コミュニティ」というコンセプトを掲げています。これはどのように生まれたのですか?
丑田
もともと僕はIT業界にいてデジタル自体に興味がありました。一方で、秋田で暮らしているため地域のつながりや自然での遊び方などアナログなものの楽しみ方も知っています。それらがかけ合わされれば新しい価値が生まれると、ずっと思っていたんです。森山ビレッジを構想する前には、茅葺古民家を村に見立て、遠く離れた人でも会員になればその「村」を「第二の田舎」として里帰りしてもらえる「村民」制度をつくり、エンジニアの「村民」と一緒に、いろいろな地域の人とつながることができるコミュニティアプリもつくりました。

コミュニティプラットフォーム「Share Village」。コミュニティメンバーの募集・管理や、決済機能、コミュニティ独自のコイン発行などを行うことができる。上記の本文にある茅葺き古民家の「デジタル村民」の実践をもとに開発された
丑田
このような、デジタルとコミュニティのそれぞれが持つ価値をかけ合わせた事業をしていたこともあって、森山ビレッジでも自然とこうしたコンセプトが生まれました。
―さらにそこへ、五城目町の地域資源もかけ合わせたんですね。
丑田
はい。田舎町には、商店街の空き店舗をはじめ、使われなくなった古民家、耕作放棄地、手入れの行き届いていない山林など、市場経済からこぼれ落ちてしまっている資源があります。ただ、いまはうまく使われていなくても、そこにデジタル技術を用いて、新しいビジネスモデルを創造すれば、きっと価値が生まれるはず。
そこで、デジタル技術と街の遊休資産をかけあわせ、地域の里山の木も活かしながら、みんなで住まいや地域との交流の場を手づくりする体験ができたら、コミュニティとしても面白いのではないかと思いました。

デジタルファブリケーション機器「ShopBot」で里山の木材をカット(画像提供:丑田俊輔さん)

カットした木材を加工(画像提供:丑田俊輔さん)
丑田
現代はデジタル技術を活用してみんなでつくる、「ものづくりの民主化」が進んでいます。森山ビレッジは、クラウドファンディングで支援してくださった方々をはじめ、地元のみなさんや有志の職人さんたちの協力によってつくられました。
建設には「デジタルファブリケーション」という新しい技術を使い、木材を3Dで加工できる「ShopBot(ショップボット)」という機械で部材をカット。それをみんなで力を合わせて組み立てて完成させました。
この技法を使えば、子どもから大人まで簡単に木材をつくりたい形に加工できるんです。

森山ビレッジの1棟の中の様子。地元の大工さんが携わり、階段や手すりなどもすべて自作した
―この椅子もみなさんでつくったんですか?

丑田
そうです。木材パーツをブラウザ上でつくって、それを出力して、組み立てるんです。結構簡単につくれますよ。
椅子がほしいと思ったら、量販店などで既製品を買うのが一般的ですが、デジタル技術を駆使して目の前にある木でつくれてしまう。これがすごく楽しいんです。
遊び仲間が増えると、頼れる人も増えてくる。柔軟にかかわり持続可能なコミュニティへ
―「森山ビレッジ」がオープンしてから1年、入居者はどんなふうに利用しているのでしょうか?
丑田
僕のように100%居住している棟もあれば、二拠点目の住まいとして月の30%くらいは滞在し、それ以外の期間は宿として活用したりしている棟もあります。
お隣には東京で医師をしていた友人が住んでいます。その方はもともと、先ほどお話しした森山ビレッジの前身ともいえる茅葺古民家の村で「村民」としてかかわってくれていました。毎月のように五城目町に「里帰り」したり、まちの朝市で健康相談コーナーを出店する機会もあり、そうするうちに移住することになって、いまはご家族で住まわれています。
宿として一棟貸しをしている棟では、国内外から来た旅人が滞在したり、企業のリトリート合宿(心身をリフレッシュするための合宿)で利用したりすることも増えてきています。ほかにも、街の小中学校への教育留学で中期滞在するご家族に活用いただくケースもありますね。

―地域外の方が五城目町に訪れやすくなる仕組みがつくられているんですね。ちなみに、地域の人たちもこの場所にかかわっているのでしょうか?
丑田
森山ビレッジの清掃は地域のみなさん(家事のベテランの方など)にお願いしているんです。仕事が丁寧だし、楽しんでやってくれています。一緒にできることがあるのはうれしいですね。
新しいことをはじめるときって、田舎も都会も関係なくその場所にいる人たちとの関係性が大事だと思うんです。町内会に入ったり、道で会えば挨拶をしたり。当たり前かもしれませんが、年齢や立場を問わずリスペクトを持って接することは大前提です。
一方で、新たなプロジェクトを立ち上げる際に、必ずしも町民全員に説明したり合意形成したりする必要まではないと考えていました。日常の先で結果的に輪が広がっていったり、かかわりが増えたりするぐらいが良いかなと。最初のハードルが高すぎると、軽やかさとか遊びがないものになってしまうので。
―仲良くなった人が増えると、協力してくれる方も増えていくイメージでしょうか。
丑田
はい。全部自分たちだけでやろうとすると限界があるので、仲良くなった人にはたくさん頼っています。それによってさらに関係性が深まっていくこともありますし。
ただ、いきなり「一緒に仕事をしましょう」と仕事仲間を集めるのではなく、まずは「遊び友だちを増やす」という意識が大切かもしれません。
私自身、好きでやっている釣りの師匠が地元の大工さんで、このビレッジをつくるときに協力してくれて。そういうふうに遊びのなかからつながりや新しい事業が生まれることもありますから。「遊び」はとても重要だなと思います。
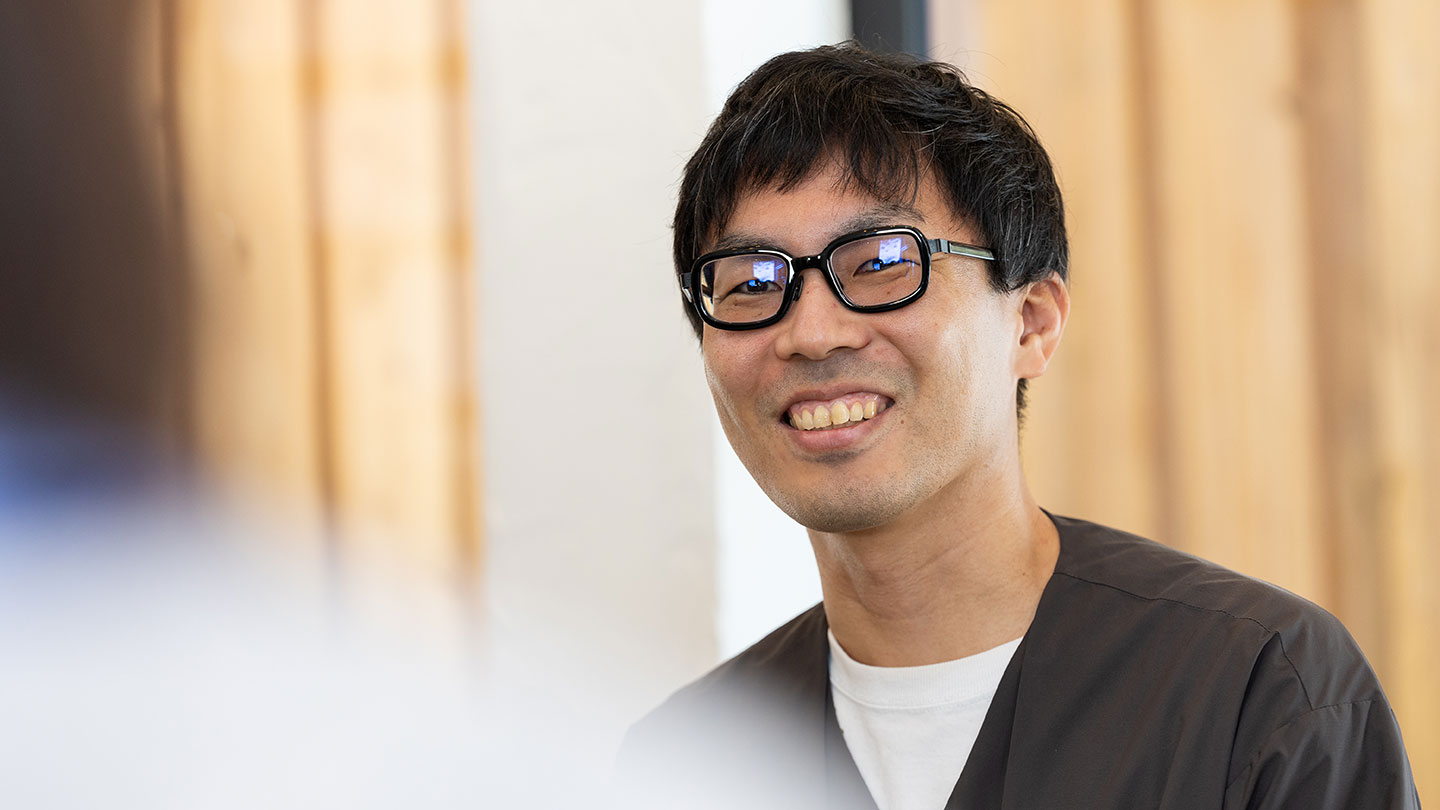
―コミュニティのあり方についてはどんなことを大事にしていますか?
丑田
心地よいコミュニティがどう生まれるかが、大事な視点だと思っています。僕が先頭に立ってコーディネートしたりプロジェクトを推進したりするフェーズはもちろんありますが、ただ生態系の一部になって暮らしているだけのときもあって、ほかの誰かが先頭に立ってはじめることもある。
たとえばコロナ禍では街の温泉が閉じてしまい、地域の方の憩いの場がなくなってしまいました。ですが、常連たちで出資しあって再開させられたらと話しているなかで、地域の高校3年生の女の子が中心になってプロジェクトが立ち上がり、無事に温泉を残すことができたんです。僕たちは高校生社長のもとで何でも動く作業員(笑)。
リーダーシップを発揮する人、フォロワーシップで支える人、お金や知恵で応援する人など、シーンによってかかわり方が入れ替わっていく。そんなふうに、コミュニティの中心に特定の誰かがずっと居続けなくてもいい状態になっていたほうが、持続可能なんじゃないかなと思います。
「デジタル×地域の資産」で街の暮らしをみんなでつくる
―今後、デジタル技術をどのように使おうと考えていますか?
丑田
デジタルファブリケーションを活用して、サウナ小屋やストリートファニチャー(公共の場に設置されるベンチなどの設備)をつくってみたいです。それから、子どもたちが「森の小さな図書館がほしい」と言っているので、街の仲間たちとつくりはじめないかな〜と眺めています(笑)。
街の中心部にある空き店舗を再利用して「ただの遊び場 ゴジョーメ」という場所をつくったのですが、その2階は「ハイラボ」という、デジタル技術を使って子どもたちが遊べる場になっています。そこでは小さな3Dプリンターやレーザーカッターでものづくりができます。


商店街にある「ただの遊び場 ゴジョーメ」。街の遊休不動産を、地域の人とリノベーションして「あそび場」にした。入口には子どもたちがつくった作品が買えるガチャが置いてある(画像提供:丑田俊輔さん)
丑田
デジタル技術は子どもたちにとって当たり前にあるものの一つで、「自分たちで何かを生み出すって面白いな」って直感的にわかっているんじゃないかなと思っていて。子どもたちにとって「遊び」と「学び」と「仕事」の境目がなくなってきている感じがします。
「この街にはないから仕方ない」と諦めるのではなく、「じゃあ、いまあるものを工夫しながら自分たちでつくってみようか」という雰囲気や環境があることは、地域の人にとっても選択肢が広がり、いい影響があるのではないかと思いました。
デジタルを活用したものづくりを身近に感じ、自分の暮らしをみんなでつくるとか、新しい仕事を生み出すとか、遊び心を大切にしながらチャレンジが生まれていってほしいです。
―コミュニティの中心が子どもになったら、また違った取り組みが生まれそうですね。
丑田
自分たちの暮らしをみんなでつくることの楽しさを、自分の身体感覚と紐づけて実感してほしいです。
ほかにも、この街で起こっていることを、デジタルを介してもっと伝えられないかと考えています。地域の企業たちの出資で生まれた宿泊施設「市とコージ」、新たなコワーキングスペースや先ほどもお伝えした「ハイラボ」など五城目ではたくさんのプロジェクトが同時多発的に立ち上がっているんですよ。
たとえば、森山ビレッジに宿泊した方向けに、アプリなどを用いた音声ガイドをつくり、森山ビレッジができるまでの話や、街のおすすめスポット紹介などを聞きながら中心地に向かうと、街をもっと楽しめるんじゃないかと思っています。海外の方のために多言語対応もしたい。デジタル技術によって滞在している時間が充実したものになるといいですよね。
「顔見知り」が地域に増えるといい。森山ビレッジをとおして描く五城目町の未来
―丑田さんが考える「地域とのつながり」とは、どんなものですか?
丑田
家づくりなど一緒に作業するきっかけがあると、コミュニケーションの得意不得意にかかわらず人と出会ってつながることができる。そういった場があることって大事だなと思っていて。
僕自身コミュニケーションがすごく上手なわけではないので、無理につながりすぎなくても、顔見知りになって何かあったときに助け合えるぐらいのほどよい距離感が地域に増えるといいなと考えています。

―森山ビレッジの取り組みを通じて、五城目町をどのような地域にしていきたいですか?
丑田
はじめて訪れる人、何度も訪れる人、ちょっと住んでみようかなという人など、多様な人が行き来する場所になって、面白いことがどんどん生まれていくといいなと思います。
それから、首都圏をはじめ企業で働く人がかかわる地域の選択肢の一つに、五城目があったらいいなとも考えています。リモートワークができるように福利厚生施設としてビレッジを活用する、2週間だけ五城目の小学校に子どもを通わせながら働くなどの選択肢もあります。企業の人と地域に関係性をつくり、新しい事業が生まれやすい環境もつくっていきたいです。
この記事の内容は2025年4月25日の掲載時のものです。
Credits
- 取材・執筆
- 佐藤文香
- 写真
- 近藤孝行
- 編集
- 岩田悠里(プレスラボ)、森谷美穂(CINRA, Inc.)


