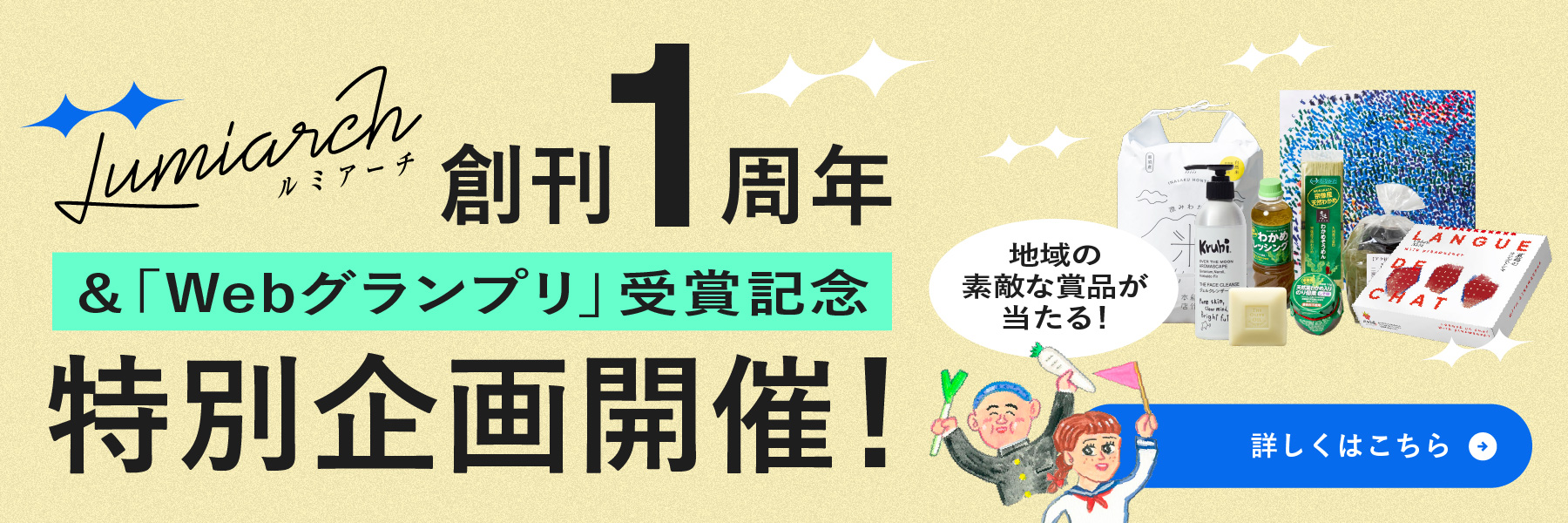Theme知る
汲めども尽きぬ「温泉愛」。地域の温泉の魅力をもっと多くの人に届けたい
- 公開日

古くから世界有数の温泉文化を育んできた日本。いま国内の温泉地には、観光地として名を馳せるところもあれば、源泉の枯渇や施設の老朽化などから存続の危機に直面しているところもあるのが実情です。
こうした状況のなかで、温泉という文化と資源を次世代に残すために奮闘しているのが、栃木県で温泉施設「中三依(なかみより)温泉 男鹿(おじか)の湯」を経営する水品沙紀さん。幼少期から温泉に親しみ、学生時代には温泉愛が高じて1,000か所以上の温泉を巡り、泉質を調査。現在では「男鹿の湯」のほかにも、温泉付き物件を紹介する不動産業も営む、温泉のエキスパートです。
休業中だった「男鹿の湯」を再建するために25歳で千葉県から栃木県に移り住んだ水品さんは、どのような思いを抱いて再建に取組んだのでしょうか。また、温泉という資源を未来に受け継いでいくためには、今後どんなことが必要になるのでしょうか。水品さんにお話をうかがいました。
1,000か所以上の温泉を巡った温泉愛を原動力に、休館していた栃木県「中三依温泉 男鹿の湯」に再び火を灯す
―水品さんは、幼少時代から温泉に魅力を感じていたそうですが、いつ頃から積極的に温泉にかかわるようになったのでしょうか?
水品:子どもの頃、家族でよく温浴施設に通っていたことから自然と温泉が好きになりました。大学生になって近隣の温浴施設でアルバイトをはじめたのですが、当時はまだ温泉の質のことなどはあまりわかっていませんでした。働いているうちに温泉のことをもっと深く知りたくなって、卒業論文で「温泉」をテーマにしようと考え、国内外の温泉を巡りました。国内を中心に1,000か所以上、湯船ごとに泉質を測定する調査を行いました。九州に行ったときには、あまりに温泉が多くて一気に回ることは難しいと途中で気づき、何度かに分けて調査したこともありました。
―卒業後は、温泉にかかわるお仕事に就かれたそうですね。
水品:そうですね。いつかは自分で温泉施設を運営したいという夢があったので、温浴施設の運営を手がける会社に就職しました。社長が温浴施設の経営コンサルタントだったこともあり、学ぶことも多く、泉質だけではなく経営という観点でも温泉のことを考えられるようになりました。
たとえば、源泉の温度が低い温泉は沸かす必要があります。そうすると、燃料代がかさんで赤字に苦しむこともあります。また、せっかく質のよいお湯があるのに、後継者不足や施設老朽化などの理由で存続が危ぶまれるところもありました。そのような施設を目にして、温泉経営というものが一筋縄ではいかないものだと実感しましたし、経営を立て直すために何かお手伝いできることはないのだろうかという思いが芽生えました。
―その後、栃木県日光市の「中三依温泉 男鹿の湯」(以下、男鹿の湯)の再建に携わることになります。

中三依温泉 男鹿の湯(画像提供:水品沙紀さん)
水品:泉質の面などを含めて自分が守りたいと思う条件に合致する温泉を探しはじめたのですが、なかなか見つかりませんでした。そんななか、ちょうど中三依の自治会が「男鹿の湯」の経営者を募集していたんです。
中三依を訪れてみたところ、自然豊かな土地で、温泉のそばを流れている男鹿川の水がとても澄んでいたことにも心を惹かれました。観光地として特に栄えている地域ではないのですが地域全体にゆったりした時間が流れていて、地域の方々も温かく迎えてくださって、この場所で暮らしてみたいという気持ちになりました。

「男鹿の湯」のそばを流れる男鹿川(画像提供:水品沙紀さん)
「男鹿の湯」は源泉の温度が低めなので加温する必要があるのは心苦しかったのですが、初めて源泉を出してみたときには、温泉の香りに心が弾みました。立地も、当時の私からすると憧れの有名温泉地に囲まれた好立地でした。当時私は25歳だったのですが、チャレンジするなら早い方がいいだろうと思って申し込んだところ、採用していただきました。
―地域の人たちとのコミュニケーションは、すぐにうまくいきましたか?
水品:リニューアルオープンをめざした時期の半年前に現地へ引っ越したのですが、自治会長さんが地域の方々への挨拶回りを一緒にしてくださったので、心強かったですね。
リニューアルについては、地域のみなさんも気になっていたみたいですね。私が準備を進めている間も、かなり奥地なので用事はないはずなのに、いろいろな方が散歩がてら訪れてくれて(笑)。ときどき、作業に戻るために会話を切り上げないといけないくらい、よく話しかけてくださいました。なかには、私より前に移住してきたという方もいらっしゃって。そういう先輩たちがいたからこそ、私はスムーズになじめたのかもしれません。
リニューアルの準備段階ではいろいろと難しい状況に直面しました。土地や源泉にまつわる権利の手続きや、何種類もの営業許可の取得など、初めてのことばかりで。施設のオープン時から20年が過ぎていたので、ボイラーや配管などの設備もかなり老朽化していました。
そんな状況に加えて、2015年9月、中三依地区が豪雨災害に見舞われました。「男鹿の湯」の駐車場は土砂と瓦礫で埋まり、浴場と機械室には泥水が流れ込みました。水道などのライフラインの復旧もままならないなかで途方に暮れていると、地域のみなさんが声をかけ合って駐車場の瓦礫の撤去作業を進めてくださったんです。そんな温かさに触れて、あらためて「男鹿の湯をなんとしても再開させたい」という思いを強くしました。その後、資金面ではクラウドファンディングを活用するなどの工夫を重ね、2016年4月に「男鹿の湯」をリニューアルオープンすることができました。

男鹿の湯・浴場(画像提供:水品沙紀さん)
―いざリニューアルオープンしてみて、どんなお客さんがいらっしゃいましたか?
水品:首都圏から車で来る方が多かったですね。釣りや川遊び、バーベキューなどを楽しみに来る方が多い印象です。リニューアル前からの常連さんも結構来てくださっていて、「男鹿の湯」の周りで温泉入り放題のキャンプもできるようにしました。目の前をローカル列車が走る不思議なキャンプ場ですが、気に入ってリピートしてくださる方も増えてきました。
2025年でリニューアルオープンから10年目を迎えるのですが、新型コロナウイルスが広まりはじめた時期は2か月間の休館を余儀なくされました。ただ、コロナ禍の期間でもキャンプの人気は高かったですし、自粛ムードが明けるタイミングでは一気にお客さんが増えたこともありました。普段、3月というのはかなり空いている時期なのですが、きっと反動があったのでしょうね。やはり人は「旅」を求めているんだということを、とても強く感じました。

男鹿の湯・コテージ(画像提供:水品沙紀さん)
たしかな温泉情報を届けたい。温泉付き物件の不動産業をはじめた背景
―現在は温泉の経営だけでなく、温泉付き物件の不動産業である「湯治屋不動産」も手がけていらっしゃるそうですね。また違った角度から温泉にかかわろうと思ったきっかけはなんだったのでしょう?
水品:自身で温泉巡りをしていると、経営者の血が通っているというか、心遣いが生きている温泉地は、すごくよいところだなと感じます。たとえば、私が経営する温泉を誰かに任せながらチェーン店のようにどんどん増やすという手法は、現実的ではないし、難しいと思います。ただ、違ったかたちで、「男鹿の湯」だけじゃなくていろいろな温泉にかかわるにはどんな方法があるだろうと考えた結果、不動産業というアイデアが浮かんだんです。
私自身、温度が高い源泉のある温泉施設を探しているときに、温泉に関する情報の不確かさに困ったことがありました。それで、「温泉情報がしっかりした不動産屋さん」があってもいいんじゃないか、と思ったんです。
いまは子どもも小さいので、子育てしやすい地域で、なおかつ本物の温泉がある大分県の湯布院で、シャワーのない昔ながらの共同浴場に毎日入る暮らしを満喫中です。大分に来てみたら温泉付きの物件がたくさんあって、お湯の質もいいのが当たり前なことに驚きました。宅建の資格も取り、現在は源泉数日本一の別府温泉の不動産屋で勉強させてもらっています。
温泉付きの物件が豊富なだけあって、私が出会ったお客さまの物件選びの傾向としては、「温泉があること」を前提として「窓から海が見える」など、温泉にプラスアルファとなる要素が決め手になる部分が多いように感じました。その地域の魅力と組み合わせて、温泉のある暮らしを楽しんでいただく方が増えるといいなと思っています。
―温泉が日常に溶け込むという生活は、温泉地ならではのように思います。
水品:そうですね。たとえば別府だったら共同浴場がたくさんあって、地域の人たちも日常的に使っています。別府などだと、入浴する際に挨拶をする文化がしっかりあり、「同時入浴者と親睦を深めること」という心得も掲げられているので、見知らぬ方と湯船のなかでお話しすることも多いです。そういう方と別の場所で会ったりすると、「あのときの、お風呂の!」という感じで一気に打ち解けるような感覚がありますね。
別府に来た当初は、子どもが通っている保育園での知り合いも一人もいない状態でしたが、あるとき保育園の送り迎えですれ違ったお母さんがお風呂で会ったことのある人で、「もう友だち!」という感じで仲良くなれたのもいい思い出です。
―温泉が日常にある街も、ない街も、それぞれで温泉物件の不動産は展開していく予定なのでしょうか?
水品:2018年に栃木県の湯西川温泉で宅建業を営む「湯治屋不動産」を開業し、現在は別府で修行中ですが、機会があればほかの地域でも挑戦してみたいです。関東平野は源泉の温度が低いので、管理が大変な点も多いのですが、一般的な「温泉」に限らない活用の仕方もあると思っています。

「湯治屋不動産」Webサイト
たとえば、東京などの首都圏だったらサウナが流行っているので、サウナ用の水風呂として温度が低い温泉を活用する可能性も大いにあるのではないでしょうか。「男鹿の湯」の源泉も25℃と低めなんです。25℃の湧き立て生源泉は温泉の香りと「ぬるすべ感」が最高なので、「男鹿の湯」では25℃の生源泉とテントサウナを楽しむプランを曜日限定でスタートしました。
それから、理想としては地域を問わず、温泉旅館なども紹介できるようにしていきたいですね。まだ不動産業界のデータベースに載っていないようなところもありますし、「休館しました」とか、「病気で辞めました」という宿の話はつい最近も耳にしました。「温泉のことなら何でも最初に相談できる窓口」という役割を担えれば、と思っています。
温泉が地域活性化のキーになるために必要なこととは?
―全国の温泉を泉質・経営など幅広い観点からご覧になっている水品さんですが、特に温泉を活用した地域活性化の好例として印象に残っているところがあれば教えてください。
水品:個人的には、熊本県の黒川温泉ですね。「温泉地として寂れていて限界」という状況から、ここまで知名度の高い素敵な温泉地になったうえに、質のよいお湯を守り続けているというのが本当にすごいと感じています。
黒川温泉は「黒川温泉一旅館」というコンセプトを掲げ、「温泉街全体がまるでひとつの旅館のように、ともに磨き合う」という考えのもと、地域全体で黒川温泉郷を盛り上げるという思いを共有しました。代表的な施策のひとつが黒川温泉のすべての露天風呂を利用できる「入湯手形」で、これにより「露天風呂巡りの黒川温泉」というブランドが作られました。

黒川温泉
―水品さんは、「温泉」が今後の地域活性化のキーになるためにはどんな要素が必要だと思いますか?
水品:そうですね。温泉について、昔は「湯治」の場として健康を目的に訪れる場所だったけれど、現在では「観光」のなかのひとつのツールに位置付けられている印象が強いなと思います。今後は「観光」にとどまらず、「健康」という観点をキーにみなさんが温泉に集うようにしていけたらとも思います。
そもそも昔は、農閑期に布団と味噌と食べ物を持って、まとまった期間を温泉地で過ごして回復をめざすというかたちの湯治が行われていました。ただ、現代ではそれだけの時間を取ることはもちろん難しいわけです。
最近では、宮城県・鳴子温泉の「旅館大沼」さんが提案している、2泊3日という滞在期間でもゆったりと自分を癒やすことができる「現代湯治」という新しいスタイルの湯治が生まれています。こうした動きがこれから増えていくと、可能性は広がっていくかもしれませんね。
日常的に地元の人たちの健康を支える場でありながら、観光資源として外からの旅行者も受け入れる。そんなふうに「内と外」の人が交わるコミュニティ形成の場になれば、もっと可能性が広がるような気がします。
―逆に、資源としての温泉という観点で課題に感じていることはありますか?
水品:温泉は未来永劫ずっと変わらず湧き続ける、というものではありません。地震の影響で突然止まってしまうこともあれば、泉質が変わってしまうこともあります。私個人としては、資源としての持続が難しくなってきた温泉を無理やり使い続けるよりは、山奥にまだまだ眠っているような湯量が豊富な熱い源泉を活用していく方がよいのではないか、と思っています。
実は、湯量が多すぎて余っている温泉地もあるくらいなんです。そういう温泉地をお客さんが来てくれるように工夫していく方が、手間はかかるけれど長期的にはよい結果につながる可能性もあるのではないでしょうか。
たとえば青森県・古遠部温泉は湯量が豊富で、湯船から常にお湯が溢れているのですが、その溢れるお湯まで無駄なく有効利用して、お客さんが浴室の床に寝転がる「トド寝」を楽しめるようにしています。各地の温泉地でいろいろな楽しみ方を生み出すことで、活用の道が広がることもありそうです。
温泉という資源の有無によって、その地域の活気や繁栄が大きく左右される場所も少なくないと思います。その意味でも、温泉という資源を大切に活かしながら、地域を元気にするきっかけにしていきたいですね。
―最後に、温泉は今後地域にとってどのような存在であるべきだと考えますか?
水品:温泉は、心身を健康にするものであってほしいと思っています。そのためには、できるだけ温泉の効果をそのまま楽しめるようにしたいですね。たとえば、ひとつの温泉にお客さんが集中してしまうと、消毒用の薬品を多く入れなければならない状況になり、温泉の効果が薄まったり、逆効果になってしまったりすることもあると思います。そういった観点でも、いろいろな温泉地にお客さんが分散していく方が望ましいと思っています。
「こういう泉質のお湯に入った後は、別のこういう泉質のお湯に入った方がいい」という泉質の組み合わせにも楽しみ方があるそうです。秋田県の乳頭温泉郷では多様な泉質を持つ複数の源泉を楽しめるのが魅力ですが、たとえば各地の離れた温泉地同士が泉質の組み合わせで結びつくのも面白いかもしれませんね。温泉が好きな人のなかには、遠方の地でも訪れてくれる方が多くいらっしゃいますから。
せっかく温泉天国日本に住んでいるので、日本温泉協会や温泉ソムリエ協会の公式サイトなどを活用し、多くの人により温泉を楽しめるようになってもらえたらうれしいです。私個人としては、温泉学の松田忠徳教授(札幌国際大学観光学部名誉教授)が提唱している「入ってみて眠くなる温泉が、自分に合ったよい温泉。(かかりつけの医師のような)『主治湯』を持とう」という考え方が好きです。一人でも多くの人が自分の「主治湯」を見つけた結果、遠方の地であっても訪れる人が増え、そこで働く人も増えて、という循環がこれから少しずつでも生まれていけばいいなと思います。
まだまだ全国各地の温泉という資源にはさまざまな活用方法があるはずですし、大きな可能性を秘めていると思います。各地の温泉地がそれぞれの温泉の特色を活かすことで、その地域の活性化に貢献する未来にもつながるはずです。私自身も、その未来に貢献できるような活動を自分の周りから続けていきたいと思っています。

男鹿川にて、ご家族と
この記事の内容は2025年1月29日の掲載時のものです。
Credits
- 取材・執筆
- 山本梨央
- 編集
- 包國文朗(CINRA, Inc.)