Theme考える
地域×食の未来はどうなる?『食べる通信』の高橋博之が事例を交えて考える
- 公開日
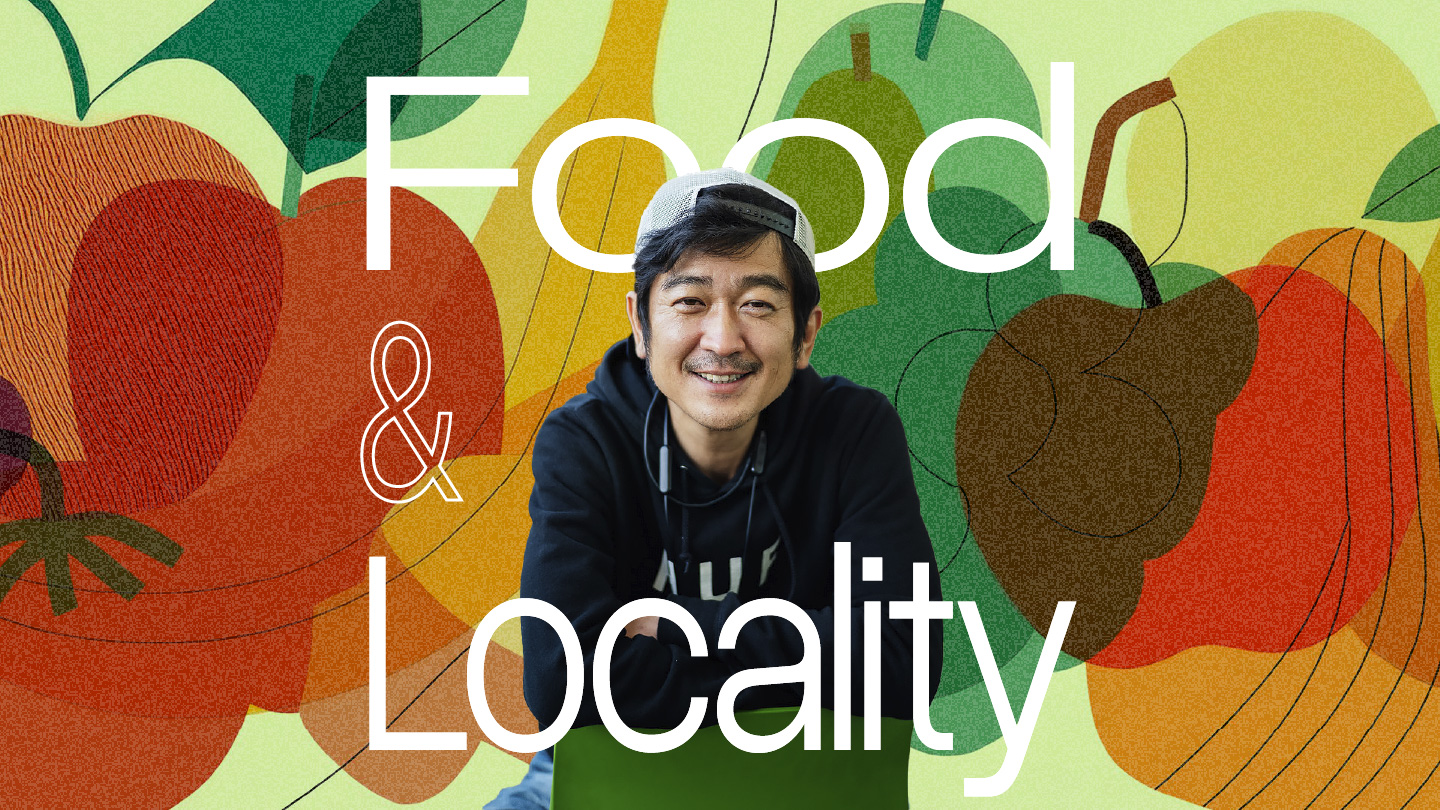
地域の魅力を打ち出す重要な資源ともいえる「食」は、いつの時代も、地域活性化や観光振興の大きな武器になってきました。ただ、人々の価値観や地域との向き合い方の多様化に加え、高齢化と人口減少による農山漁村の後継者不足などの社会課題とも隣り合わせにあるのが現代の「地域×食」。そうした課題解決の糸口を見つけ、各地の「食」を活かしてより発展させていくためには、どんな取り組みや考え方が必要になってくるのでしょうか?
そんな「地域×食」の現代と未来について考えるコラムをお届けします。執筆者は、食のつくり手を特集した情報誌『食べる通信』などを運営する株式会社雨風太陽の代表・高橋博之さん。全国各地の生産者と消費者の声に耳を傾け、食にまつわる産業や社会課題と向き合い、食を通じて都市と地方をつなぐ新しいコミュニティも生み出してきました。
あらゆる地域の食と向き合ってきた高橋さんが考える、現代と未来の「地域×食」における重要な考え方と、カギを握るキーパーソンとは? 2023年に訪ねられた農家の方との実体験エピソードから、よりよい食の未来へつながるヒントをコラムで綴っていただきました。
若手農家と消費者の関係性にあこがれて脱サラ。訪れた「ぶどう園」の話
私は2023年、大阪府柏原市の山間部にあるぶどう園を訪ねた。ここで生産・販売を行っているのは奥野成樹さん(37歳)。大阪の中心、梅田から電車で約1時間の距離にある小さな駅に着くと、奥野さんが軽トラで出迎えてくれた。
農園へ向かう途中、細い道を進んでいくと、傾斜地に家や農園がひしめき合い、あちこちに石垣が見える。「お客さんから『大阪のマチュピチュ』って言われたこともあります(笑)」と奥野さんは笑った。
実は、奥野さんはもともと実家の家業であった農業にまったく興味が持てず、高校卒業後は京都の大学へ進学し、福島県いわき市で会社員として働かれていたそうだ。しかし、そこで出会った若手農家の畑に、常に消費者が手伝いにやってきて、笑いが絶えず賑やかな光景を目にし、「農家って、こんなカッコいい仕事だったのか……」と気づいた奥野さん。農業に対するイメージが一新され、9年前に脱サラして親元で就農したという。

奥野さんのぶどう園「OKUNARY」を訪れた際の高橋さん(画像提供:株式会社雨風太陽)
到着したのは、1.7ヘクタールを有する奥野さんのぶどう園「OKUNARY(オクナリー)」。この地域特産のデラウェアをはじめ、シャインマスカット、巨峰、ピオーネなどの大粒品種を、父と一緒に多品種生産していると教えてくれた。
農業初心者の「オーナー兼消費者」とスタートした共同プロジェクト
就農2年目の2017年冬からスタートした「OKUNARY」は、体験型ワインオーナー制のぶどう園である。耕作放棄地を開拓し、そこに130本の苗木を植え、その130の枠のオーナーを募集。さまざまなバックボーンを持つ農業初心者のオーナーたちと、ぶどうの農作業を行うプロジェクトだ。1つの苗には、おおよそ4~5kgのぶどうが実り、だいたいワイン5本分ほどの収穫となる。
オーナーになることで、ぶどうの栽培工程すべてに携われることと、手塩にかけて育てたぶどうでオリジナルのワインをつくれることが最大の魅力だと奥野さんは言う。
そもそも「OKUNARY」が誕生した事の発端は、大阪府とJAグループ大阪が主催する若手農業者の経営強化プランコンテスト『おおさかNo-1グランプリ』に試しに出場してみたのがきっかけ。農業の魅力発信や担い手不足の課題解決を目的に、このオーナー制の実現に向けた夢を語ったところ、うっかり優勝してしまった。最初は農家として一人前になってからこのプロジェクトをスタートしようと考えていたが、優勝したことで引っ込みがつかなくなったという。
年会費は22,300円(税込)で、現在オーナーは100名以上に増えている。オーナーは自分のぶどうの木に木製のネームプレートを設置し、4月から7月のあいだは芽かき、花切り、摘芯、副梢管理、傘掛け、除草などの自主農作業を行う。オーナーの好きなタイミングで畑に訪れ、奥野さんが自ら撮影した作業動画を参考にしながら汗を流す。
年間を通じてさまざまな農作業があり、7月後半はビニールかけ、9月には収穫祭、11月から12月は防草シートの張替え、1月から2月は剪定、3月は病気対策の作業がある。頻繁に通うオーナーはほかの木の手入れも行う。

「OKUNARY」のぶどう(画像提供:株式会社雨風太陽)
「オーナーたちの畑が、この農園のなかで一番管理が行き届いている」と感心しながら頭をかく奥野さん。2022年の収穫祭には70人のオーナーが集まり、約300㎏のぶどうを20分で収穫し終えてしまったそうだ。
収穫したぶどうは地元のワイナリーで醸造され、各オーナーによる世界にひとつだけのオリジナルワインが完成する。2022年は210本、2023年は250本ほど。完成したワインは、選定作業後にオーナーが集って試飲する機会もあるという。また、知人の飲食店で行われたオーナー同士の食事会では、食事と一緒に自分たちのオリジナルワインを楽しむこともあるそうだ。
オーナーの80%以上が毎年契約を更新しており、なかには自宅の庭で苗木を育てはじめた人もいるという。さらには、奥野さんの1.7ヘクタールの農園を手伝うオーナーもおり、現在は8組が定期的にボランティアとして手伝っている。
こうしたオーナーたちは奥野さん家族のぶどう生産に欠かせない存在となっている。奥野さんは「もっとオーナーを増やし、担い手不足が解消できる新しいモデルをつくりたい」と意気込む。上限130名のオーナーの枠のうち、2023年時点で104の枠が埋まっていた。
第一次産業の未来のカギを握る「プロシューマー」とは?
私は、奥野さんの農園のような「消費者自身が生産に携わるプロジェクト」こそ、「食」の基盤である第一次産業にさらなる発展をもたらしてくれるのではないかと感じている。
実は、そのような未来になることを、約40年前に予測していた人物がいる。未来学者のアルビン・トフラーだ。彼は、1980年に出版した著書『第三の波』のなかで、情報化社会の到来とともに「プロシューマー」という存在が出現することを予言している。
プロシューマーとは、生産者(プロデューサー)と消費者(コンシューマー)を合わせた造語。通信技術が発達した未来では、「生産者=つくる人」「消費者=使う人」という垣根が取り払われ、消費者がモノの生産や販売にかかわる「プロシューマー」になっていくと本書には記されている。
トフラーの予言どおり、情報化社会となった現代。実際、消費者の意見をもとに生産者や企業がプロダクトを開発したり、消費者自身がモノを直接生産・売買できるプラットフォームも誕生したりと、いまや消費者が生産に携わることは珍しくなくなった。奥野さんの農園も、そうしたプラットフォームのひとつであり、そこに集うオーナーたちは、まさにプロシューマーといえるのではないだろうか。

OKUNARYに集うオーナーの方々(画像提供:株式会社雨風太陽)
そうしたプロシューマーがこれからの消費と生産、需要と供給を循環させる重要な存在になっていくと、私は強く感じている。そう思う理由には、時代背景が大きく関係している。
大量生産・大量消費の産業社会を経て情報化社会が実現し、消費者があらゆるモノを見定めたうえで取捨選択できる環境になった現代。消費者は数ある選択肢のなかで質や価値を求めるようになり、「意味のある選択をしたい」という潜在意識が高まった。この「意味のある選択」というのは、そのモノのコンセプトや生産背景に共感できるかどうか、消費者自身にとって本当に必要なものかどうかという視点である。
そして、消費者でもあるプロシューマーは、そうした視点を軸にしながら、モノを生産する。プロダクト起点ではなくユーザー起点でつくられるからこそ、消費者が潜在的に求めている質や価値を体現したモノになり得る。そこから従来の生産者(※OKUNARYでいうと奥野さんの立場)がニーズをとらえ、自身の商品づくりに活かすことができる。
また、生産者・消費者という一方的な視点に縛られないプロシューマーが、モノの魅力をはじめ、生産の想いや背景などを情報発信することで、ほかの消費者からの共感と支持も得られやすくなる。さらには、奥野さんの農園のように、さまざまな立場やバックグラウンドを持つプロシューマー同士がつながり、新たな目線で意見を出し合うことで、モノの質と価値がより向上していく。
そういった観点から、各地でプロシューマーとそのコミュニティが増えることによって、生産と消費の循環がより活性化し、ますます第一次産業が活気づくはずだと期待している。
プロシューマーが機能すれば、生産者の所得向上や一次産業の価値向上にもつながるはず
冒頭でも述べたが、OKUNARYがある大阪府柏原市は、大阪の都市部から車や電車で1時間ほどの距離にあり、気軽に足を運べる。そのためオーナーは地元民に限らず、都市部から通う方が多い。奥野さんはOKUNARYを軸に、多くの都市住民と接点を持ち、ゆくゆくは柏原市への移住者のみならず新規就農者の増加など、「地域×食」の発展を見据えた目標を掲げている。
私は、奥野さんの農園のように、都市住民を地方の生産現場に呼ぶための取り組みやコミュニティの形成が、地方活性化と「食」を支える第一次産業の未来にとって、重要な役割を担っていくと考えている。
その考えにいたったのは、私自身の活動で体感したことが大きく影響している。私は都市と地方の分断と食にまつわる社会課題を解決するために、2013年から食べ物つきの情報誌『東北食べる通信』や産地直送EC「ポケットマルシェ」をはじめた。食にかかわる生産者と消費者を数多くつなぐための取り組みだ。

岩手県大槌町の漁港にて、定置網漁を終えた漁師との2ショット(画像提供:株式会社雨風太陽)

山形県の酪農の現場(画像提供:株式会社雨風太陽)
その活動のなかで、全国各地の農山漁村で生産者と消費者、そしてプロシューマーに出会ってきた。奥野さんの農園のように、プロシューマーが参加するコミュニティは、都市部やさまざまな地域から継続的に地方創生の活動に関わる「関係人口」の人たちが多いということを知った。そうした人たちは、地元の人にはない視点を持っているのが大きな特徴といえる。
ビジネス面では、地元の人たちがこれまで持っていなかったドローンやD2C(*1)などの新たな技術と知見を持ち寄り、「食」に関する生産・物流・販売の可能性を広げているケースが多い。そうした動きがますます活発になり、利益の増加につながれば、地域の「食」を支える生産者の所得や第一次産業の価値の向上にも、大きく貢献していくだろう。
また、多くの地方の農山漁村では、人口減少や高齢化に伴う人手不足が課題となっている。これらは、「食」の未来を担う第一次産業において、深刻な社会課題である。しかし、地元の人たちだけの力ではなく、プロシューマーを含む関係人口が増え、各地でコミュニティが発生して活気づけば、そうした社会課題の解決にもつながっていく可能性は高まるはず。
「食×地域」の明るい未来を築いていくには、地方と都市、地元民と関係人口が持つ、それぞれの価値や魅力を再配列したり、結合したりすることが重要になる。つまり、プロシューマーを含んだ関係人口が増えるような各地の取り組み、そうした人々と地元民の連携、そこでできたコミュニティ活性化の強化などが、「地域×食」の未来を担うカギになるのではないだろうか。
*1 D2C:ダイレクト・トゥ・コンシューマーの略。メーカーやEC事業者が中間業者を通さず、ダイレクトに消費者へ販売する方法のこと。

秋田県仙北市の田んぼで田植えする農家に取材した際の様子(画像提供:株式会社雨風太陽)
この記事の内容は2024年12月19日の掲載時のものです。
Credits
- 執筆
- 高橋博之
- 編集
- 吉田真也(CINRA,Inc.)


