Theme考える
地域おこし協力隊を経て感じたリアルな課題と可能性。町おこしに必要な視点とは?
- 公開日

都市部から地方に移住し、地域活性化に取り組む「地域おこし協力隊」。2009年にこの制度がはじまり、3年間の任期終了後も約7割が移住した地域に定住しています。
今回お話をうかがったのは、それぞれ異なる地域で地域おこし協力隊として活動し、現在も地域に根ざした取り組みを続ける3名の方々。実際に移住して働いたからこそ見えた地域の魅力と課題とは? また3人はそこから、これからのまちづくりにどんな可能性を見出したのでしょうか。未来に向けた地域とのかかわり方のヒントを考えます。
そもそも、地域おこし協力隊とは?
地域おこし協力隊とは、都市部などから過疎など課題を抱える地域に移住し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PRなどの地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの「地域協力活動」を行う、総務省が実施している制度のことです。任期はおおむね1年〜3年ほど*1。
今回お話をうかがう谷口さん、福田さん、井比さんも、地域おこし協力隊の経験者です。
*1 総務省「地域おこし協力隊~移住・地域活性化の仕事へのチャレンジを支援します!~」を参考
この3名は、そもそもなぜ地域おこし協力隊になることを決めたのでしょうか。
自分が培ってきた経験で、地元に貢献できるチャンスだった(谷口さん)
谷口
大学進学で上京してから、所属していた学生団体の活動でさまざまな地域に足を運んでいました。社会人になってからは、広告やITの仕事を経験したあと、地域と企業をつなぐコミュニティの企画や地方創生に関する仕事に就き、そこでも日本各地を飛び回って。各地域の人たちが現地の課題に懸命に向き合われている様子もたくさん見てきたんです。次第に「自分もいつか副業でもいいから、地元に貢献できるような働き方ができたらいいな」と思うようになりました。
そんなタイミングで、地元の新潟県小千谷(おぢや)市で新しくできる施設の立ち上げメンバーを募集していると友人づてに聞いたんです。施設の運営だけでなく、商店街の活性化のためのイベント企画なども含む業務内容に、これまで自分が培ってきた経験をフルに生かせそうだなと感じました。
いつかやろうと考えていたことを、しかも本業でできるなら本望だ、と思いきってチャレンジしようと決めて。その際、募集の要項に「地域おこし協力隊として現地に赴任すること」という条件が含まれていたので、転職と同時に地域おこし協力隊としてUターンした……という流れです。
やりたい仕事が、地域おこし協力隊で実現できる(福田さん)
福田
私は前職でコンビニ向けの商品開発などを手がけていたのですが、だんだんと「都会から離れて、生産者や実際に食べてくれるお客さんの顔が見える仕事がしたい」という気持ちが大きくなっていっていたんです。
そういう仕事を調べていたときに、埼玉県横瀬町への地域おこし協力隊の募集を見つけました。その業務内容に「特産品を活かした商品開発」が含まれていたんです。ここなら明確に自分のやりたい商品開発に携われると思ったので、迷わず応募しました。
仕事で感じていたモヤモヤから心機一転。まずは住みたい場所へ(井比さん)
井比
私の場合、新潟県十日町市のNPO職員の方に「こういう制度があるので、よかったらどうですか?」と、地域おこし協力隊を勧めてもらったことがきっかけです。
当時はブライダル関係の雑誌メディアの営業をしており、新潟市を中心とした上越エリアや魚沼エリアを担当していました。ただ、30歳手前に仕事で少し違和感を抱いていて。このまま同じ業務を続けるよりも、「まずは住みたい場所に移住して、そこで何ができるか考えてみよう」と思い立って、地域おこし協力隊として十日町に赴任することを決めました。
住んだからこそわかる、その地域の「たくましさ」
─参加の背景についてよくわかりました。みなさんは各地域に住んでみて、どのような魅力を感じましたか。
井比
十日町市の人たちには「人間としての力強さ」を感じるんですよね。暮らしにまつわるものは何でも自分たちでつくっていこうとする、言葉どおりの「百姓」的な生き方──あらゆる仕事を自分の手でやり遂げる暮らしを実践している人たちが多くて、とても憧れています。
私の出身地である新潟県柏崎市も、冬には30センチ程度の雪が積もっていましたが、十日町市は3メートルほど積もる豪雪地帯。だからこそ、自然に抗うことなく粛々と共存していこうとする文化が根づいていて、そこにこの街特有の奥深い魅力があるなと感じています。
福田
井比さんの「人間としての力強さ」という表現にはすごく共感します。そういう生活感のともなったたくましさって、都会だとなかなか感じにくいですよね。
ほかの観点でいうと、横瀬町は「よそ者を受け入れてくれるやさしさ」があるところが魅力的だなと感じています。Iターン*2の移住だと地域に馴染むのが難しい……といったエピソードはよく聞きますが、この町の人たちはホントに温かくて、私が何か新しいことをはじめようとすると、すごく応援してくれるんです。
*2 生まれ育った場所以外の地域へ移り住むこと

福田
地域の歴史をたどるとこのエリアはほかの土地から流れてきて住み着いた人たちが多いらしい、という言い伝えも耳にすることがあり、もしかするとそういった背景がよそ者への寛容さにつながっているのかもしれません。
谷口
私の場合は出身地なのでもともと見知った街ではあるのですが、一度離れてから戻ってきてみると、あらためてさまざまな魅力に気づくことができました。
なかでも印象的なのが、長年受け継がれている伝統的な産業の多様さです。花火や錦鯉、へぎそば、闘牛など、古くから伝わる日本の文化を支えている方々がたくさんいて、これらの魅力を市外・県外のみなさんに伝えていきたいなと思っています。
イベント企画や畑仕事、飲食店の運営など、多岐にわたる協力隊の活動
─協力隊として、実際にどのような活動をされていたのでしょうか。
谷口
私の場合は企業に所属しながら活動する「企業連携型」の協力隊でした。大きな内容は、市が持っている「テレワークステーションおぢや」という、コワーキングスペースやサテライトオフィス、セミナースペースがある施設の運営と、その施設がある商店街のにぎわいづくりや新規出店などを目的としたマルシェイベントの企画・運営でした。
また、所属していた企業が県外から企業誘致する活動も行っており、その一環で現地視察の対応や、市民や企業向けのセミナーの企画・運営などもしていました。
これらが主な業務でしたが、その場その場で地域の人たちに頼まれて取り組むものも多く、本当にいろいろな経験をさせてもらいましたね。

「テレワークステーションおぢや」のコワーキングスペース

2025年6月に開催したマルシェの様子。商店街の空き店舗やスペースを活用し、市内外から出店者を集めた
福田
実は私も企業連携型で、最初は地域商社の立ち上げメンバーとして活動をスタートしたんです。そのため就業当初は、会社の雑務から現場仕事まで、さまざまな業務に携わっていました。
地域の農家の手伝い、耕作放棄地の再生、イベントの企画運営、飲食店の経営などなど……一番やりたかった商品開発やレシピ考案の仕事もできて充実していましたが、やることが増え続けて大変でしたね(笑)。
残り半年ほどの任期が残っているタイミングで、企業連携型から個人型に切り替えて、それ以降は個人事業主として地元産のお茶をプロモーションする事業に専念するようになりました。

福田さんが管理している茶畑の様子。剪定や除草、茶摘みなど、管理にはさまざまな仕事がともなう

2024年の秩父夜祭で販売した、福田さんオリジナルのブレンド緑茶。茶葉はもちろん、ブレンド素材の半数以上が横瀬産
井比
お二人は企業連携型で、なおかつおそらく「ミッション型」だと思います。これは、自治体側から業務の内容が大まかに指定されている形態です。私の場合は個人型かつ「コミュニティ型」で、現地に入って住民たちとコミュニケーションを取りながら、自分でミッションを見つけて取り組む内容を決めました。
1年目は町おこしのためのアートイベントの手伝いなどを行いながら、多くの人たちと接点を持って地域のニーズを見定めていきました。2年目以降は、空き家を活用したコワーキングスペースづくりをはじめたり、婚活イベントを企画したり。ほかにも東京で十日町市をPRするイベント開催など、自分から発案していきました。

井比さんが1年目に携わったアートイベントにて、作家さんと撮影
下の表は横方向にスワイプできます
【地域おこし協力隊の「○○型」とは?】
公式な分類ではないが、地域おこし協力隊員などのなかで役割を整理をする際に用いられることがある用語。おおまかに以下のようなものがある。
| 種類 | 概要 |
| 企業連携型 | 企業と地域の連携プロジェクトに参加して活動 |
| 個人型 | 地域の課題からやるべき企画を考案、行政などに提案しながら活動を遂行 |
| ミッション型 | 観光PRや農業支援など、自治体が設定した課題に対して取り組む |
| コミュニティ型 | 住民と一緒に地域行事や暮らしを支え、自分で課題を見つけて取り組む |
「みんなハッピー」は難しい? 地域活動のリアルな課題
─地域で活動をするなかで、特に大変だなと感じることはありますか?
福田
いい意味でも悪い意味でも、商売っ気が薄いところです(笑)。横瀬町にはすごく質の高い農作物をつくっている人たちがたくさんいるんですけど、「人にあげるのが好き」とか、「育てるのが楽しい」というモチベーションの方が多いので、商品化して売り出すことをあまりしていないんです。この地域ならではの温かい人柄が出てはいるのですが、「ビジネスや町のPRにもっと生かせるのに、もったいないなあ」と感じることがありますね。
谷口
私の場合、活動当初は新しいことをしようとすると「それって本当に必要なの?」と、一部の地域の人たちから少しネガティブなリアクションをもらうことはありましたね。
ただ、個人的に自分の役割は「新しい何かを地域に持ち込んで盛り上げること」であり、アクションを起こし続けていくことだと考えていて。そのため「いろいろな声があるけど、なんとか頑張っていこう」という気持ちで動いていました。
そんなふうに挑戦を続けていると、そのうち人づてに「あの人よくやってるね」という評価を聞く機会も増えてきました。直接褒めてもらうことはほとんどないのですが(笑)、それも地域性かなと。

谷口
市外から人を呼び込む取り組みをして、それがメディアなどで紹介されると、風向きがポジティブなほうに変わっていきますね。
井比
谷口さんが直面した苦労は、地域おこし協力隊には必ずついて回るものじゃないかな、と思います。コミュニティで新しいことを提案すると、やりたいという人もいれば、やりたくない人も必ず出てくる。そこから、どれだけ異なる意見の方々を中立に持っていくための働きかけができるかが、ローカルで物事を動かすカギになるんですよね。私もそのあたりの折衝に、毎回骨を折っています。
どんな「地域のための活動」でも、全員の利益を守ることは難しい。利益の大きい人と少ない人、もしかしたら不利益を被るかもしれない人、それぞれのバランスをどう調整していくか――そこに体当たりで挑んでいくのが、地域おこし協力隊の大変な部分でもあり、醍醐味のひとつだといえますね。
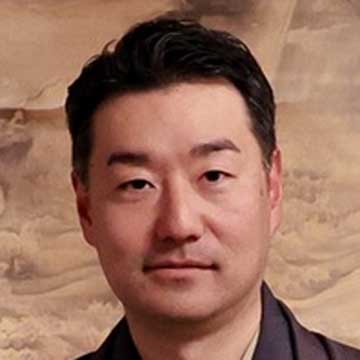
井比
以前「全国のお米を食べ比べ」イベントを実施したところ、味の違いを楽しんでくれた地域の方には「もっとおいしいお米をつくろう!」と好評。でも地元米の評価が伸びず、一部の方には不評でご指導いただく一幕もありました(笑)
それぞれの課題に、独自の方法でアプローチ
─実際に各地域で過ごして、あらためて解決したいと感じた課題はありますか?
谷口
「地域の伝統的なお祭りをどう存続させていくか」が、直近で感じている大きな課題です。とある神社で長年続いてきたお祭りがあるのですが、主要な担い手が高齢化していることもあって、体力的にも経済力的にも存続が危うい状態なんです。こうした地域のお祭りって、一度途絶えてしまうと、復活させるのはすごく難しい。
そこで、昨年からこのお祭りのための実行委員会を新しく組織して、30代から40代の比較的若い世代のメンバーが中心になって、お祭りのなかで新たな企画をいろいろと立ち上げています。
伝統的な神事は神社の維持や管理を行う氏子のみなさんに続けていただきつつ、マルシェのようなかたちで市内を中心に出店者を募ったり、ステージで市内出身のミュージシャンや子どもたちのダンスチームにパフォーマンスをしてもらったり。そういったアプローチでお祭りのあり方を見直し、いまのかたちに合った、持続できるやり方を模索しながら、財務的にも赤字なく成立させられるようにしていきたいと考えています。

毎年7月に行われている二荒神社祭礼

二荒神社祭礼で、市内出身の若手によるダンスパフォーマンス
福田
うちの地域では「農業の担い手不足」が一番の課題だと感じています。横瀬町は中山間地域でお茶を育てている農家が多いのですが、傾斜地での農作業は平地よりも格段に負担が重いんです。
現役農家のおじいちゃんおばあちゃんも「子どもにわざわざ大変な仕事を継がせなくてもいいんじゃないか」という人が多くて、10年以内には農家が大幅に減ってしまうのでは……と危惧されています。
私も今年から、担い手がいなくなって数年経った、もはや農地だった痕跡もほとんど残っていないお茶畑を、地元の有識者と一緒に再生する活動をはじめました。こうした取り組みにもっと若い世代を巻き込んでいきたいのですが、地元にはそもそも若者が少なくなってきているので、隣接する自治体とも協力しながら活動を広めていきたいなと思っています。
井比
お二人に比べると少し抽象的なんですが、私は「アイデンティティの再定義」が最大の課題だととらえています。十日町市をはじめとする雪国の人たちって、自分たちの地域の暮らしや文化に潜在的にはプライドを持っていても、現状ではそれがなかなか伝わらない状態なのかな、と感じるんです。
私たちの暮らす地域は、全国ニュースでよく「何メートルも雪が積もる場所」として紹介されることが多いです。それはつまり、「雪が多くて暮らしが大変、辺鄙(へんぴ)で不便な街だ」という、ある種のネガティブなイメージを押しつけられ続けている、ともいえるでしょう。その影響もあって、地元の人たちが自分の街に誇りを持ちにくく、自虐的になってしまう可能性もあるんじゃないかと思うんです。
しかし実際は、雪とともに暮らすことが当たり前ですし、この雪のおかげで、豊かな水資源が得られています。そして、雪による貴重な資源を生かし酒造りや染め物などの素晴らしい地場産業を育んできました。そこには、この土地ならではのたくましさと地域愛が根づいているはずです。

HOME HOME NIIGATでは、雪国ならではの文化を体験してもらうため、かんじきを履いて雪上を歩くツアーを行っている
井比
雪はマイナスでもあるが、プラスでもあり、私たちの文化には欠かせないもの――そんな前提を踏まえて、100年後も自分たちの暮らしに誇りを持てる街であるために、いま一度「雪国」としてのアイデンティティをフラットにとらえ直す必要があると考えています。
協力隊を経て見えた「地域おこし」に必要なスキルとは?
─ご自身の協力隊での経験を踏まえ、これからIターン・Uターンをして地域おこしにかかわっていきたいと考えている人たちに向けてアドバイスをするとしたら、どんな言葉をかけますか?
谷口
「利他の精神をどのくらい持てるかが重要だ」と伝えたいですね。外からやってきて「いまの地域にはこれが必要だ」と新しい物事を押しつけるのは、たとえそれが合理的であったとしても、地域の方々に対してとても失礼な行為です。
地域にはそれぞれ、その土地特有の多様な文化や人間関係から成る「営みの循環」のようなものが存在します。地域での活動のスタートは、まずその循環に入って、溶け込めるかがカギになるでしょう。そこで必要になるのが「利他の精神」なのかなと。

谷口
「地域のみなさんの仲間になりたい、役に立ちたい」というのを、行動で示していくことが大事だと思います。
福田
わかりやすく「仲間になりたい」という意思表示をするのは大事ですよね。その文脈でいうと、私は「挨拶をする、お礼を言う、謝る」の3つは、常に意識しています。どんな小手先のスキルよりも、コミュニケーションで基本的な行動を徹底することが、いい関係を築くための土台になる気がするからです。
あとは、ベタかもしれませんが「相手に興味を持って話を聞くこと」でしょうか。「地域のため」は、やっぱり「地域の人たちのため」と同義であるべきで、そこに住む人たちのことを知れば知るほど、なるべくみんなで幸せになる道筋が見えてくると思うんです。実際、こちらが興味を持つと、向こうも興味を持ってくれるし、かかわる人たちのバックボーンが理解できると、物事も円滑に進みやすくなるはずです。
井比
地域が抱えている課題というのは、いろいろな社会課題が何十年にもわたって積もりに積もった、分厚い岩盤のようなもの。その壁を前にしたら、自分ひとりの力なんてあまりにも無力です。
でも、無力なりにできることはある。私が協力隊として初期に一生懸命やったのは、草刈りでした。相手から求められるフェーズにならないと、いくら企画書を書くのが上手くても、そのスキルは何の役にも立たないんです。
汗を流しながら、愚直に地域の人たちのために行動すると、少しずつ受け入れられて、頼られ、悩みを相談されるようになる。それくらいの信頼関係を築けたときに、はじめて地域の課題解決の入口に立てるんだと思います。
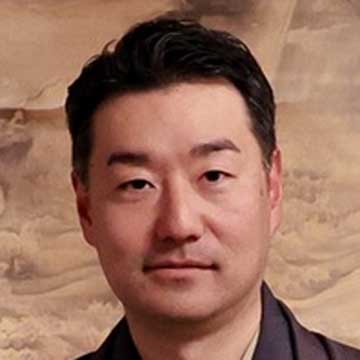
井比
少し厳しい言い方かもしれませんが、「外から新しい人がひとり来たぐらいで、すぐに変わることなんかない」ということは、心に留めておいたほうがいいかもしれません。
─協力隊としてかかわった地域で、今後どのような活動を広げていきたいですか?
谷口
地域内で空き家が急速に増えているので、それらを活用して飲食の営業や物販ができるような場所をつくろうと計画しています。
空き家の活用がうまくできれば、外から人を集める手段にもなるし、地元の人たちが小さくビジネスをはじめるハードルも下がるので、一石二鳥かなと。こうしたプロジェクトを展開しながら「小千谷を面白がれる人」を地道に増やしていきたいですね。
福田
最近、思いきって山の上に古民家を購入したんです。そこで町の特産品を扱うアンテナショップ兼カフェを開業するための準備を進めています。地域内外の人たちの交流が生まれるような拠点になるよう、時間をかけて場づくりしたいと考えています。

福田さんがカフェ開業を試みている古民家の様子
井比
市内には30年後に消滅してしまうと予想されている限界集落がいくつかあります。そこにゲストハウスをつくって、観光業の活性化による新しい仕事を生み出すことで、少しでも持続可能な状態で町を維持できないか……というアプローチを検討しています。
外から人を呼び込める観光業の実現は、中の人たちがシビックプライドを取り戻すためのアプローチでもあるととらえています。ツアー企画や民泊の運営を通じて「この地域は面白いですね」と言ってくれる人を増やすことで、地域のアイデンティティを温めていきたいですね。
※当記事内の記述においては、発言者の表現を尊重し、職業の歴史的表現を含みます。現代の職業一般を指す言葉としては用いておりません。
この記事の内容は2025年11月18日掲載時のものです。
Credits
- 取材・執筆
- 西山武志
- 編集
- 森谷美穂(CINRA, Inc.)


