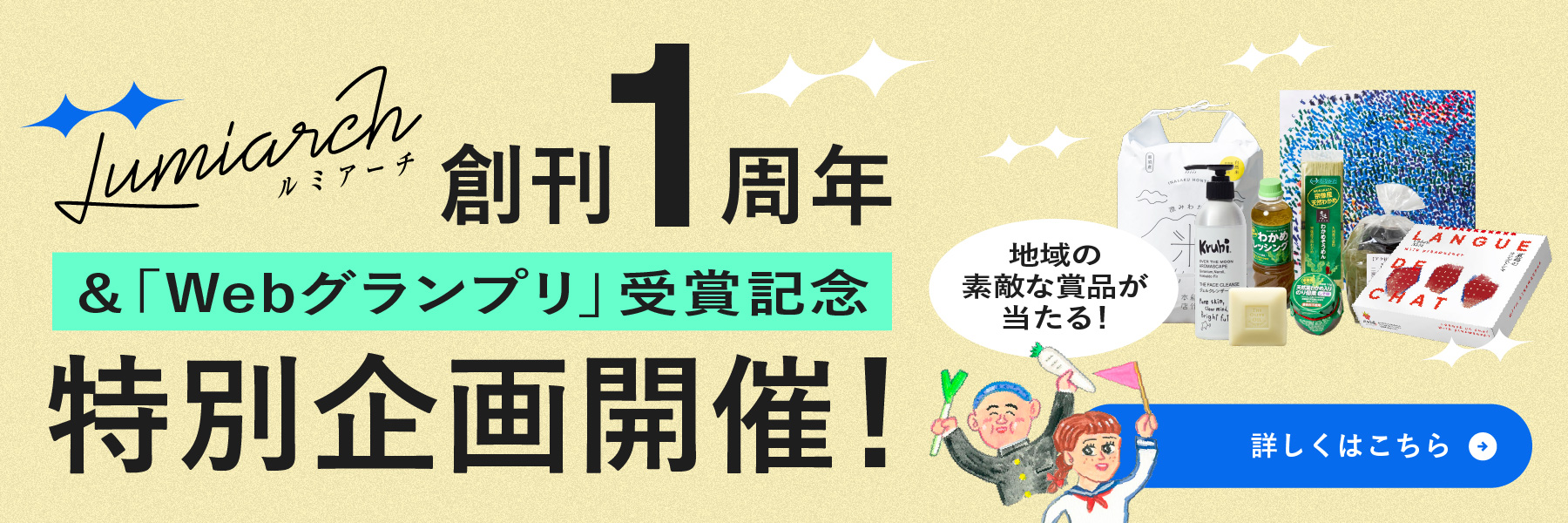Theme知る
北海道仁木町を「ワインの町」へ。髭男爵・ひぐち君と訪ねるNIKI Hills Winery
- 公開日

人口減少や高齢化が進むなか、地域産業を起点に地域の未来を切り開こうとする動きが全国に広がっています。そのなかでも注目を集めているのが、「ワイナリー」の存在です。地域の風土や文化を活かしたワインづくりは、その土地ならではの魅力を表現すると同時に、新たな付加価値を生み出しています。
北海道南西部に位置する仁木町の「NIKI Hills Winery(ニキ ヒルズ ワイナリー)」もそのひとつ。自然との共生を理念に土づくりからはじめ、ブドウ畑と森が共存する美しい環境をつくり出し、地域とともに歩んできました。
今回その地を訪れたのは、日本ワインの魅力を発信し、全国200以上のワイナリーを巡っている、お笑い芸人・髭男爵のひぐち君。仁木町隣町の「余市町ワイン大使」も務めるほか、日本ソムリエ協会のソムリエ・ドヌール(名誉ソムリエ)にも就任しています。NIKI Hills Winery総支配人・舟津圭三さんとともに、日本ワインの魅力やワインを通じた町おこしの可能性を語り合います。
仁木町にワイナリーを立ち上げた理由。冒険家と果樹園の出会い

今回の対談取材の舞台となる、北海道仁木町のNIKI Hills Winery。雄大な自然に囲まれ、レストランやホテル、ツアーアクティビティなどが楽しめる複合型ワイナリー
2014年、丘の上にある33ヘクタールの広大な敷地で事業をスタートしたNIKI Hills Winery(以下、NIKI Hills)。仁木町と余市町を見渡せる自然豊かなこの場所で、どのようにワイナリーが誕生したのでしょうか。その歩みを、「余市町ワイン大使」として活動するひぐち君が、NIKI Hills の総支配人・舟津さんとの会話から紐解きます。
ひぐち君
実は、僕がワインの世界に足を踏み入れたのも、およそ10年前なんです。芸風からワインイベントに呼ばれる機会が多かったのですが、あるとき、知識がなく見当違いなコメントをしてしまって大失敗しました。それをきっかけに、「しっかり学んで話せるようになりたい!」と思い、ワインの勉強をはじめました。そこから資格を取り、はじめて足を運んだ日本ワインのイベントで余市の生産者と出会ったんです。その体験が大きな転機となり、日本ワインの奥深さに一気にのめり込みました。
日本ワインは繊細で、和食や京料理に合う「出汁」や「旨味」のようなものを感じるのが特徴だと思います。ワインは自然環境や気候によって違いが出るのが面白いなと思っていて。なかでも北海道のワインは、冷涼感のある爽やかな酸味が特徴的ですよね。仁木町と余市町で比較すると、同じケルナー種でも余市は赤りんご、仁木は青りんごのような果実感があります。
だから今回、NIKI Hills Wineryを訪ねるのをとても楽しみにしていました。これだけのワイナリーを立ち上げるのは壮大な物語があったと思いますが、まず舟津さんがかかわることになったきっかけからおうかがいできますか?
舟津
ありがとうございます。ワイナリー計画との出会いは、現オーナーである石川和則との出会いです。私はもともとアメリカのアラスカ州で22年間アウトドアガイドの仕事をしていたのですが、冒険家でもあった石川とは北極点へ向かうクルーズで出会いました。その後も一緒に南極点や北極点を冒険していたんです。
その中でNIKI Hills Wineryの構想を打ち明けられました。それで一緒にワイナリーを立ち上げるために「日本に戻ってこないか」と言われて。

ひぐち君(髭男爵)
お笑いコンビ・髭男爵のボケ担当。2015年に日本ソムリエ協会認定「ワインエキスパート」を取得。「余市町ワイン大使」として広報活動に尽力しながら、日本全国のワイン産地を巡っている。さらに、自身のオンラインサロンでワインイベントを開催するなど、日本ワインの魅力を幅広く伝えている

舟津圭三さん
NIKI Hills Winery総支配人。犬ぞりとスキーによるグリーンランド縦断や、史上初の犬ぞりによる南極大陸横断に成功するなど、冒険家として活躍。北極点へ向かう途中、オーナーの石川和則と意気投合し、北海道仁木町でのNIKI Hills Wineryプロジェクトヘ参加。2015年よりNIKI Hills Winery総支配人に就任する
ひぐち君
どんな構想だったんでしょうか?
舟津
ここは冬は雪に包まれ、夏は森から爽やかな風が吹き抜ける、世界でも珍しい環境です。しかし、もともとは果樹園だったこの広大な土地も、後継者不足により一部が耕作放棄地となり、荒れ果てた状態でした。
それでも、この地の風景の素晴らしさに惹かれた石川は、ここで観光事業を軸としたワインツーリズムの可能性を見出したんです。地域振興や経済活性化、ひいては地方創生につながると確信し、ここを開墾してワイナリーをつくる構想が浮かび、そこに私も参画してほしいと。
私もワインが好きで、ワイナリー巡りもしていたので、アラスカ在住時の開墾生活の経験が役立つのならと、この町に来ることを決めました。

ブドウ畑の先に見渡すことができる、北海道余市町と仁木町の町並み
ひぐち君
僕も全国各地のワイナリーを巡ってきましたが、NIKI Hillsのように、ブドウ畑の周辺に森やガーデンを整備し、豊かな自然環境をつくり出している場所は、世界的に見ても本当に珍しいと思います。
舟津
そう言っていただけてうれしいです。森の整備に関しては、ナチュラリストとして知られるC.W.ニコル氏にアドバイザーとして入っていただきました。
防風林として約80年前に植えられたまま放置されていた森は、風通しが悪くなっていた。そのため、間伐を進めて風が流れるようにしました。この風の流れは、空気の澱みを取り除き、害虫の発生を抑えるなど、ブドウ畑にもいい影響を与えています。
ひぐち君
そうした自然環境の整備や美しい景観にこだわっているワイナリーだからこそ、美しいワインが生まれるんですね。はじめてここでつくられたワイン、「HATSUYUKI 2015」を飲んだとき、きれいでエレガントな、とても美しいワインだと感じたので、いまのお話を聞いて納得しました。

NIKI Hills内にある、舟津さんが造成した広大な森

NIKI Hillsの代表格である「HATSUYUKI」。写真は2024年に醸造されたもの
人間も自然も、すべてがつながっている。仁木町と地域ブランディング
美しいワインをつくるために、ブドウ畑や周辺の自然環境をつねに整えているNIKI Hills Winery。その背景を探ると、そこには「人と自然はすべてつながっている」という思想がありました。
舟津
ワインをつくるためには、まず豊かな自然を育むことが不可欠です。そうすることで生態系が循環し、良質な微生物が育ち、土壌が豊かになる。そしていいブドウが実るのです。この命のつながりを実感できることで、人の心も豊かに、美しくなり、愛情のこもったワインをつくることができます。
ひぐち君
「イライラしていると荒々しいワインになってしまうし、やさしい気持ちでつくると、やさしいワインになる」と僕も聞いたことがあります。
舟津
まさにそのとおりで、人間がストレスを感じると腸内細菌が悪くなるのと同じように、畑の土壌も条件が悪いと微生物が育ちにくくなる。それが最終的には、ワインの味にも影響してくるんです。

取材した8月下旬頃、ブドウ畑はたくさんの実が成っていた。シャルドネという品種で、10月くらいに収穫するそう
ひぐち君
それはワインを飲む側にも当てはまると思います。リラックスしていれば、その土地のワインの味を豊かに受け取れるもの。NIKI Hills内のレストランや宿泊施設も、訪れた人が優しい気持ちで過ごせるようにつくられていると感じます。
舟津
そうですね。忙しい日常から離れて、リラックスしながら豊かな時間を過ごしていただきたい。そうすることで五感を通じてワインを楽しみ、食事を味わい、自然そのものを感じてもらえる。自分が自然の一部であることに気づき、自然に帰れる空間でワインを味わっていただく。それこそが私たちのミッションだと思っています。

NIKI Hillsに併設されているホテル。窓からはブドウ畑や、余市湾まで見渡せるヴィンヤード ラグジュアリー ルーム(画像提供:NIKI Hills Winery)

滞在期間中は自然を感じ、リラックスしてワインを楽しむことができる(画像提供:NIKI Hills Winery)
地域一体で「ワインの町」をブランディング。ワインに宿る、土地の魅力と人をつなげる力
2025年2月時点で、北海道内のワイナリー数は71か所となり、10年前の約3倍に増加*1。なかでも北海道余市郡の余市町・仁木町では、合わせて約25軒のワイナリーが開業(2024年時点*2)しています。地域一帯が一大ワイン産地になろうとしているいま、その盛り上がりをお二人も肌で感じているといいます。
舟津
仁木町・余市町のエリアは、間違いなく「ワインのメッカ」になってきていますよね。2022年に仁木町ワインツーリズム推進協議会が設立され、町の後援と観光協会の協力を得て、NIKI Hills内でもさまざまなイベントやワインセミナーを開催しています。
2023年からは、ワイナリーを巡りながらワインと地域の食を一緒に楽しめる『ワイリングウォークフェスNIKI』がはじまりました。1回目の参加人数は200人でしたが、年々増え、3回目の今年は500人が来場されました。いまではチケットが即日完売するほどの人気となっています。

「ワイリングウォークフェスNIKI2023」の様子。仁木町のワイナリー11社が集まりワインを提供する(画像提供:NIKI Hills Winery)

イベントで提供しているすべてのフードは、仁木町がある後志(しりべし)管内エリアの食材を使ったもの。当日提供しているワインに合わせて、その日のためだけにシェフが開発している(画像提供:NIKI Hills Winery)
ひぐち君
僕も仁木町でのイベントには注目していますが、特に冬に開催されている『冬のワインパーティ in NIKI -仮面葡萄会-』が気になっています。生産者と参加者の垣根なく、ワインや食、音楽を一緒に楽しめる場として、毎度大盛況だそうで。ワイナリー、町、観光協会、そして町民のみなさんが協力して「ワインの町」としてブランディングしているのが本当に素晴らしいなと。僕も呼ばれたいです!
舟津
ぜひぜひ、来てください。まずはそうしたイベントを軸に、仁木町の魅力も知っていただくきっかけになればとスタートしました。結果的に、以前は余市町とニセコ町の通過点でしかなかった仁木町が、ワイナリーの集まる地となり、自治体も「ワインの町」として取り組みに積極的になってくれました。NIKI Hillsとしても、「仁木町を盛り上げる牽引役」を果たせているという自負はあります。

「冬のワインパーティ in NIKI – 仮面葡萄会」では、仁木町のワイン生産者たちが「冬にワインを飲みに来てほしい」「ワインの魅力を直接伝えたい」という想いから、生産者10社が25種以上のワインを提供
ひぐち君
NIKI Hillsさんの存在がなければ、この地域一体も10年でここまでの発展はなかったと思います。
また町全体にワイナリーが増えてきたことで、仁木町はワインの町として観光客が訪れる場所になっていますよね。それにともない、ワイナリーだけでなくレストラン、宿泊施設も増え、地域活性化にもつながっていくのかなと思います。

舟津
そうやって人が集まり、地域が元気になっていくのは理想的ですよね。
ひぐち君
余市町のワイン大使としても感じるのですが、ワインの魅力は「地元の食材とペアリングができる」という点にある気がして。地元の野菜や米、フルーツ、肉や魚などと合わせられるからこそ、地域全体が盛り上がり、町全体がつながっていくのではないかと思います。人を集め、土地の魅力と人をつなげる力が、ワインにはあるんです。ワインをきっかけにその土地を訪れる人も多いので、そういうかたちで地域に貢献できればと思っています。
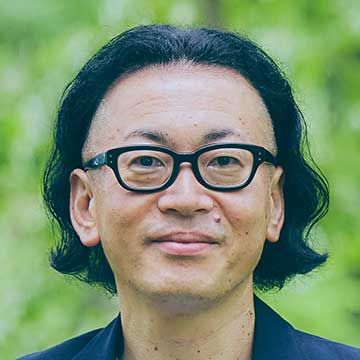
ひぐち君
あと、つくられた地域で飲むのがいちばんおいしい!!

ひぐち君が地域の野菜をふんだんに使った料理に合わせていただいたワインは、「ピノ・ノワール(Pinot Noir)2023」。自社畑産100%のピノ・ノワールは、軽やかでありながら複雑な味わいで、野菜との相性が抜群なのだとか

「ザクロやラベンダーのようなアロマに、土っぽいニュアンスも。冷涼感のあるきれいな酸味が感じられます。ワインの複雑な味わいがいろいろな野菜とマッチして、一口一口が楽しいペアリングですね!」
ひぐち君
そして、その地域の魅力やつながりを絶やさずに継続していくことも重要ですよね。ワイン用のブドウは、植樹して収穫できるようになるまでは3〜4年ほど時間がかかります。しかし大切なのは、そこからさらに続く未来です。50年後のブドウの樹木からもワインがつくれることがあるように、いまから「種まき」をしていく視点も大切だと思います。
舟津
まさに私たちも、そうした取り組みが大事だと思っていまして。未来につながるワインづくりの一環として、仁木町からの依頼で教育委員会と連携し『仁木町子ども体験塾 特別講座』を実施しています。
仁木町で育つ子どもたちの「生きる力」と「ふるさとへの愛着」を育むため、2020年からはじまりました。ワインづくりの流れを3回に分けて体験する事業です。対象は小学4年生で、10月に収穫、11月に醸造、2月にラベル貼りと、20歳の自分へ宛てたメッセージを作成し、「マイボトル」を作成します。これはNIKI Hillsで保管され、10年後に本人がお酒を飲めるようになってからお渡しする予定です。

20歳になった自分へ向けて、思い思いのメッセージを込めた「マイボトル」(画像提供:NIKI Hills Winery)
舟津
体験後には、ワイン造りの体験を修了したことを証明する、オリジナルカード「ジュニアマエストロ修了証」をプレゼントします。
この取り組みも今年で6年目を迎え、あと4年で第1期生が取りに来る予定です。仁木町を代表する産業となったワインづくりをとおして、子どもたちがワイン文化に親しみ、誇りを持てるよう、これからも続けていきたいと思っています。
ワインと地域の理想的な関係とは? 住民・行政・ワイナリーがつながる、まちづくりのヒント
「仁木町や余市町のワイン産業が評価される一方で、地元の人々の関心はまだそこまで高くない気がする」と分析する、余市町ワイン大使のひぐち君。そこで、地域とワインの理想的な関係性について、舟津さんとよりよいアイデアを探ります。
ひぐち君
日本ワインの有名な産地でさえ、地元の人が地元のワインを飲んでいない現状があります。余市町や仁木町ではまだまだ歴史が浅いということもあり、地元の人がこの町のワインが人気であることを、イベントの賑わいを見てはじめて知るケースも少なくありません。いまはまだ、少しずつ気づきはじめている段階というか。
僕の理想は、フランスやイタリアのように「地元の人は地元のワインしか飲まない」という状態になること。そんなふうに、地域の人みんなが地元のワインに誇りを持つようになれば、有名な地酒や地ビールのように、地域の日常にもより溶け込んでいくはず。日本食に合うのはやっぱり日本ワインだと思うんです。もっと有名な温泉地や、いろいろなレストランなどでも日本ワインを置いてほしいですね。
そうなれば、旅行で訪れた人たちも町のレストランや宿泊施設などで、そのワインを目にする機会が増え、結果的にいろんな人に仁木町や余市町のワインの魅力を知ってもらえることにもつながると思っています。

舟津
そのためにも、行政とワインのつくり手が連携し、戦略的に仕掛けていくことが大切ですよね。加えて、ワイナリーが単独で成功しようとするのではなく、横のつながりで情報交換をしながら、ともに発展していく姿勢が重要になってくると思います。
ワインを中心に人が集まり、地元の食材とペアリングを楽しむ。その体験をきっかけに、ワイナリーだけでなく、レストランや宿泊施設、やがて地域全体がつながっていく。それが、町全体を一体にする好循環を生むのだと思います。
ひぐち君
そうですね。ワインには人をその土地に惹きつける力があると思っていて。僕みたいに、「このワインいいな」と思ったら、その産地に行くようなワイン好きはもちろん、まだワインに興味を持ちはじめた段階という人も、気軽に足を運べるようなまちづくりができるといいですね。ワインがきっかけで、その土地や地域に興味を持ち、行ってみたくなるような。
そうした動きが、結果的に地域の人々のワインへの関心や、自分もかかわってみようなどというポジティブな循環も生むかもしれませんね。
舟津
私もそう思います。NIKI Hillsとしても、世界一のワイナリーをめざしているので、世界各地のいろんな方々に来ていただけるように下地づくりを進めていくつもりです。

ひぐち君
実際にいま、日本ワインに関心の高い外国人が最も注目しているのが、仁木町や余市町だと思います。僕自身も、海外の日本ワインファンとの交流を通じて、その熱気を肌で感じていますから。
もし、僕がいま新しいイベントを考えるなら、山側の仁木町から余市町へかけて中央を流れる余市川をテーマにしたイベントをやってみたいですね。「余市川の右岸と左岸にある、それぞれのワイナリーのワイン飲み比べ」のような。
ボルドーでも、右岸と左岸では土壌や気候が異なり、ワインの味にも違いが出ます。その違いをつくり手と一緒に体験できたら、地域やワインへの理解がさらに深まるのではないかと思うんです。
舟津
そうした学びのあるイベントも面白そうですよね。ひぐち君にぜひ仁木町にも来ていただいて、そんなイベントをご一緒できたらうれしいです。

この記事の内容は2025年10月30日掲載時のものです。
Credits
- 取材・執筆
- 宇治田エリ
- 撮影
- タケシタトモヒロ
- 編集
- 篠崎奈津子(CINRA, Inc.)