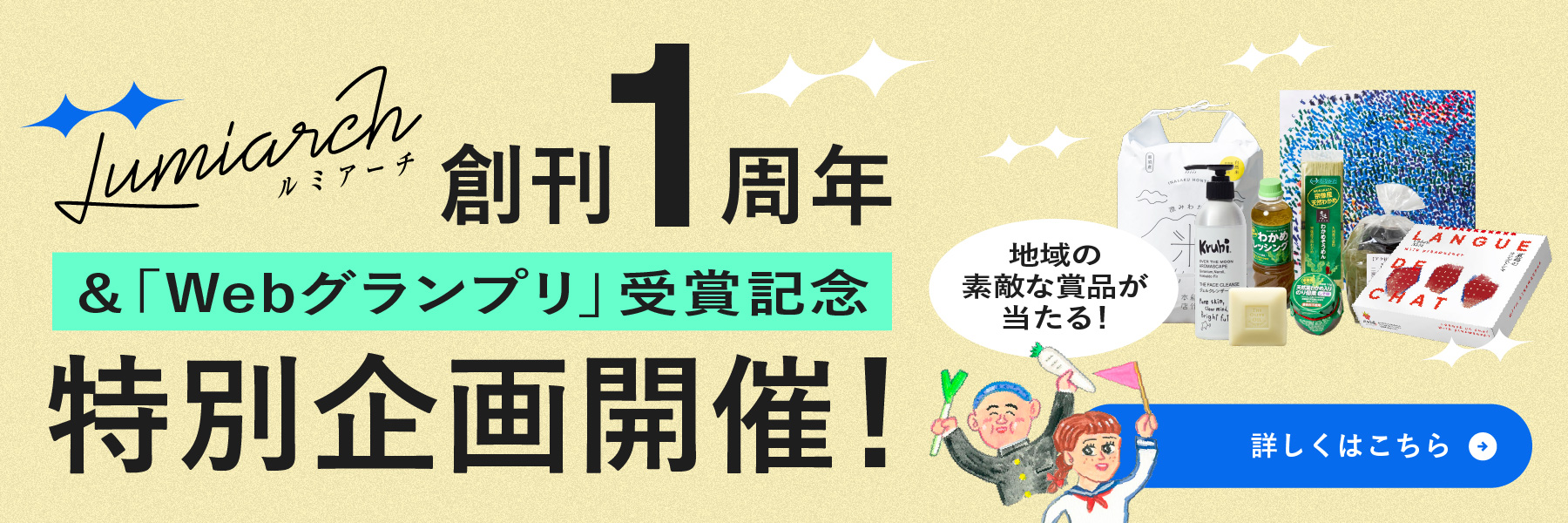Theme学ぶ
音楽フェスが開催地域にもたらすものとは?津田昌太朗に学ぶ、国内の事例で見える可能性
- 公開日

かつて音楽フェスは「音楽好きのための空間」という印象がありましたが、音楽だけでなく、いまでは開催される地域の食やアート、伝統文化などを楽しめる「地域密着型」フェスが全国各地で存在感を増しています。
自然豊かなロケーションや地域の人々とのふれあいが魅力のフェスは、地域活性化にも貢献します。なぜ音楽フェスは、地域と相性がよいのでしょうか?
今回は、年間40本以上の音楽フェスに足を運び、国内外のフェスシーンを知り尽くす「Festival Life」編集長・津田昌太朗さんに、フェスが地域にもたらすメリットや、地域の特色を活かした取り組み、地域との持続可能な関係づくりのヒントをうかがいました。
音楽好きの場から地域のプラットフォームへ。進化する「フェス」の現在地
―津田さんは長年にわたり、多くのフェスに参加されています。音楽フェスが開催地域とのかかわりを深めていったのは、いつ頃からだと感じていますか?
津田:僕がフェスに通いはじめた2000年代前半頃は、新潟県湯沢町で行われている『FUJI ROCK FESTIVAL』のような大規模フェスが主流で、音楽好きのための場という印象でした。でも2000年代中盤あたりからアウトドアブームの影響などもあって、音楽だけじゃなくフェスでのファッションやフードなど、カルチャー全体を楽しむ場として広がっていったんです。
大きな変化が起きたのは、2011年の東日本大震災のあと。「地域のためにフェスをやろう」というような動きが活発になり、フェスを開催する意義があらためて見直されました。さらにコロナ禍で多くのフェスが中止を余儀なくされ、人々が集まる場や人と人とのつながりが一時的に断たれたことで、「フェスは地域とどうかかわるべきなのか」という点も問われるようになりました。実際、フェスの開催には地域の理解と協力が不可欠。コロナ禍を経て「地域との連携なしにはフェスは成り立たない」「地域とうまくかかわれなければ続かない」といった現実が、より明確になったんです。その結果、地域の特色や文化と音楽をかけあわせた「地域密着型フェス」への注目度がますます高まっていったと実感しています。
―特に開催地域とのかかわりが強いと感じたフェスはありますか?
津田:やっぱり象徴的なのは『FUJI ROCK FESTIVAL』ですね。1997年に山梨県・富士天神山でスタートし、1999年からは新潟県湯沢町に開催地を移しました。実績のあるフェスとして鳴り物入りでの開催でしたが、当時の日本にフェスがあまり定着していなかった背景もあり、当初は全国から多くの来場者が集まることによる「ごみ問題」や「マナー」などへの懸念から、懐疑的な目もありました。
しかし、主催・運営を行っているSMASHが中心となって、会場の外にはごみを落とさないよう、ごみの自己管理を徹底させたり、来場者に地域への配慮を呼びかけたりして、街との信頼関係を築き続けたんです。いまでは「『FUJI ROCK FESTIVAL』は湯沢町の誇り」とまでいわれる存在になっています。
そもそもフェスというのは、開催できる場所があってこそ成り立つもの。地域の方々に歓迎されていないままでは、継続的な開催はどうしても難しくなります。『FUJI ROCK FESTIVAL』は、“外”からやってきたフェスが、地域と共創し、文化としてその地に根づいていった——そんな事例なんです。これは、のちの日本における「フェス文化」にも大きな影響を与えたと思います。

『FUJI ROCK FESTIVAL』は「自然と音楽の共生」をテーマにしている日本最大級の野外音楽フェス(画像提供:株式会社SMASH / 撮影:宇宙大使☆スター)
津田:あとは、滋賀県出身のミュージシャン・西川貴教さんが地元を盛り上げたいという想いからはじまった『イナズマロック フェス』も印象的です。滋賀県草津市の琵琶湖畔で開催されているこのフェスでは、行政や観光協会、地元企業が一体となって運営していて、草津や守山などの紹介ムービーを上映するブースや、国指定重要無形民俗文化財である「大津祭り」のお囃子(はやし)を体験できるブースが出展するなど、滋賀県全体の情報発信の場がつくり上げられています。この市区町村や団体の枠をこえた「オール滋賀」の盛り上がりは、ほかの自治体からも「あんな取り組みをやってみたい」と注目されるほどです。

『イナズマロック フェス』は、2009年から開催されている野外音楽フェス。会場内には、滋賀県の魅力をPRする“体験型観光ブース”が設けられ、地元の団体や事業者が一堂に会する(画像提供:イナズマロック フェス実行委員会)
津田:ほかにも、2014年にはじまった茨城県結城市の『結いのおと』や、コロナ禍以降にスタートした大分県別府市の『いい湯だな!in 別府』など、地域色の強いフェスも増えていますね。
『結いのおと』は、地域振興のひとつとして、Uターンした商工会議所の職員の方が立ちあげたフェス。お寺や酒蔵などをライブ会場にしたり、アーティストが結城市の伝統産業である高級絹織物・結城紬(ゆうきつむぎ)の着物を着てパフォーマンスしたりと、地域の風景や文化そのものがフェスの一部になっているんです。
『いい湯だな!』は、温泉街のホテルや映画館が会場になり、街全体を回遊できる仕掛けが魅力。参加者は地元の中高生から40代と世代の幅が広く、市長がトークイベントに登場することもあって、行政と地元の有志が一緒に盛り上げている雰囲気があります。

神社仏閣や酒蔵、結城紬の産地問屋など、地域の文化資源をステージにした回遊型の音楽祭『結いのおと』。アーティストの演奏を聴きながら街に息づく生活や文化を体感できる(画像提供:一般社団法人MUSUBITO)
『結いのおと2025』 AFTER MOVIE

おんせん都市型音楽祭『いい湯だな!』は別府駅前の繁華街に点在する4つの会場を巡りながら、さまざまなアーティストのライブを楽しめる音楽祭。画像はライブ会場となった映画館で盛り上がる観客の様子(画像提供:AKANEKO)
フェスがもたらすのは経済効果だけではない。地域の「音楽文化を育む土壌」にも
―フェスを通じて地域が得られるメリットには、どんなものがあるのでしょうか?
津田:一番わかりやすいのは経済効果ですね。たとえば福井県福井市の『ONE PARK FESTIVAL』では、2024年の開催において、県外から多くの人が集まり、宿泊費や飲食費などの経済波及効果が約13億円(実行委員会ら発表)になったと発表されています。音楽ライブ以外のコンテンツも充実していて、地元グルメや工芸品を通して、訪れた人に地域の魅力を知ってもらえる機会にもなっているんです。

津田さんが『ONE PARK FESTIVAL』で出会って以来、大好きになった福井県の老舗・谷口屋の「竹田の油揚げ」。パリッと香ばしい表面の食感と、ふんわりジューシーな中身が絶品なんだそう(画像提供:ONE PARK FESTIVAL 実行委員会)
津田:そのほかには、地域の音楽文化が育つ土壌にもなるという点も大きなメリットだと思います。ある意味、フェスは最先端の音楽を、プロによる演奏やパフォーマンスを通して“全身で浴びる”ように体感できる場。つまり、フェスがその地域で開催されることで、東京や大阪といった都市部まで行かないと観られなかった最先端の音楽やアーティストのライブを地元で観ることができるんです。
そうした体験を通じて、「自分も音楽をやってみたい」と思う人が現れたり、地元で音楽イベントを企画しようとする動きが生まれたりと、その地域の音楽文化が育まれていきます。さらに、フェスでの反応がよければ、アーティスト側もその地域で単独ライブを開催するきっかけにもなるかもしれません。
また、たとえば『ONE PARK FESTIVAL』では地元出身のアーティストが音楽顧問としてかかわり、若手アーティストの起用にも力を入れています。単にアーティストを「呼ぶ場」ではなく、「育てる場」としての側面も持ち合わせているんです。そうした取り組みが、ひいては国内の音楽文化全体の底上げにもつながっていると感じます。

2019年からスタートした『ONE PARK FESTIVAL』のテーマは、「街全体がひとつのテーマパークになる」。 福井駅から徒歩5分の福井市中央公園で行われ、昨年は過去最多の2万7千人が来場した(画像提供:ONE PARK FESTIVAL 実行委員会)
津田:ほかにも、兵庫県伊丹市で無料フェス『ITAMI GREENJAM』を企画・運営している、一般社団法人GREENJAMは、フェスの開催にとどまらず、地元にイベントスペース&カフェ(MOGURA CAFE)などが入る複合施設「GREENJAM BUILDING」という拠点をつくっています。年に一度の開催となるフェスの高揚感を一過性のものにせず、地域とのつながりを継続的に育んでいきたい——そんな想いから、同じ地に“コミュニティビル”というかたちで、人が集える場を設けたんです。
そこでは、DJパーティーや音楽ライブなど、さまざまなイベントが行われていて、若い方や地元の人々が集える場所として親しまれています。フェスの開催時期に限らず人の交流が生まれる拠点があることで、フェスをきっかけに生まれた文化的なにぎわいが、フェス以外の時間にも持続的な地方創生の取り組みとして広がっているんです。

「GREENJAM BUILDING」は、『ITAMI GREENJAM』の主催者たちが空きビルをリノベーションして生まれた複合施設。画像は、その一角にある「MOGURA CAFE」で開催されたダンスイベントの様子(提供:一般社団法人GREENJAM)
『ITAMI GREENJAM』は関西最大級の入場無料ローカルフェス。2014年にスタートし、「市民表現のプラットフォーム」を掲げて、プロに頼らず地元の人々が企画・制作・運営をDIYで手がける「地域文化祭」のスタイルが特徴
―日本の地域フェスの強みは何だと思いますか?
津田:日本の地域フェスの最大の強みは、その多様性と地域密着性にあると思います。海外のフェスは街全体を巻き込むかたちで、大々的に開催されるものが多く見られますが、日本では、たとえば『結いのおと』や『いい湯だな!』のように、地域ごとの個性が色濃く出た「小さな個人商店のようなフェス」から、『FUJI ROCK FESTIVAL』のような都市部と変わらないラインナップを揃える「大型ショッピングモール的なフェス」まで、幅広いスタイルのフェスが存在しています。いずれも音楽だけでなく、フードや地域文化にも触れられ、その土地ならではの魅力を体験できるのが特徴です。人々は自分の趣味に加え、そのときの気分やライフスタイルに合わせて、まるで行きたいお店を選ぶようにフェスを選ぶことができます。
そういう「多様な選択肢のなかで楽しむ」というフェス文化が、いまの日本にはあると思います。それぞれの地域が自分たちらしさを出しながら開催しているのは、世界的に見てもかなり珍しいことなんです。
―では日本の地域フェスが、今後さらに発展していくためのポイントはありますか?
津田:海外とのつながりでいえば、インバウンドはひとつの大きな可能性だと思います。たとえば、『青森ねぶた祭』や徳島県の『阿波おどり』のような各地の伝統的な祭りには多くの外国人が訪れていますが、『結いのおと』や『いい湯だな!』のような地域の中小規模のフェスまでは、まだその流れが届いていないのが現状です。
でもそこに、大きなチャンスがあると思っていて。たとえば「有名な観光地はひと通り巡った」「もっとディープな日本を知りたい」という海外のリピーターにとって、地域のフェスは「次の旅」の目的地になり得ると思うんです。そうした文脈においても日本の地域フェスは大きな可能性を秘めていると感じています。
理想は「中高生の初デートの場」?地域の距離を縮める仕組み
―音楽フェスが地域にさらに根づき、これからも継続的な価値が生まれる場となっていくために、主催側にはどんな姿勢や工夫が必要だと思いますか?
津田:一番大事なのは、フェスを続けることだと思います。「街」というのは、毎日の暮らしの延長、つまり、私たち一人ひとりの日常の積み重ねによって形づくられているものだと考えています。ですから、イベントも継続していくうちにだんだん街や人に根づいていくと思うんです。
毎年やっていれば、「今年もあのフェスがあるから、開催地域のために何かしようかな」って考える人が増えてきて、その街に継続的にかかわり、支える人々——「関係人口」が増えていくのではないでしょうか。
ただし、開催地域にとって“よそ者”が集まるフェスは、非日常的なものであり、ごみの問題やマナー、騒音といった課題も抱えています。だからこそ、「開催地域の誰かには迷惑をかけているかもしれない」という前提を持ちつつ、地域の人々とていねいに関係性を築いていくことが重要だと感じています。
それでも、フェスという場を通じてそこから音楽を好きになる人や、地域に興味を持つ人がきっと生まれる。フェスが地方創生のプラットフォームみたいな場になる可能性を秘めていると思うんです。そうやって少しずつ、僕の考える理想的な「地域に開かれたフェス」のかたちに近づいていくのではないでしょうか。
―津田さんが思う、「地域に開かれたフェス」とはどんなものですか?
津田:地元のお祭り感覚でふらっと寄れるフェスですね。たとえるなら、中高生が「初デートの場」の候補にできる気軽さ。そのくらい敷居が低いことが大事だと思います。地元のお祭りも、まさにそんな存在ですよね。「日常の延長にある非日常」——そんな雰囲気こそが、理想的な「地域に開かれたフェス」だと感じます。
フェスがそういうふうに、地域に開かれた場になるための工夫は、いろいろあります。たとえば『FUJI ROCK FESTIVAL』では、前夜祭に無料で花火や盆踊りがあって盛り上がります。『イナズマロック フェス』では、無料エリアでフードや催し物を楽しめたり、ちょっとしたライブも観られたりして、若い方も多く来ているんですよ。
構えてフェスに参加するのではなく、もっと気軽に楽しんでほしい。だから「誰でも入っていきやすいフェス」にするための工夫って、すごく意味があると思うんです。

『FUJI ROCK FESTIVAL』では前夜祭として参加無料の盆踊りなどを開催。国内外のファンと地元住民が、苗場に伝わる「苗場音頭」を一緒に踊る(画像提供:株式会社SMASH / 撮影:宇宙大使☆スター)
―地域の若者や住民がフェスにかかわりやすくなる仕掛けとして、印象的な事例はありますか?
津田:たとえば、宮城県の『ARABAKI ROCK FEST.』では、地元中学校の吹奏楽部がステージに立ったり、地域の若い方がボランティアとして積極的に参加できたり、観客じゃなくて「参加者」としてもフェスにかかわりやすい場がちゃんと用意されています。そうした工夫が、フェスと地域との距離をぐっと縮めているなと思いますね。

『ARABAKI ROCK FEST.』のステージに、地元中学校の吹奏楽部が出演。2025年の開催では、ほかの出演アーティストとのコラボレーションも実現した(画像提供:ARABAKI ROCK FEST.25 Photo by Team SOUND SHOOTER)
津田:ほかにも、地域の大学や高校と連携した事例もたくさんあります。たとえば、大分県の『いい湯だな!』では、地域の大学の留学生たちが多く運営にかかわっているので、フェスにも自然と国際色が反映され、大分県内で最も在留外国人数が多い別府市らしい雰囲気づくりにもつながっています。
日本のローカルなフェスシーンは、こうした多様性と地域との連携が融合した、非常に「いい状態」にあると思うんです。行政もフェスを地域活性のチャンスととらえ、積極的にかかわるようになってきたと思います。
『いい湯だな!2023』アフタームービー
津田:一方で、フェスと地域の関係は過渡期ともいえます。フェスが広域から多くの来場者を集める存在へと成長するなかで、単に開催することにとどまらず、「その地でいかに続けていくか」が問われていると感じます。
たとえば、地域側の宿泊施設や受け入れ体制が整っていなければ、来場者が周辺地域へ流れ、結果的に経済効果が分散してしまう。また、地域に観光資源が乏しかったり、それが活かされていなかったりすれば、せっかくの集客が地域経済に還元されにくいという課題も。
だからこそ、フェスを一過性のイベントで終わらせず、地域とともに継続的に育てていくためには、宿泊や観光資源といった受け皿の整備を、地域と連携して進めていくことも重要になると思います。
それに、地元の若い方が運営にかかわったり、最新の音楽やカルチャーに触れたりすることで、次代のアーティストやクリエイターがその土地から育っていくかもしれません。
フェスと地域が互いに作用し合い、ともに成長していく。そんな好循環をつくることが、フェスの価値をより深く、より広げていくカギになるのではないかと思います。いまは、その土壌をどう整え、継続発展させていくかが問われているタイミングだと感じています。
非日常の楽しさが、日常の風景を変えていく。フェスは、地域の未来を描ける場所
―たとえば、地域活性化を促進するためのフェスを企画する人がいるとしたら、どんなアドバイスをしますか?
津田:まずは、「とにかくいろいろなフェスに行ってみてください」と伝えたいです。最近、「フェスを主催したい」という相談を受けることも増えていますが、話を聞くと、実はフェスに行ったことがあまりないという人も意外と多いんです。
動画や記事を見て参考にするのも大事ですが、やっぱりフェスの現場に足を運ばないとわからないことが多いと思います。
僕は立場上、多くの主催者の苦労を間近に見ているので、誰にでも簡単に「フェスをやろう」とは言えません。でも、日本全国には素晴らしいフェスがたくさんあります。その魅力は、現場に立ち会うことで、きっと感じてもらえるはずです。
音楽の前では、参加者や主催者といった肩書きや役割の違いがなくなり、立場の違いを超えてみんなが平等になれると思うんです。あの場では、どれだけ心から楽しめるかが何よりも大切。そんな場面を体感して、「自分の街でもこんな風景をつくりたい」と思えたなら、そこが本当のスタートラインになるのではないでしょうか。
―地方の音楽フェスで、今後面白くなりそうな注目フェスはありますか?
津田:いくつかあるなかで、ひとつ挙げるとすれば、福島県福島市で開催されている『LIVE AZUMA』。これは『SUMMER SONIC』を手がける運営会社・クリエイティブマンと、福島テレビや地元企業が共同でやっていて、音楽・フード・アートを組み合わせたフェスなのですが、そのバランスが本当に見事なんです。
大物アーティストによる華やかなライブパフォーマンスがある一方で、東北各地を代表するラーメン屋が集結するエリアなどもあって、東京など遠方から訪れた人にも、地元の人にも楽しめる内容になっています。実際、チケットが完売になったこともある人気のフェスです。こうした、地域独自の魅力と音楽フェスのエンタメ性をうまく融合させたフェスは、ここ数年で増えてきました。
さらに、『LIVE AZUMA』では今後、世界で活躍する日本のアーティストや海外アーティストを積極的にブッキングしたいと主催の方が語っていて、インバウンド層もターゲットのひとつに据えているそうです。また、地元の学校の先生から「ぜひ学生をかかわらせたい」というお話もあったそうで、学生が運営にかかわれるようなスキームの検討も進められています。2022年にスタートしたこの『LIVE AZUMA』が、これから福島でどのように根づき、育っていくのか。今後の展開がとても楽しみです。
2022年に福島で誕生した『LIVE AZUMA』は、福島駅からシャトルバスで約20分の場所で開催される、県内最大級のフェス

『LIVE AZUMA』のライブ会場の入り口近くには「球場前飲食街」が登場。福島県会津地域の地酒や、福島県産のブランド米の試食、農作物の販売などが行われ、「福島の味」を堪能できる(画像提供:LIVE AZUMA)
―最後に、読者に向けて伝えたいメッセージをお願いします。
津田:僕はフェスというものを、「理想を共有できるオープンスペース」みたいなものだととらえています。たとえば「環境問題」や「復興支援」といった、日常のなかでは少し距離を感じるかもしれない話題でも、フェスという空間だと、不思議とそういったメッセージが自然にスッと身体に入ってくることがある。フェス空間では、ポジティブな気持ちがまっすぐ届きやすいと思うんです。
そのなかで、「音楽で地域を変えたい」「街に何か残したい」という想いから「フェスで街を盛り上げる」という動きが生まれるのは、いまの時代、とても自然な流れだと感じます。フェスにはエンタメ的な側面もあるけれど、その街のことを考えるきっかけになったり、そこで交わされる対話や体験を通じて、理想を共有できたりする場所にもなり得る。
そんなフェスという場の可能性を、もっと多くの人に体験してほしいと思っています。そして、そこで生まれた想いやつながりが広がり、少しずつその地域をよりよい方向へと動かしていく——そんな循環が生まれていくといいですよね。
この記事の内容は2025年7月3日掲載時のものです。
Credits
- 取材・執筆
- 坂口ナオ
- 編集
- exwrite、CINRA, Inc.
- メイン画像撮影
- Hiroshi Maeda
- メイン画像提供
- ARIFUJI WEEEKENDERS 2025